「休むのが怖い」から「休んでよかった」へ。休職をためらう従業員への効果的なアプローチ
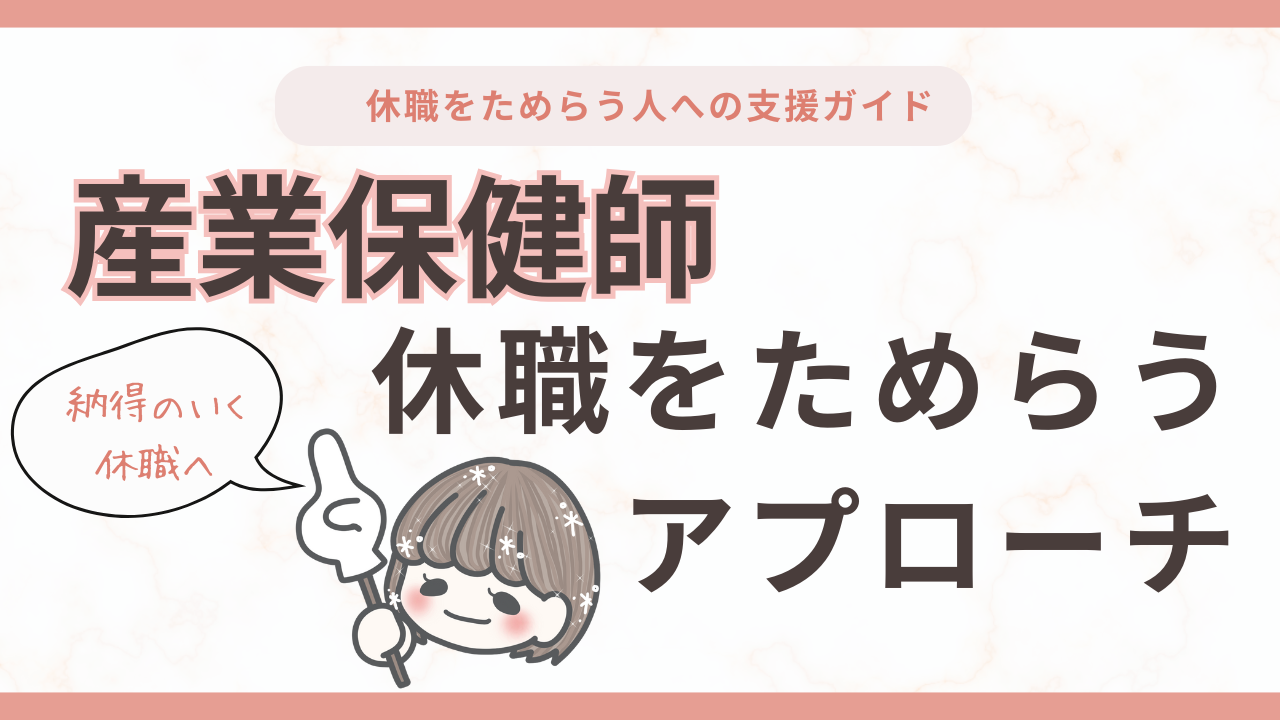
こんにちは!産業保健師のなのんです。
今回は、「休職したくない」っという従業員を療養に繋げる実践的アプローチについてご紹介していきます!
相手の事情を伺いつつ、療養への合意を得ることが重要です。
産業保健師2年目の方からこのようなご相談がありました。
 産業保健師2年目
産業保健師2年目上司からの依頼で、体調不良の部下の保健師面談を行ったところ、
メンタルで通院し服薬治療を行いながら、就労しているのですが
明らかに療養が望ましい体調だったので、療養への意向を伺ったところ
「休職したというレッテルを自分に貼ってしまう。仲間に迷惑をかけたくない」の一点張りです。
上司に業務上の支障を伺ったところ、「明らかに仕事のミスが増え、会議での発言も減り、勤怠の乱れが生じている」との情報の共有もあり、
休んで体調を整えた上で、仕事に復帰された方が良いと思っています。
どのように本人の納得を得られ、円滑な休職へ導くことができるでしょうか?
通常は、産業医面談に繋ぐこともあると思うのですが、産業医が月1回しか勤務がなく、相談できるような感じではありません。
なのんさんのご意見を伺えると嬉しいです。



難しいケースに丁寧に対応されており、素晴らしいです!
休職をすることにハードルを感じる従業員の方は多いです。
ご本人が休職を躊躇する理由を深掘りし、そのハードルを取ってあげることやご本人が納得感を持ってお休みいただくように支援することが大事です。
ためらう理由を確認し、壁を取り除く


従業員が休職をためらう理由は様々です。産業保健師は、従業員から丁寧に休職をためらう理由を丁寧に聞き出していきましょう!ためらう理由を聴取し、本人が感じている休職へのハードルを取り除くようアプローチを行うことが重要です。
従業員がメンタル休職をためらう理由
私が保健師面談をしている中で以下のような理由が従業員の方がよくおっしゃる理由になります。
経済的な不安
- 休職中の給与が減ることへの不安
- 家族に迷惑をかけたくない
- 傷病手当金などの制度を知らない、または申請手続きの方法がわからない
評価やキャリアへの悪影響
- 休職すると今期の評価が下がるという不安
- 休職によって昇進やキャリアに影響を受ける可能性への恐れ
復職への不安
- 休んでしまうと、職場での立場や役割がなくなるのではないかという不安
- 休んでも変わらない(よくならない)のではないかという不安
- 復職時にスムーズに仕事に戻れないのではないかという心配
周囲への罪悪感
- チームメンバーや上司に迷惑をかけたくないという気持ち
- 自分が休むことで、周りの業務負担が増えるのではという罪悪感
責任の重さと組織への影響(管理職など職位がある方)
- 自分がいない間に業務が滞ることへの不安
- プロジェクトの進行が停滞、あるいは中止する可能性がある
- 変わりがいない、その業務を担当できる人がいないと考える
「頑張りたい」という責任感
- 「自分がこんなことで休んでしまうほど、弱い人間だと認めたくない」「まだやれる」という思い
- メンバーがサポートしてくれていて、もっと自分も頑張りたいという責任の強さ
メンタル面での自己否定感
- 「休むことは逃げだ」と思っている
- 助けを求めることに抵抗感がある
休職への壁を取り除く
休職をためらう理由を伺った後に、休職の壁を取り除く説明を行います。
経済的な不安に対するアプローチ
- 制度の説明とサポート提供: 傷病手当金の概要、給付条件、申請手順などを説明します
- 人事労務担当者へつなぐ:傷病手当金担当者などにつなぎ、金銭的な面の詳細な説明を行ってもらう



経済的な不安をおっしゃる方へは、「休職中は傷病手当金が健保から支給されます。現在もらっている給与の6〜7割程度の金額になりますので安心してくださいね。」「傷病手当金のご担当者にお繋ぎすることも可能です!」っとお伝えし、金銭面の不安を取り除くようにしています。
評価やキャリアへの悪影響
- 評価に関する方針の明示: 休職が昇進や評価に直接影響を与えないことを明確に説明します。
- 実際の事例の共有: 匿名性を保ちつつ、自社で過去に復職し、問題なくキャリアを築いた事例があれば紹介します。
- キャリアサポート: 会社は、復職後のスムーズな業務復帰を支援するプランを作成し、本人とすり合わせを行った上でサポートしていくことを説明します。



事前に人事労務担当者へ休職することによるキャリアや評価への影響について、会社の風土としてはどうなっているのかを確認した上で、
評価やキャリアへの悪影響について懸念がある方へは、「休職することで評価が下がることはありません」「休職して一旦リセット期間を設けて、キャリアについてゆっくり考える機会を持つことも長く働く上で大事なこともあります。」っと優しくお伝えし、安心感を持ってもらいます。
復職への不安
- 復職プログラムの導入: 復職支援プログラムを用意し、段階的な業務復帰をサポートします。
- 業務引き継ぎ支援: 休職中に業務が適切に引き継がれていることを説明し、復帰時に業務が整理されていることを保証します。
- 復職前のコミュニケーション強化: 復帰時の役割や期待事項について事前に話し合い、安心感を与えます。



会社の復職プログラムを事前に確認した上で、
復職への不安がある方へは、「復職前に復職支援プログラムを上司の方が作成し、復帰前にすり合わせを行なって、段階的に業務を増やしていくようになります」「復職後は、保健師が面談を行い、体調確認を行いながら、上司・保健師・産業医・人事労務と連携しながら、復職後をサポートさせていただきます」っとお伝えし、復帰に対してウェルカムであることをお伝えします。



休職しても良くなるかどうか不安を感じている方へは、
「おやすみされた方の多くが、復帰後もしっかり働けています」っという好事例を出して、安心感を持ってもらいます。
周囲への罪悪感
- チームサポート体制の強調: 「会社全体でカバーするので心配いらない」というニュアンスとして伝えます。
- 感謝の言葉の強調: 「まずは自分の健康が一番大事です」と強調し、会社がサポートしている姿勢を示します。



本人の罪悪感のお気持ちに共感しつつ、事前に上司の方とお話しできた場合は、上司の方からは「休んでもチーム全体で回していくので大丈夫」っとおっしゃられていましたよ。っとお伝えし、罪悪感を減らすような言葉掛けでお伝えします。
「頑張りたい」という責任感
- 健康の重要性の啓発: 「健康がなければ本来のパフォーマンスは発揮できない」ということを優しく説明します。
- 前向きな療養の提案: 「今休むことで将来的にもっと力を発揮できる」と強調します。
- 成功事例の共有: 一時的な休養で復職後により高い成果を出した事例があれば共有します。



「今業務上に支障が生じているのは、能力が低いからではなくて
メンタルからくる症状でパフォーマンスを発揮できていないだけです!
なので、お休みすることで必ずパフォーマンスは復活します!」ということをお伝えしています。
メンタル面での自己否定感
- 心理的安全性の確保: 「休むことは前向きな選択です」と伝え、自己否定感を軽減します。
- 周囲のサポート強調: 「会社や同僚も応援している」というニュアンスのメッセージを伝えます。



「休むことは悪いことじゃないですよ〜人生100年時代ですから」
っと明るく、相手が少しでも元気になるようにお伝えしていますね。
主治医意見の聴取


本人から主治医意見を確認
保健師面談で、主治医意見を本人から確認しましょう。
主治医は、休んだ方がいいが、本人の希望(休みたくない)を尊重している可能性があります。



先生は、「休んだ方がいい」などおっしゃっていますか?
主治医への相談方法を説明
「会社から休暇をすすめられた」という本人からの説明では、主治医が「会社の都合」と捉えてしまう可能性があります。また、本人も休みたいと心の中では思っているが、主治医へどう伝えていいのかわからないケースも多いです。
まずは、本人の「症状」「業務上の支障」を確認した上で、以下のように相談を促す。
主治医への相談の仕方の例
「体調がしんどいため、休みたいと思っていますが、休んだ方がいいでしょうか?休む場合は、診断書を書いてもらうことは可能ですか?」
「体調が業務に支障をきたしていて、一旦療養して体調を戻したいと思っていますが、診断書を書いてくれませんか?」



診断書を書いてくださいと伝えると
多くの主治医は診断書を書いてくれますよ〜
診療情報提供書の作成
従業員が、主治医へ具体的な症状や勤務状況、職場環境を正確に伝えられていない可能性があります。そのため、主治医から休職の必要性の判断や具体的なアドバイスが得られていないこともあります。
従業員と主治医の間で情報共有を円滑に行えるように、産業保健スタッフが診療情報提供書を作成することも有効なアプローチです。
診療情報提供書の目的
・従業員の勤務状況や体調に関する客観的な情報を主治医に提供する。
・主治医から具体的なアドバイスや診断結果を得るための土台を整える。
診療情報提供書の作成ポイント
以下の情報を含めることがポイントです。
- 業務時間
- 業務内容
- 残業の有無
- 業務上の支障
- 体調面での懸念事項
また、主治医から意見が得られやすいように、産業医と保健師の連名で書類を発行したり、主治医記入欄を設けて、その欄に記入し、返信してもらうことや、主治医へ事前に電話で診療情報提供書を作成することを伝えておくのもおすすめです。
主治医記入欄には、以下の情報を含めることがベスト
・診断名
・治療内容
・主治医意見:「通常勤務可能」「業務継続が可能」「休職が必要と考える」
・業務継続に際しての留意事項
・医療機関所在地、医療機関名、医師氏名、上記を証明した日付
診療情報提供書のサンプル
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2012/124021/201233004A/201233004A0002.pdf
主治医が休職の診断書を出さない場合
主治医によっては、診断書の発行に消極的な場合もあります。



数年に1回くらいそういう主治医に当たる場合があるんですよね。。。
以下のアプローチが効果的です。
- 症状の伝え方の説明: 従業員に再度症状を明確に伝えるよう指導し、主治医が状況を正確に把握できるようにします。
- セカンドオピニオンの提案: 主治医が診断書の発行を渋る場合、別の医師の意見を求める「セカンドオピニオン」を提案します。セカンドオピニオンを受けることで、従業員の体調改善に向けた新たな治療方針が見つかる場合もあります。
様子を見る期限を決める
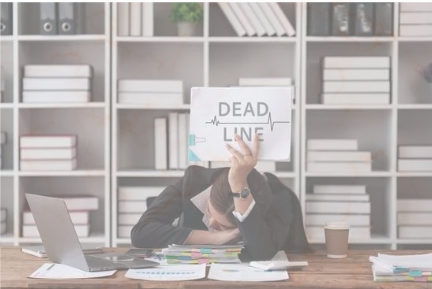
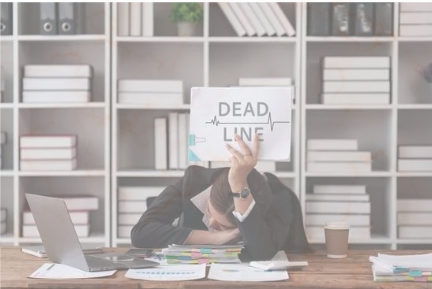
どうしても休職したくないと言う従業員に対して、可能な限り納得感を持って療養に入っていただくようにお話を続けることが重要です。
ただし、対話だけでは問題が解決しない場合もあります。ここで「この期限までに改善しなかったら休職を検討しよう」という目標を設定し、実質的な取り組みを決めることが有効です。



本人から数週間様子見させてくださいとおっしゃるケースもあります。
じゃあ、いつまで様子を見るの?っと曖昧にしておくと、
本人の療養の機会を逃しちゃうことにもつながるんですよね。
様子を見る期限を決める具体的ステップ
休職したくない理由を聞く
休職したくない理由を丁寧に聴取していきましょう。
ゴールを一緒に設定する
以下のようなゴールを設定し、従業員から同意を得ておきましょう。
- 「3週間後までに心療内科を受診する」
- 「この日までに体調が少しでも改善しなければ休職を検討しましょう」
体調を良くするための行動を決める
従業員自身がどのような行動を取るのかを言語化させます。従業員自身にも「自分の健康を保つことが必要である」という自覚を持たせる意義にもつながります。



期限を決めないと、体調が悪い状態で働き続けることで
治療に専念する機会を奪い、
療養が長引くケースもあるので、期限は決めること!
産業医面談へつながる


産業医面談を活用することで、就業可否や就業上の措置についての適切な意見を得ることができます。
ですが、産業医面談を効果的なものにするためには、産業保健師が産業医面談を依頼する際に産業医へ正しく依頼し、従業員本人自身にも産業医面談を前向きに促すことがとても大事です。
産業医面談を依頼する際のポイント
面談の目的と意図を明確に説明する
産業医に依頼する際は、以下のポイントを整理して伝えましょう!
- 面談の目的: なぜ産業医に面談を依頼するのか明確に伝えます。
- 本人の業務内容や職場環境: 業務の負担度、長時間労働の有無、職場のストレス要因などを具体的に説明します。
- 上司から見た本人の様子: 上司が懸念している点や業務上の支障、パフォーマンスの変化について共有します。
- 保健師の面談記録: これまでの面談で把握した健康状況や悩みなどの情報を産業医に端的に共有します。
- 療養が望ましいと判断したポイント: 保健師や会社としての見解も踏まえ、どのような支援が必要かについて意見を求めます。
産業医意見書の作成依頼
産業医面談の結果、就業可否や就業制限の有無に関する産業医意見書を作成してもらうことで、会社として、より適切な対応が可能になります。



産業医へ依頼する際は、産業医面談へ押し付け感がないように
産業医へつなぐ目的と産業医へどんな判断をお願いしたいのかを
正しく伝えましょう!
本人に産業医面談を促すポイント
産業医面談の目的を明確に説明する
従業員に対して、面談の意図を正確に伝えることが大切です。以下のような説明を心がけましょう。
- 健康支援のため: 産業医面談は、従業員本人の体調や業務状況を確認し、適切な健康支援のサポートを提供するための一環であることを伝えます。
- 業務継続の支援材料: 就業上の措置の必要性や業務負荷の軽減、就業上の配慮についての意見を求めることで、会社としても負担軽減策の検討が可能になることを説明します。
強制ではなく選択肢として提案する
従業員が産業医面談を「強制的なもの」と感じると拒否感が生じやすくなります。そのため、次のような姿勢で提案しましょう。
- 「希望があれば産業医の意見を参考にして、支援策を検討できます。」
- 「選択肢の一つとして産業医の助言を受けることも検討してみませんか?」



産業医と聞くと途端にブロックが発動する方もいるため
産業医面談を受けることによるメリットもお伝えすると
良いと思います”
アウト条件を決める


アウト条件を決めることも重要なポイントです。
従業員本人の健康だけでなく、会社の安全配慮義務に基づく正当な対応の実施にもつながります。
状況が改善されない場合のアウト条件を先に明確にしておくことで、従業員自身の責任の意識も高め、ダラダラ体調が悪い状態で働き続けることを防ぐことも可能です。
アウト条件の具体例
下記のような条件をあらかじめ従業員と共同で決め、互いに理解しておくことが効果的です。
- 月に2回以上の突発休暇が発生した場合、早退や遅刻が1回でもあった場合
月に2回以上の突発な休暇がある場合や早退や遅刻は、体調の悪化による業務上の支障が出ていると判断せざるを得ません。 - 保健師への定期的な体調報告を怠る場合
定期的な体調報告を怠ってしまうような健康状態であると判断せざるを得ず、自己保健義務を果たしているとは言えないため、体調の回復に努める必要があります。 - 希死念慮がある場合
早急に休職し、安全な環境で療養することが優先となります。 - 体調が悪化している場合
働きながら体調を良くしていくことは難しいため、体調の回復に努める必要があります。



面談記録に必ず記録として残しておくことがベスト!
関係者会議を開く


産業保健師として、休職を渋る従業員への対応において関係者会議を活用する方法もあります。
人事労務担当者、産業医、保健師、本人、上司といった関係者が集まり意見をすり合わせることで、より効果的かつ納得感のある対応が可能です。
関係者会議の意義
休職が必要かどうかの判断は、会社にとっても本人にとっても重要な決断です。産業医や保健師だけが療養の必要性を訴えると、本人が納得しないケースも少なくありません。関係者会議では、複数の視点から状況を共有し、以下のような判断基準を設けることで、本人や会社双方の合意形成がしやすくなります。
関係者会議で決めるポイント
・療養が必要かどうか
・業務上の配慮がどこまで可能か
・いつまで様子を見るか、その期限と条件
関係者会議の事前準備は必須
関係者会議が円滑に進むためには、事前準備が不可欠です。以下の手順をご参考までに。
本人以外で事前打ち合わせや認識共有を行う
- 人事労務担当者、産業医、保健師、上司で事前ミーティングを行い、共通のゴールを設定します。
- 「療養が必要かどうか」「業務上の具体的な配慮内容」「配慮の期限」などについて話し合い、方向性を共有しましょう。
必要な情報の共有
- 本人の業務内容や負担状況
- これまでの産業医・保健師面談での経過
- 上司から見た勤務状況や本人の様子
- 休職制度や人事制度面からの意見
- 産業医の所見(可能であれば事前に意見書を準備)



本人以外で認識を統一させ、会社としての方向性を
示すことがとても大事です!
関係者会議の進行ポイント
会議の目的を明確にする
「今後の勤務継続の可否とその条件を話し合う場です」という趣旨を従業員が受け入れやすい言葉を使いながら、優しく冒頭で共有します。
現状の共有
- 本人から体調や勤務に対する自己認識を説明してもらいます。
- 上司から業務上の支障やチームへの影響の有無、パフォーマンスの変化について報告してもらいます。
- 保健師や産業医から健康状態の見立てと療養が必要な理由を説明します。
選択肢の提示
- 療養の必要性について関係者全員で議論します。
- 就業継続の条件(軽作業、残業禁止、受診機会の確保など)や期限を明確にします。
- 必要な場合は療養開始の具体的なスケジュールを設定します。
本人の意向確認
- 強制的に休職を促すのではなく、本人の納得感を重視します。
- “ご自身の体調管理を最優先に考え、会社もサポートしていきます”といった配慮の言葉をかけます。
合意形成のポイント
以下のポイントを意識しながら、合意形成することがおすすめです。
期限の設定:“〇月〇日までに改善が見られなければ療養に入る”など具体的な期限を設けます。
アウト条件の明確化:月に突発的な休暇が一定回数を超えた場合や希死念慮が見られた場合など、具体的な基準を提示します。
役割分担の明確化:人事、産業医、保健師、上司それぞれがサポートする内容を確認します。



産業保健師として、単独で対応するのではなく、チーム全体で支援する体制を築くことが重要!
まとめ
今回は、休職をためらう従業員への実践的なアプローチ方法をご紹介しました。
従業員が休職をためらう理由を丁寧に聴取し、壁を取り除くだけでなく、個別の事情に合わせた適切な対応を行うことが重要です。経済的な不安やキャリアの心配、復職への不安など一つ一つの理由を丁寧に解消することで、従業員が安心して必要な療養に進める環境づくりが可能になります。
また、企業側の安全配慮義務の履行という観点からも、療養がダラダラ延長されることは企業にとってリスクでもあります。そのため、様子見の期限やアウト条件を決める、産業医面談へつなげる、関係者会議の開催などを行い、リスクの低減を図るだけでなく、従業員が納得感を持って休職に入れるようにアプローチすることが大事です。



休職をためらう従業員への対応に悩んでいる産業保健師さんは、
ぜひ今回ご紹介した対応方法を実践して、本人および会社の支援を
行っていきましょう!
もし、メンタルヘルス不調者への対応でお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!
入門・実践コース
産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。


\ 産業保健師のプロになる/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!

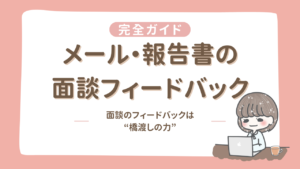
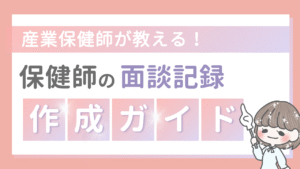
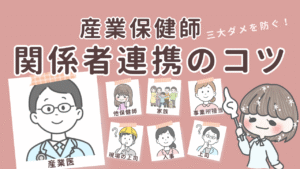
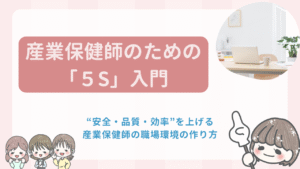
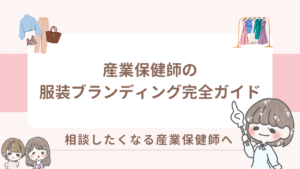

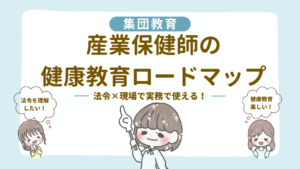
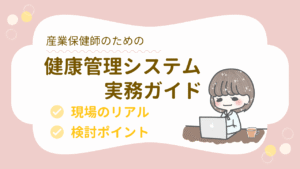
コメント