【保存版】定期健康診断の基礎から実務まで!定期健康診断完全ガイド
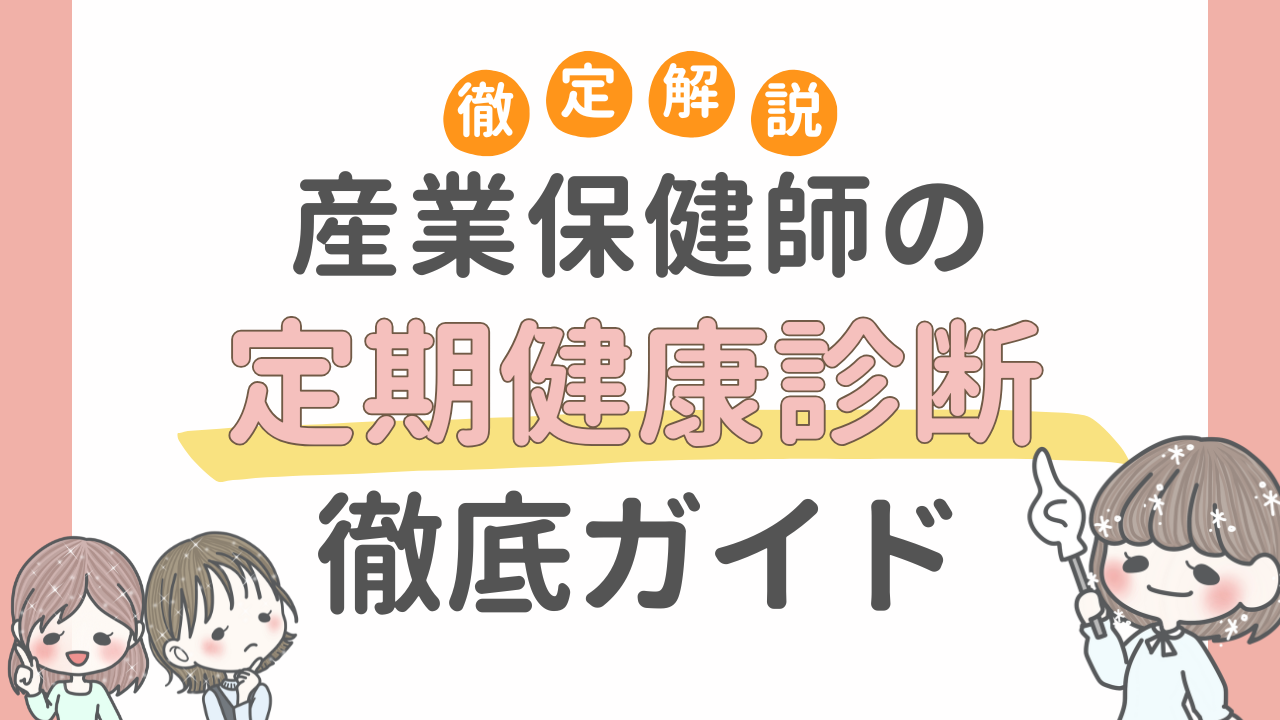
こんにちは、産業保健師のなのんです。
定期健康診断は、従業員が年に1回必ず受診できるように、産業保健師が日程調整や受診勧奨を行う“年間の中でも一大イベント”のひとつ。
とはいえ、産業保健師の皆さん――定期健康診断について、こんな戸惑いや悩みはありませんか?
 産業保健師2年目
産業保健師2年目健診機関との連携や社内の調整に時間を取られ、これって産業保健師の仕事?っと感じています。



「受診日が現場の繁忙期と重なる」「在宅勤務でクリニックが遠い」など、現場事情に合わせた運用ルール作りに行き詰まっています。



定期健診の受診率が伸びず、期末が近づくたびに未受診リストとにらめっこしています。



よく頑張っていらっしゃいますね。
「健康診断は毎年実施しているけれど、それぞれの法律の要件や種類が多く、ごちゃ っとして分かりにくい――」
そんな声をよく耳にしますし、私自身も新米産業保健師だった頃は、各健診の種類や受診項目の違いを把握するのに必死でした。
そこで本記事では、法令・運用・現場支援の3視点で定期健康診断を徹底解説。
産業保健師が “いま抱えている悩み” を整理し、明日から使える実践ノウハウとともにお届けします!
- 定期健康診断の法令→会社の運用が“一本の線”でつながる
- 定期健康診断における産業保健師の役割が理解できる
- 受診率を上げる仕組みと“未受診者対応”の考え方がわかる


- 新卒から産業保健師歴約15年
- 産業保健師としての企業での活動実績
- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社
- オンライン健康セミナー 約10回/年
- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年
- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供
基礎から実践まで、“できる産業保健師”を育成!
定期健康診断とは


まず、いわゆる「健康診断」は、労働安全衛生法第66条に規定されています。
健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断の二つに分けられています。
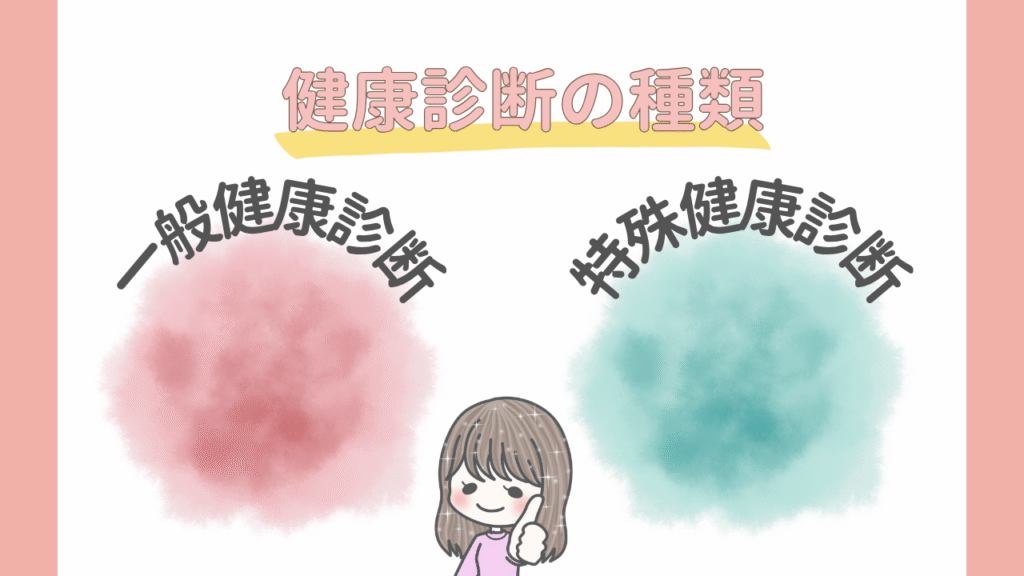
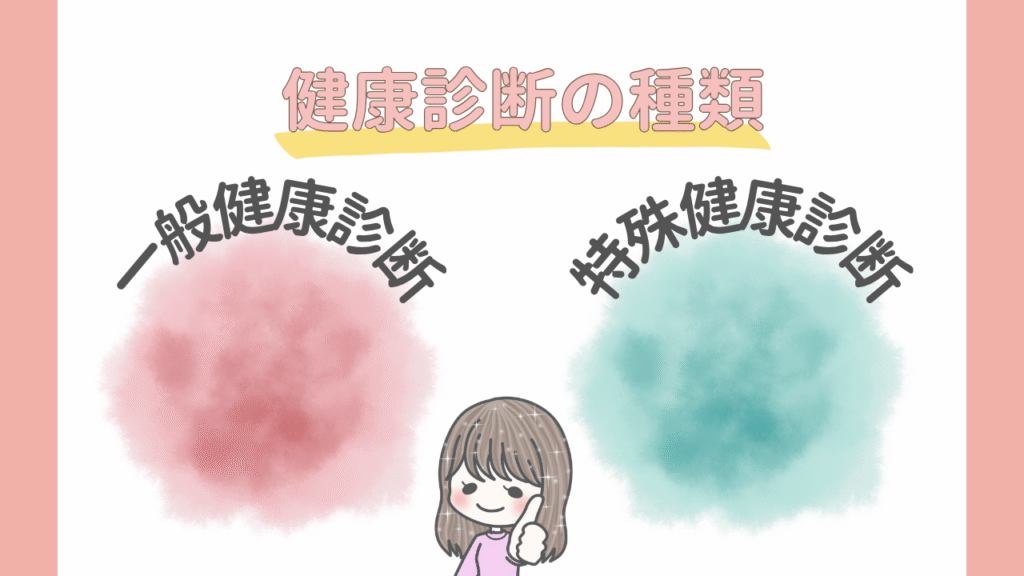
定期健康診断は、一般健康診断の中に含まれる健康診断の一種。
| 一般健康診断の種類 | 法令条文 | 実施タイミング |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 安衛則 第43条 | 採用時 |
| 定期健康診断 | 安衛則 第44条 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 安衛則 第45条 | 6ヵ月以内ごとに1回 など |
| 海外派遣者の健康診断 | 安衛則 第45条‑2 | 派遣前・帰国後 |
| 給食従事者の検便 | 安衛則 第47条 | 年2回以上 |
| 自発的健診 | 安衛法 第66条‑2 | 任意 |
法律における「定期健康診断」の目的
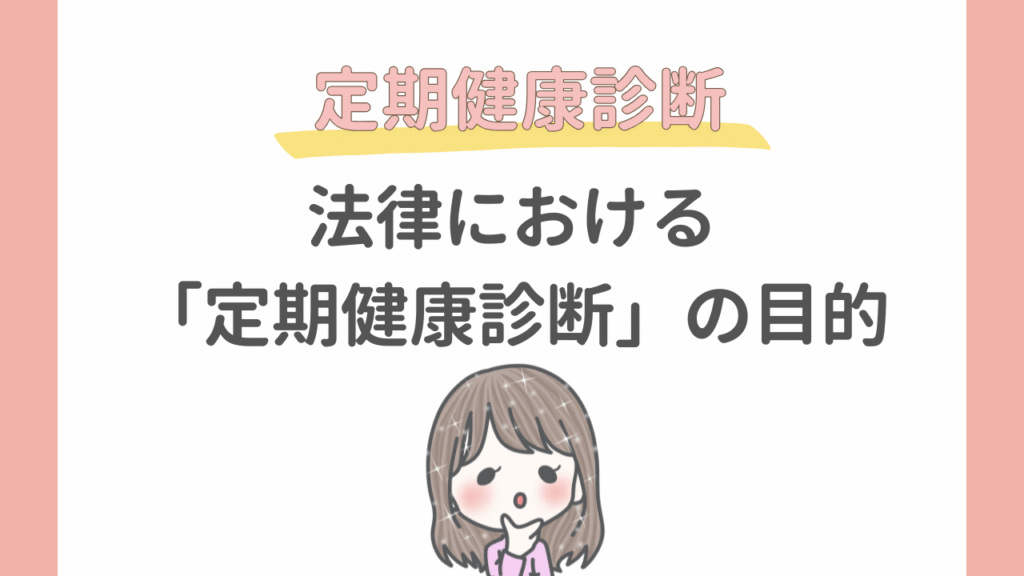
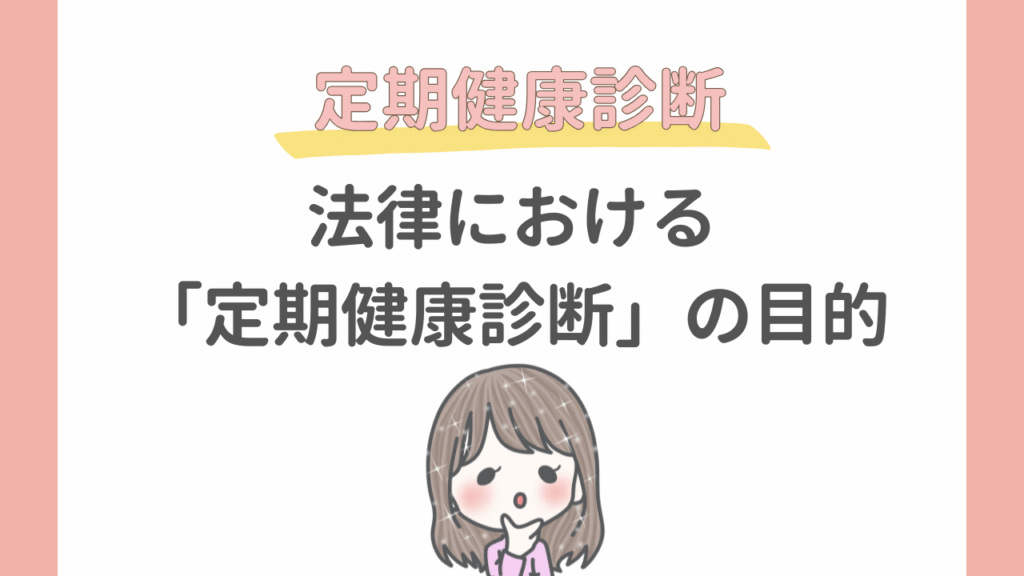
定期健康診断は、労働安全衛生規則第44条に明記されており、事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、受診項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(※)第45条第1項に規定する労働者:特定業務従事者



特定業務従事者に関しては、定期健康診断の受診項目と同様であるため、定期健康診断+特定業務従事者健康診断の2回受診は不要になります。
労働安全衛生法では、業務が原因で、労働者が疾病にかかったり、疾病が悪化することを防ぐため、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に、年1回、健康診断を実施することを罰則付きで義務付けています(費用は全額事業者負担。労働者にも受診義務あり)。労働基準局安全衛生部より
定期とは、毎年一定の時期に、という意味であって、その時期については各事業所毎に適宜決めさせること(昭二三・一・一六基発第八三号、昭三三・二・一三基発第九〇号)



実施時期は会社(または事業所)で決めてOKですが、異動者は要注意。異動のタイミングで年1回の受診を逃しやすいので、会社全体で実施月を固定するのがおすすめです。



受診期間の目安:従業員1500人未満=1か月、3~4000人以上=3か月で全員が受診できる期間を会社方針として設定することがおすすめです。
① 1年以上の長さで雇用契約をしているか、または、雇用期間を全く定めていないか
あるいは既に1年以上引き続いて雇用した実績があること。
② 一週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上であること。
※ 上記の②にあたらない場合でも、①に該当し、同種の業務に従事する労働者の一週間の所定労働時間の概ね
2 分の 1 以上の労働時間数を有する者に対しても、健康診断を実施することが望ましいとされています。
産業保健における「定期健康診断」の目的
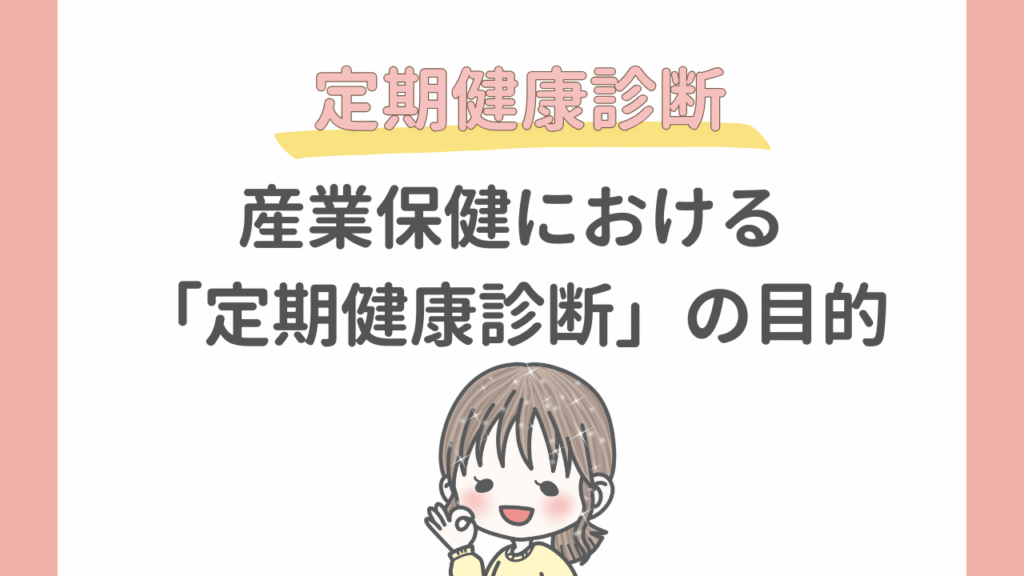
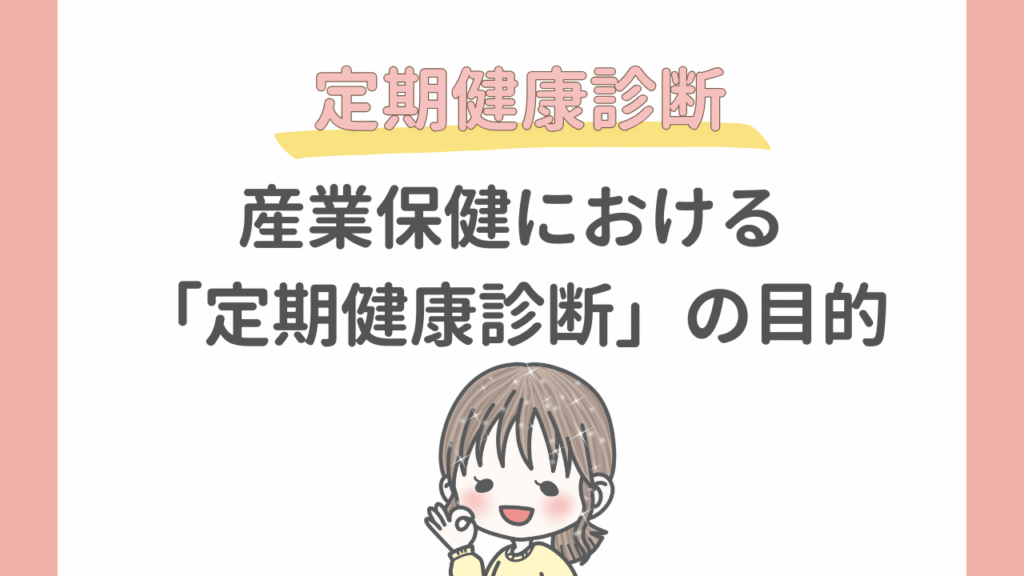
産業保健における一般健康診断の目的は、一言で言うと「適正配置を行うこと」「就業判定を行うこと」です。
そのため、一般健康診断の中の「定期健康診断」の目的も、「適正配置」「就業判定を行うこと」になります。
一般健康診断は、過労死防止や高齢化対策の一環として、また、特定業務等への適正配置のために、メタボリックシンドロームや生活習慣病を含めた全般的な健康状態の把握と、作業環境や作業条件等による健康影響・健康障害の早期把握を目的としている。また、健康障害が明確な場合には、「要休業」として療養が必要であると判断する「病者の就業禁止(安衛則第61条)」の観点から、これも目的のひとつに挙げられる。
はじめての嘱託産業医活動p38より
会社における「定期健康診断」の目的
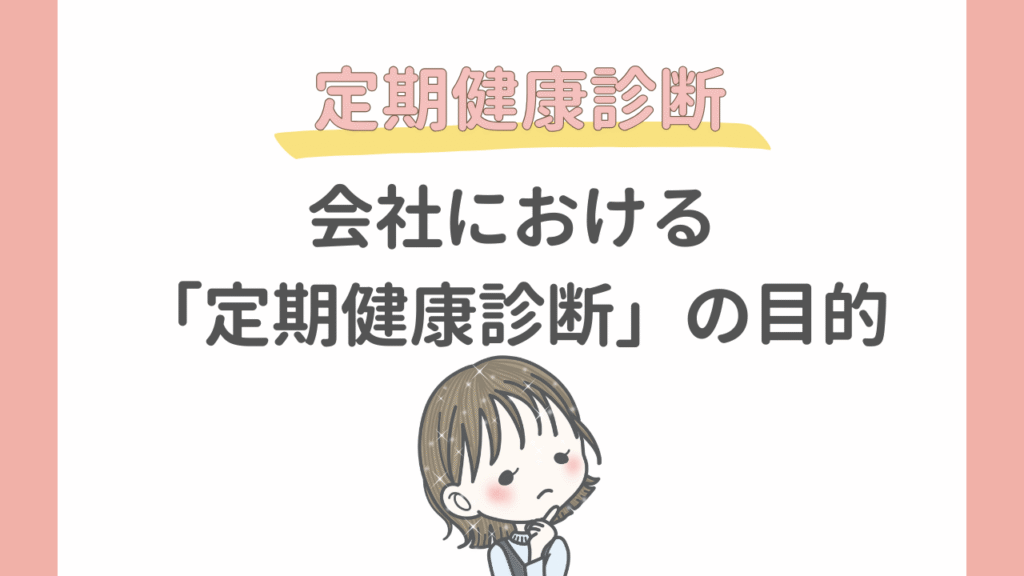
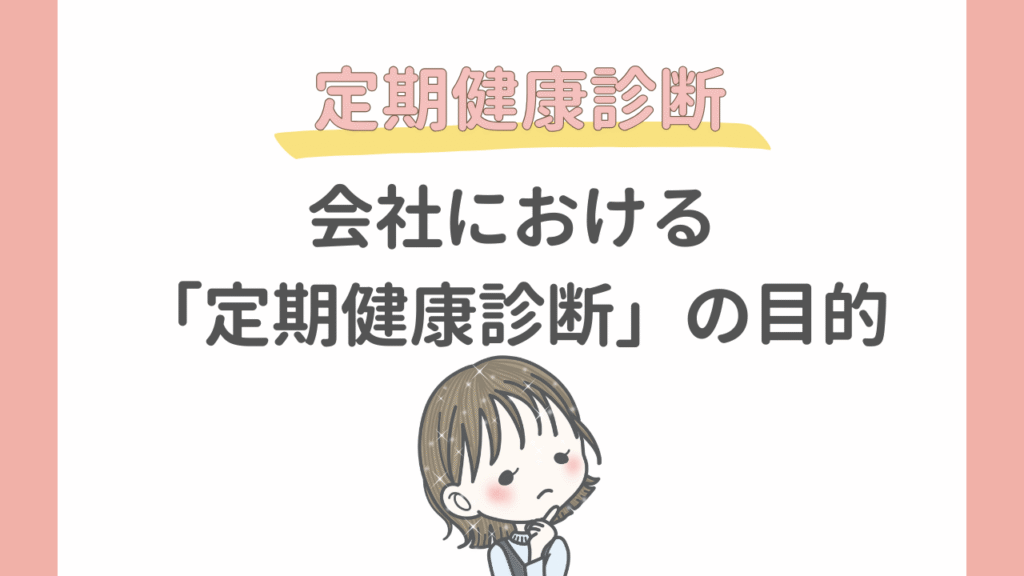
会社における「定期健康診断」の目的は、所属する企業によって異なるため確認が必要になります。
しかしながら、会社における定期健康診断の目的は、主に以下の点に集約されます。
- 法令遵守(労働安全衛生法第66条)
- 業務に起因する健康障がいを未然に防止すること
- 就業の可否や適正配置の判断材料とすること
- 従業員の健康状態を把握し、病気の早期発見・予防を行うこと
- 従業員の健康維持・増進と生産性の向上
つまり、定期健康診断は「個々の従業員の健康リスクを把握し予防・早期発見につなげる」「適切な人事配置や労務管理を実現する」「法令遵守として会社が果たすべき責任を履行する」という複合的な意義があります。
定期健康診断の受診項目を把握する
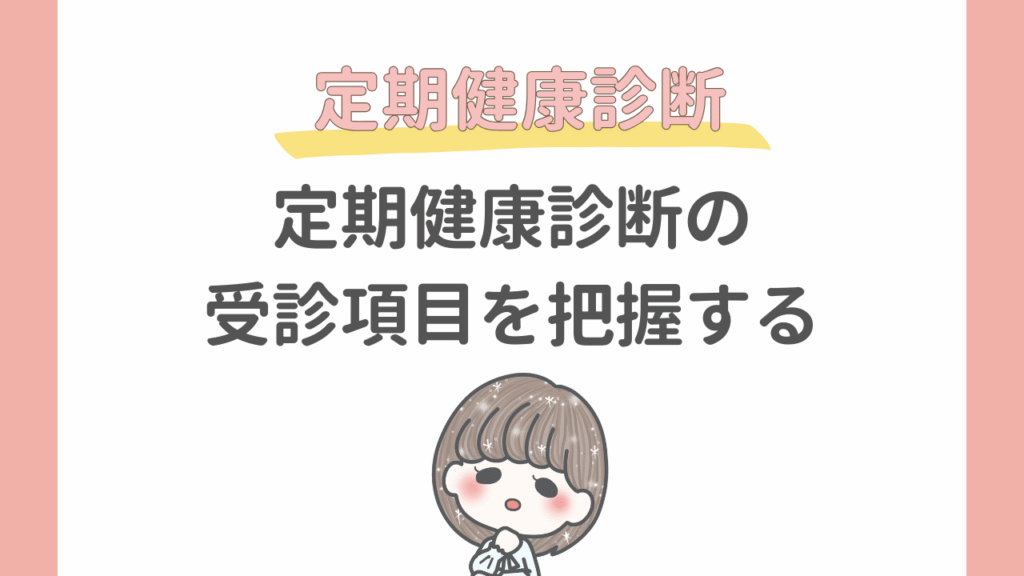
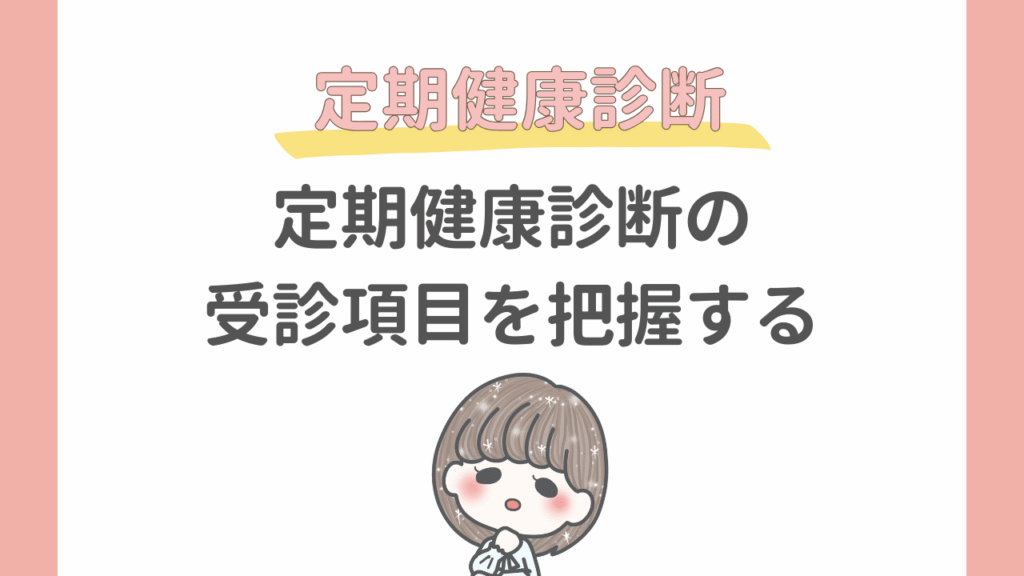
定期健康診断の現場運用でつまずきやすいのが、「法定必須」と「会社独自(任意追加)」の切り分け、そして年齢別の例外(35歳特例など)です。ここが曖昧だと、「受診項目漏れ」や「省略可の項目を再度受けさせる」など現場の負担とミスの温床になります。
この章では、まず法律上の受診必須項目を年齢別に確認し、次に会社で実施している項目との違いを整理していきましょう。さらに、各項目の実施目的(関連する疾患・リスク)を短く押さえ、最後に自社用の「健診項目確認表」で棚卸しすることで、法律及び自社での定期健康診断の理解が深まります。
法律上の受診必須項目(定期健康診断)
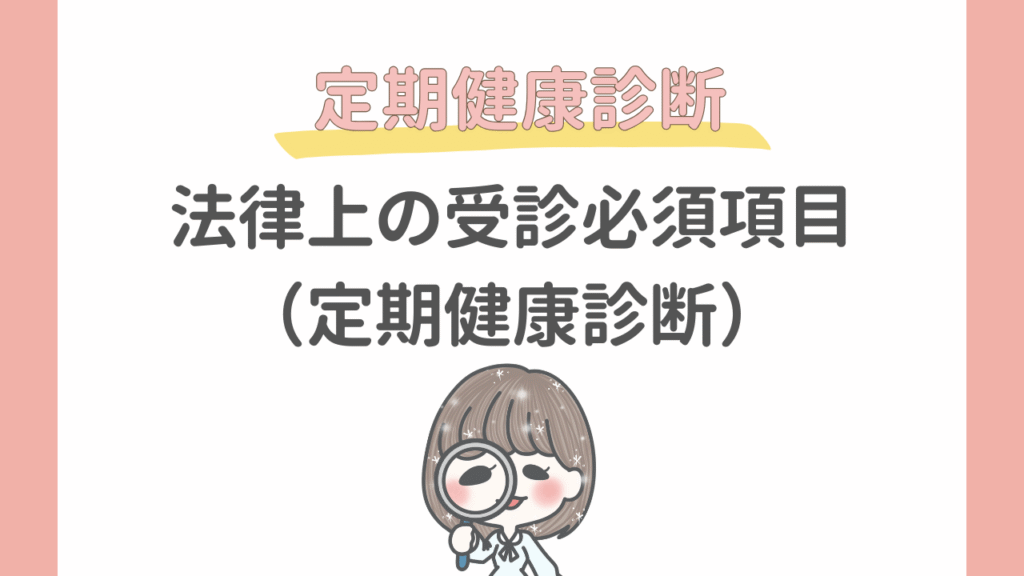
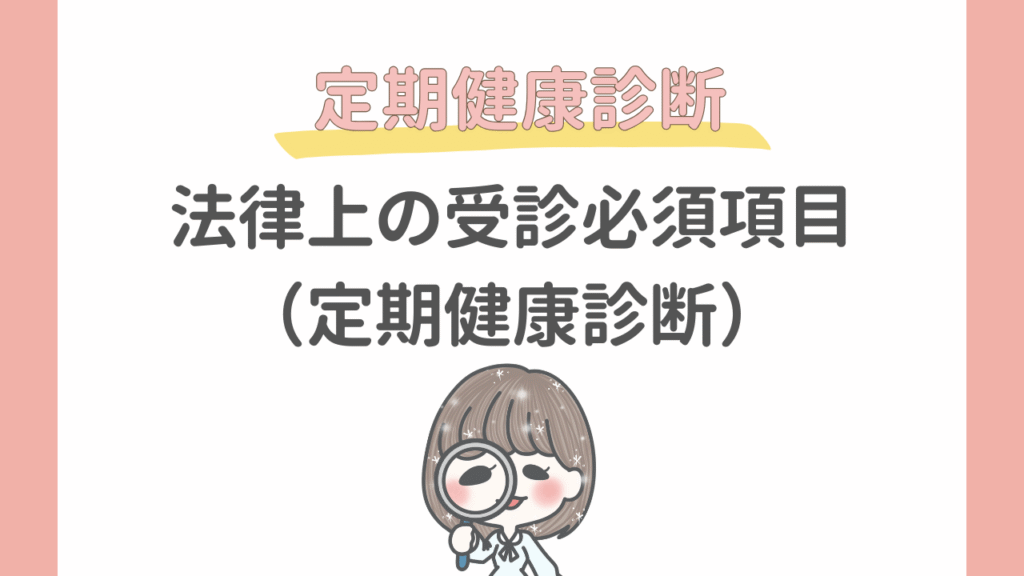
法律上の受診必須項目は以下になります。
| 項目 | 20歳未満 | 20〜34歳 | 35〜39歳 | 40歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 既往歴・業務歴・自他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身長 | ○ | △ | △ | △ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | △ | △ | △(※35歳のみ○) | ○ |
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部 X 線or喀痰 | △ | △(※20・25・30歳のみ○) | △※(35歳のみ○) | ○ |
| 心電図 | △ | △ | △※(35歳のみ○) | ○ |
| 貧血検査 | △ | △ | △※(35歳のみ○) | ○ |
| 肝機能 | △ | △ | △※(35歳のみ○) | ○ |
| 血中脂質 | △ | △ | △※(35歳のみ○) | ○ |
| 血糖 | △ | △ | △※(35歳のみ○) | ○ |
| 尿検査(尿糖、尿蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ |
法令では、医師が「不要」と判断した項目は省略しても差し支えありません。
ただ、実務では年齢ごとに項目が違うと案内・予約・結果管理が複雑になるため、全従業員に同一の項目セットで受診してもらう運用を採用する企業が少なくありません。
また、従業員が市区町村の健診結果を提出した場合、法定必須項目を満たしていれば、年齢により省略可能な項目(任意項目)が未実施でも追加の再受診は求めない取り扱いにしている会社が多いのが実情です。最終判断は会社の方針として事前に明文化し、例外対応を減らすのが安心です。
健診項目の実施目的を理解する
定期健康診断の実施項目の主な目的は以下になります。
| 項目 | 目的・関連疾患(抜粋) |
|---|---|
| 身長・体重・腹囲 | 代謝異常・循環器リスクの早期把握 |
| 視力・聴力 | 視聴機能の変化・業務起因性障害の早期検出 |
| 血圧 | 虚血性心疾患・脳血管疾患の危険因子を若年期から定期評価 |
| 胸部 X 線/喀痰 | 結核・呼吸器疾患のスクリーニング |
| 心電図 | 不整脈・虚血性心疾患・高血圧性心疾患の把握 |
| 貧血検査 | 栄養不良・高齢期の貧血を把握 |
| 肝機能 | 肝障害を早期発見し重症化を防止 |
| 血中脂質 | 虚血性心疾患・脳血管疾患ハイリスク者のスクリーニング |
| 血糖 | 糖尿病と関連する心血管リスクの評価 |
| 尿検査 | 腎不全リスクを含む循環器疾患の早期把握 |
労働安全衛生法に基づく一般健康診断について 厚生労働省 労働基準局安全衛生部
所属する会社で実施している受診項目を把握しよう
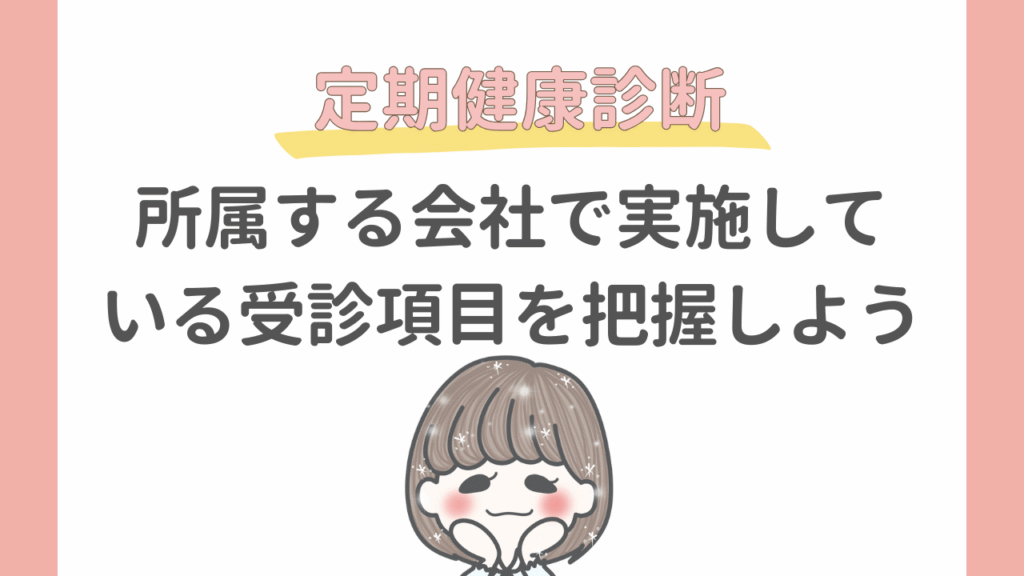
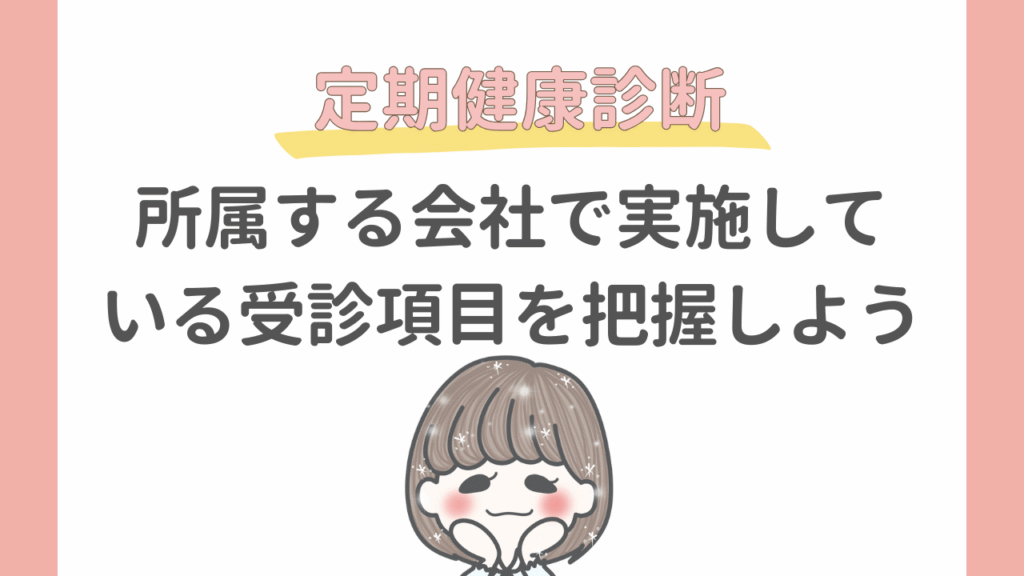
会社ごとに受診項目や年齢区分、追加オプションは異なります。現場で迷わないための第一歩は、「どれが法定必須/どれが会社追加(任意)/なぜ測るのか(任意項目の目的)」を整理することからスタートです。
健診項目確認表をダウンロードし、所属する会社の健診項目を整理してみましょう!
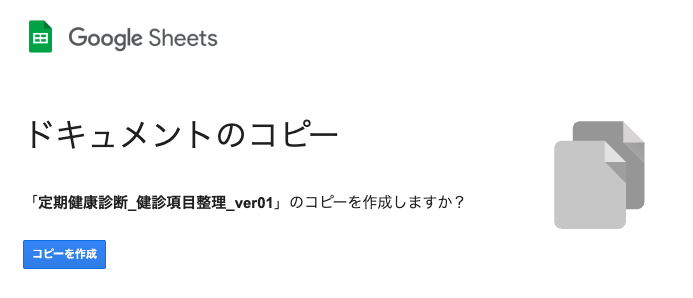
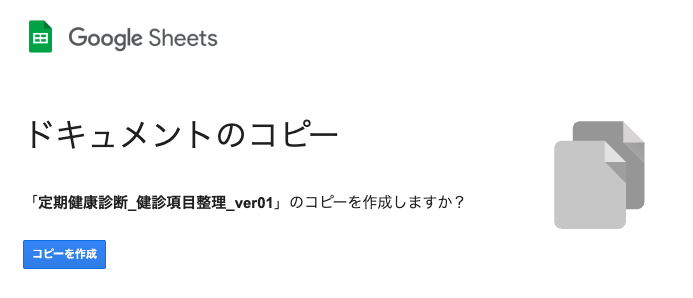
- 健診項目確認表の法定必須項目を確認
- 自社の健診項目を入力し、必須、任意を把握する
- 事業所や工場ごとに定期健康診断の健診項目が違う場合は、全て健診項目を把握し、入力を行う



会社内でも事業所や各工場によって定期健康診断の項目が違う場合がありますので、現状を把握し、必要に応じて、項目を統一できるようにしていきましょう!
定期健康診断の実施における産業保健師の役割・業務
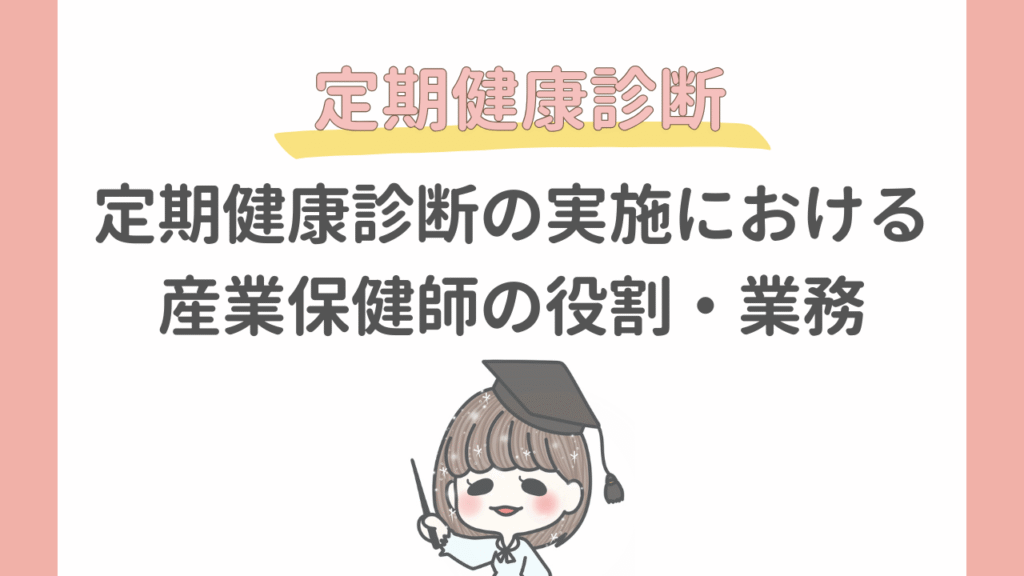
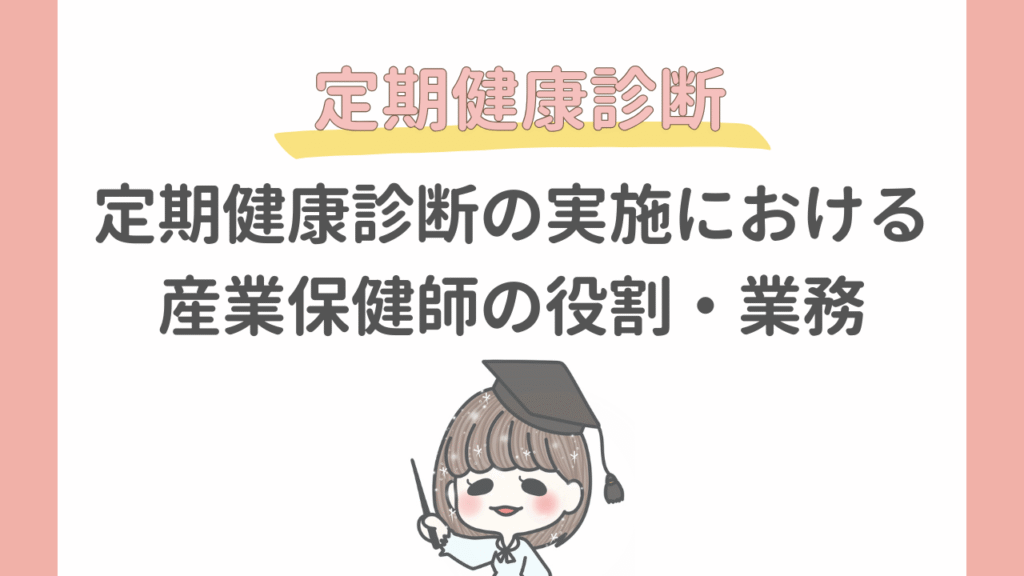
定期健康診断から事後措置における産業保健師の主な役割や業務は以下になります。しかし、会社によって、産業保健師に求められる業務範囲は変わってきますので、人事労務担当者との業務の線引きや求められる業務を把握しましょう。
- 受診促進・運営管理
- 健康診断の日程調整や受診対象者リスト作成、健診機関との調整、健診実施案内や受診率の管理など、健診実施までの運営面を担います。
- 健診結果の確認・判定・抽出
- 面談と保健指導
- 健診業務の評価、改善提案
- 今年度の健康診断運営業務の課題抽出→改善提案。
- 課題抽出のポイント:受診率、未受診者対応、受診勧奨実施工数の増減、業務フロー等。
- 昨年度の健康診断運営業務の改善後の評価。
- 今年度の健康診断運営業務の課題抽出→改善提案。
会社によっては、定期健康診断を事後措置まで含めた一つのプロジェクトとして運用している場合があります。
ここでは、その中で産業保健師が担う主な役割についてもご紹介します。
まとめると、「健康診断の実施~結果フォロー、保健指導、働きかけ、施策提案」まで幅広い実務を担い、事業場の健康リスク低減、法令遵守など人と会社と守ることに貢献する役割です。



定期健康診断で産業保健師に求められる業務は会社ごとに異なります。まずは自社の期待(業務範囲・優先順位・期限)を確認し、必要に応じて人事と役割分担をすり合わせたうえで、その要望に沿って対応しましょう。
定期健康診断を実施しないとどうなる?
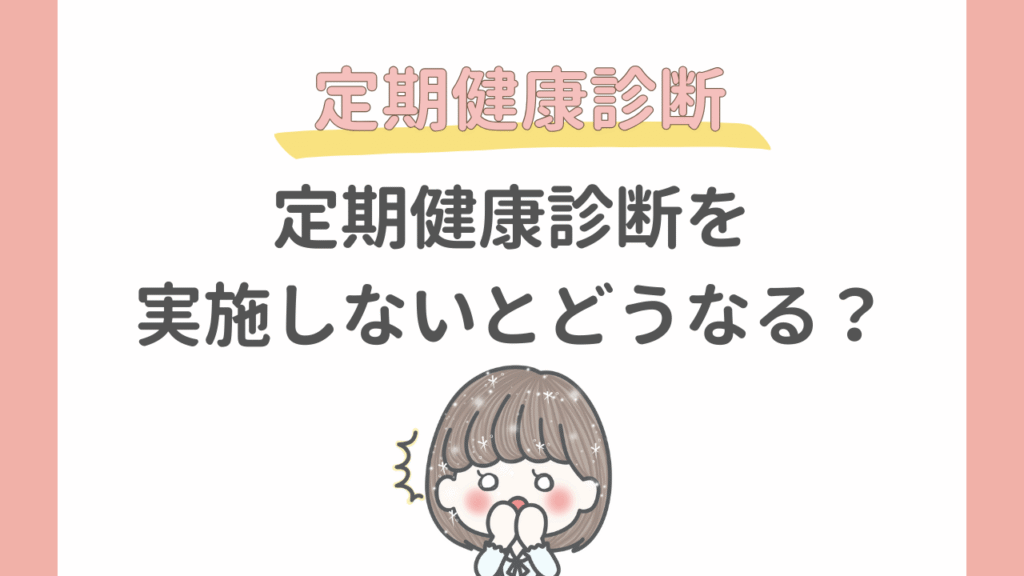
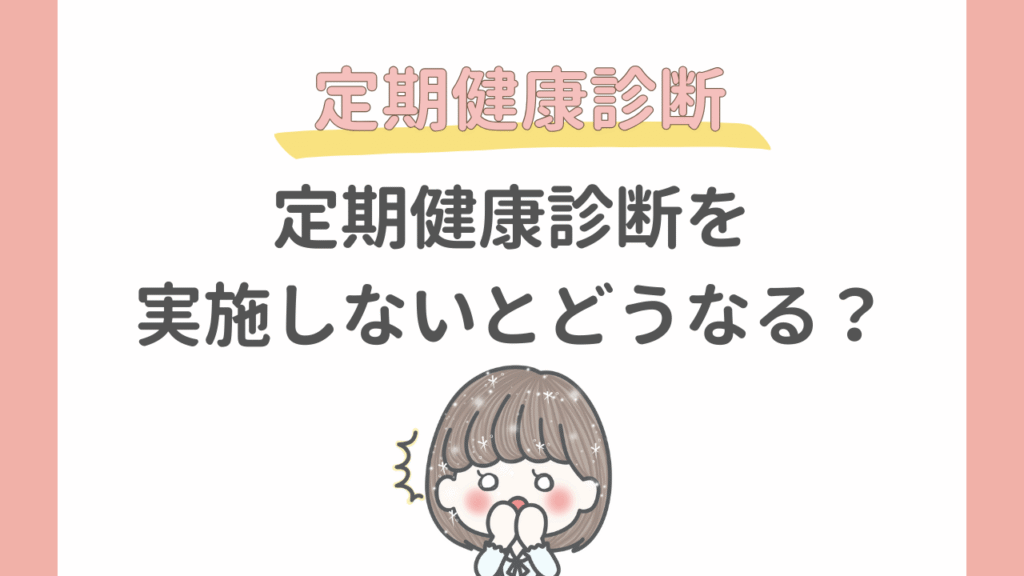
定期健康診断を実施しない場合の法律上の罰則と企業リスクを理解しておきましょう。
労働安全衛生法第120条に基づき「50万円以下の罰金」が科される罰則あり。健康診断未実施が発覚した場合、まず労働基準監督署から指導が入ります。それでも改善されない場合、最大50万円の罰金刑が科せられることになります。



中小企業以上の企業にとっては、法律上の罰則は痛くも痒くもないという状況があります。法律面以外の企業のリスクを理解し、受診の必要性について説明できるようにしておきましょう!
- 安全配慮義務違反による損害賠償リスク
- 健康診断の未実施により従業員が健康被害を被った場合、会社が安全配慮義務違反として民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります。
- 行政指導や企業信用への悪影響
- 行政(労働基準監督署)の立ち入りや指導が入ります。また、社会的信用を失い、採用活動や取引にマイナス影響が及ぶことがあります。
- 従業員の健康リスク・労務管理問題
- 未然に健康障害や重大な疾病を発見できず、重症化や長期欠勤、労働災害などにつながるリスクが高まります。
- 健康経営銘柄/優良法人の認定取消
- 会社が健康経営銘柄/優良法人の認定を受けている場合、認定取消となります。
定期健康診断:受診率向上&受診率 100 %を実現する7つの鍵
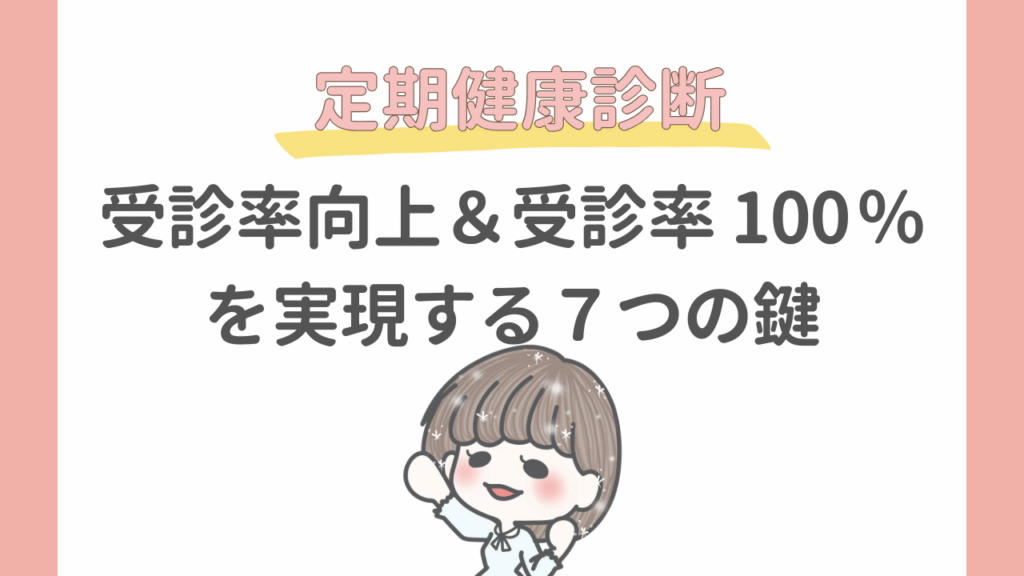
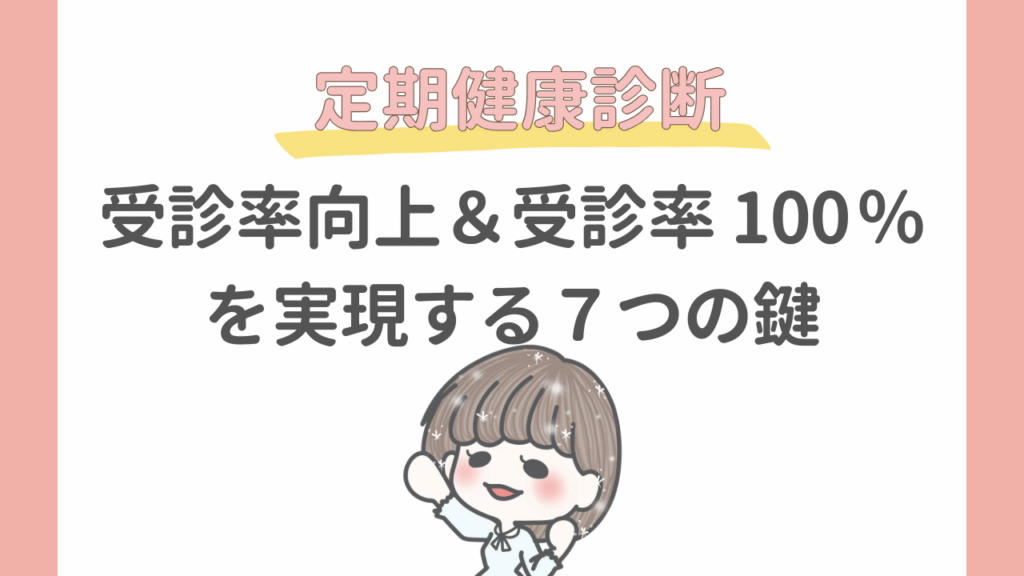
受診率100%にするためには、さまざまな取り組みが必要になってきます。その取り組みを行なっていくことで、会社として、定期健康診断は受診するものという風土を定着させることが可能になります。
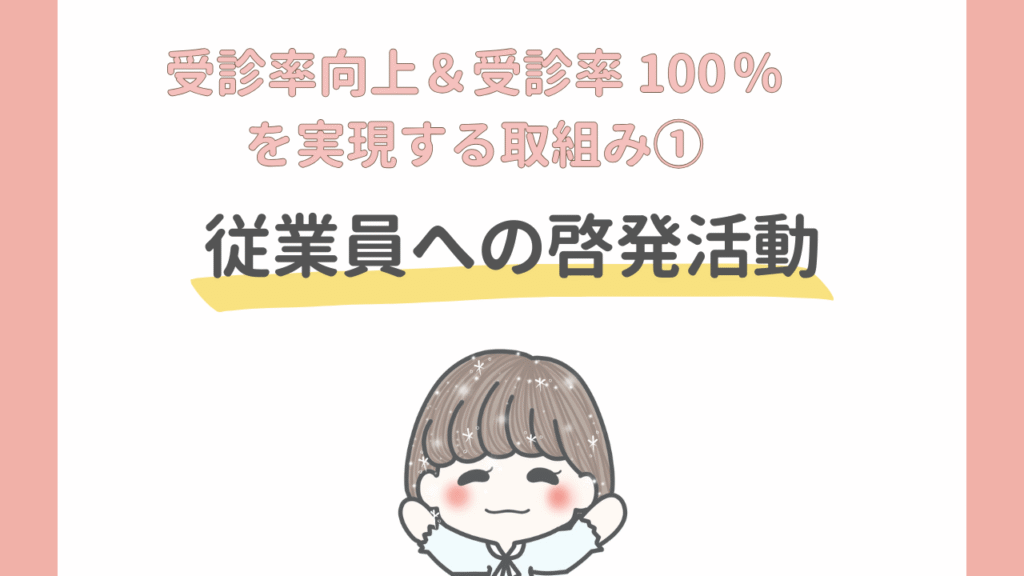
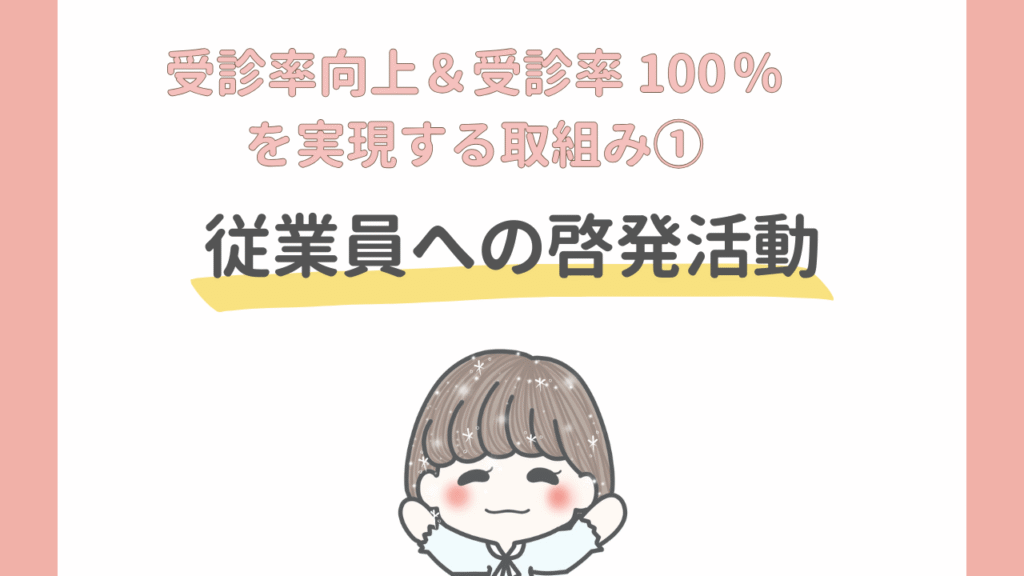
- 「受診義務」「安全配慮義務」「自己保健義務」をわかりやすく説明する資料で全社提示。
- 所属する企業の健康診断に関する目的や意義の周知。
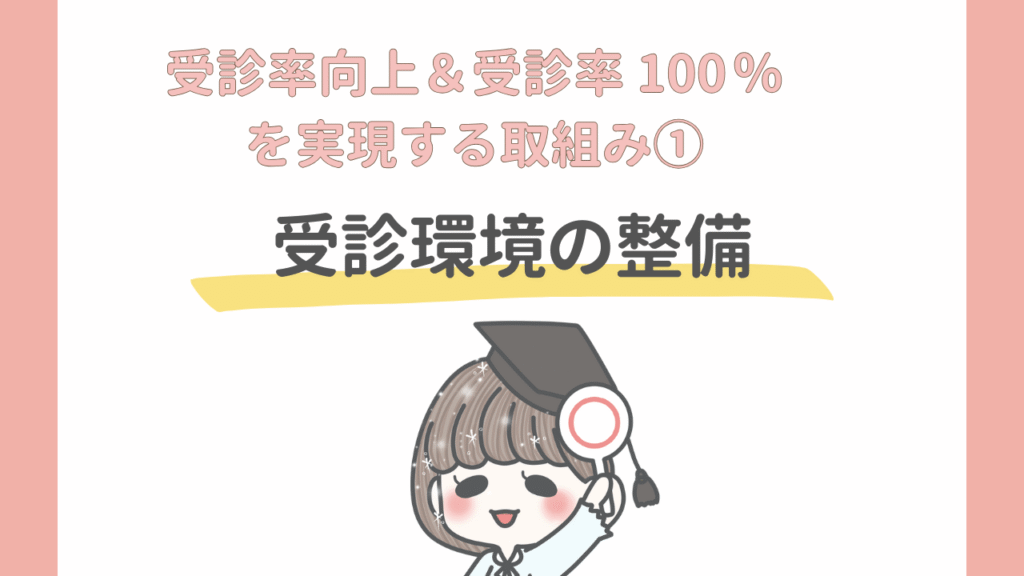
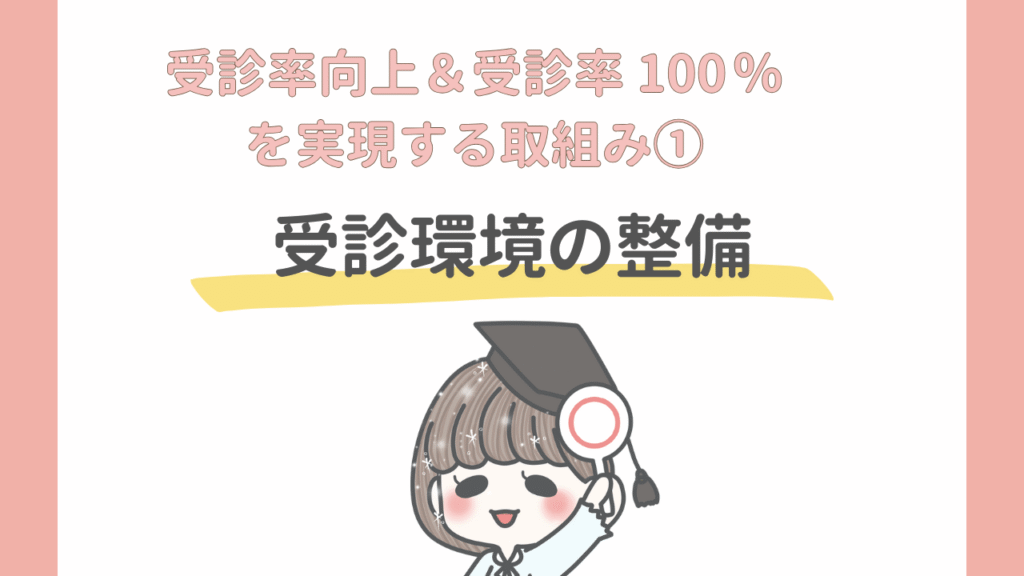
- 繁忙期を避けた受診期間の設定。
- シフト調整のご協力を伺う。
- 効率的な受診管理のための事業所担当者やライン長との連携。
- 就業時間内に受診できるように人事と調整。
- 健診バスなど事業所内で受診できるように調整。
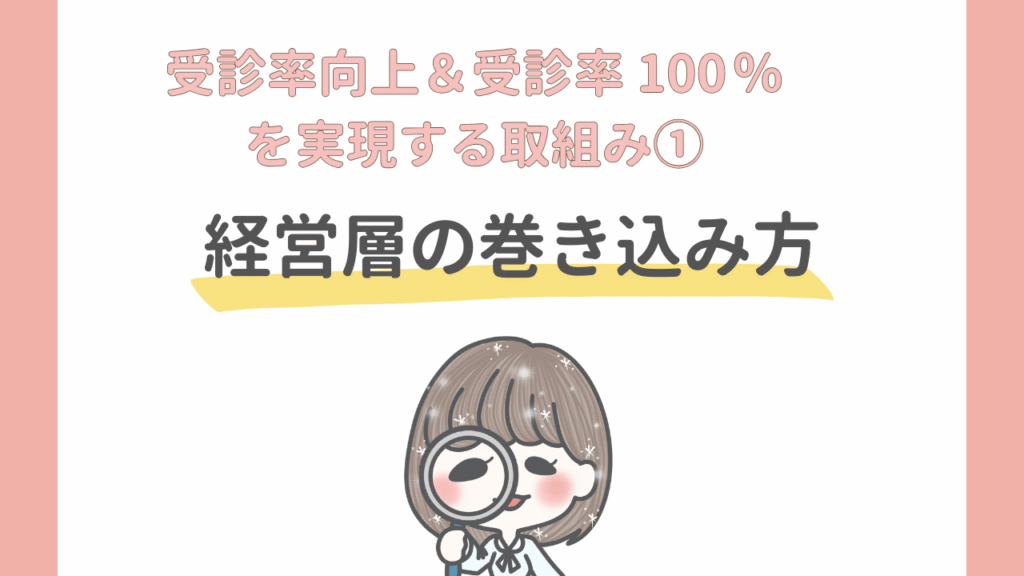
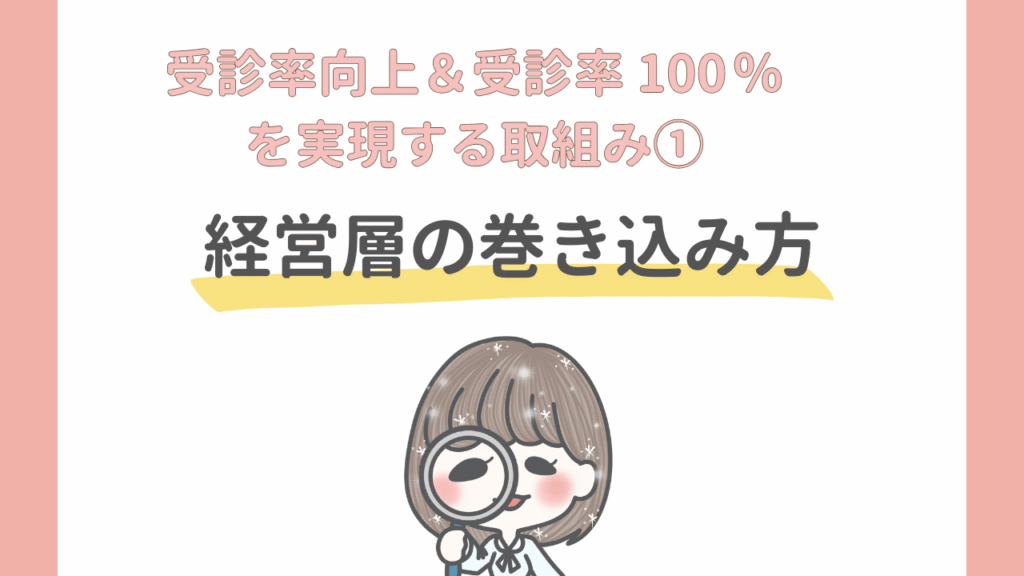
- 法令遵守、コンプライアンス違反によるデメリットを提示。
- 健康状態が確認できない社員がいることの課題を提示。
- 受診率を KPI 化し全社に宣言。
- 健康経営宣言を出し、トップダウン。
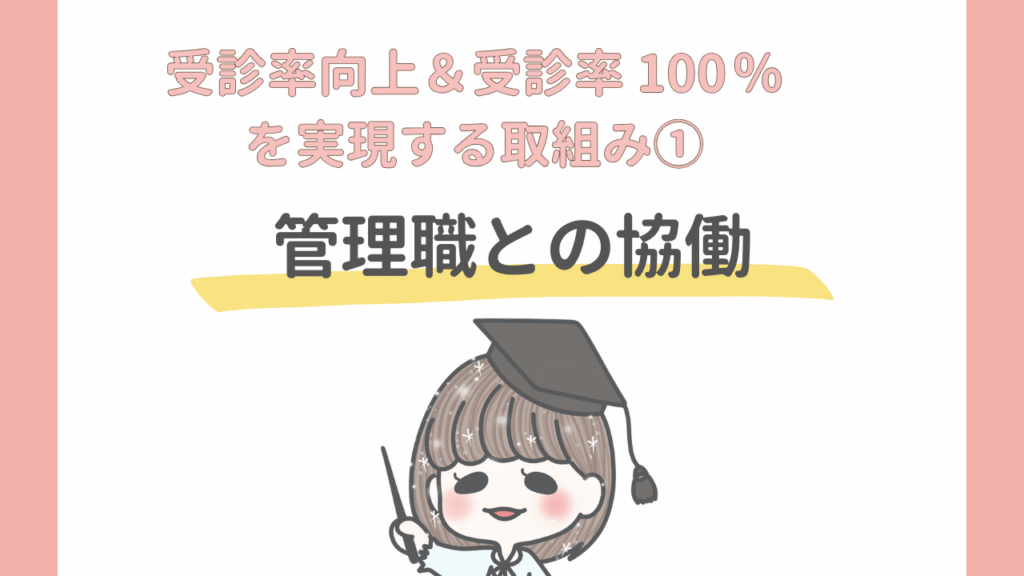
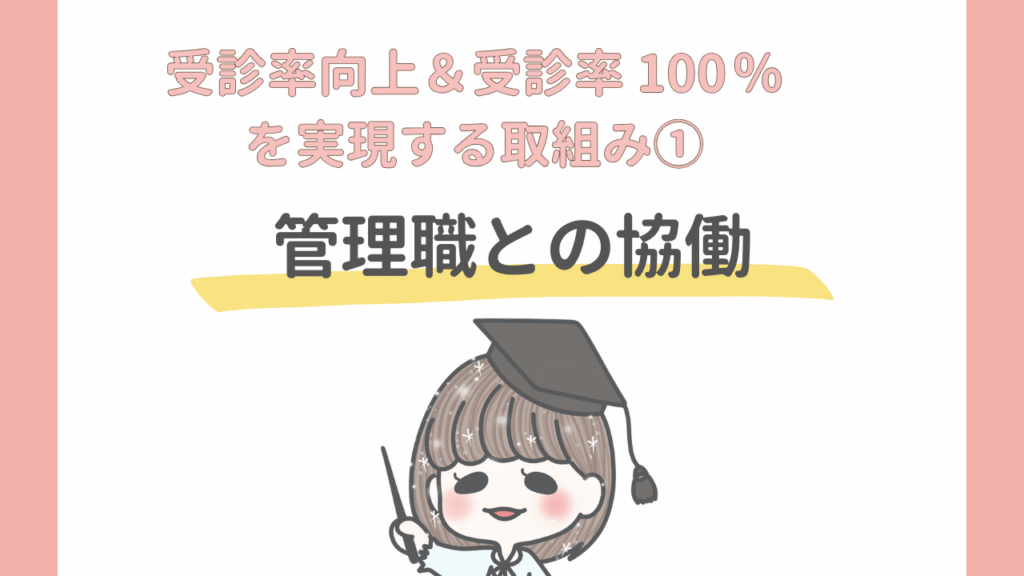
- 効率的な受診管理のため管理職やライン長との連携。
- 未受診者を隔週ごとに共有し、受診の声かけを行ってもらうよう協力を得る。
- 管理職向け研修で、受診の必要性や受診勧奨の協力をえる。
- 部門別受診率の共有と活用法。
- チーム単位での受診推進の仕掛け。
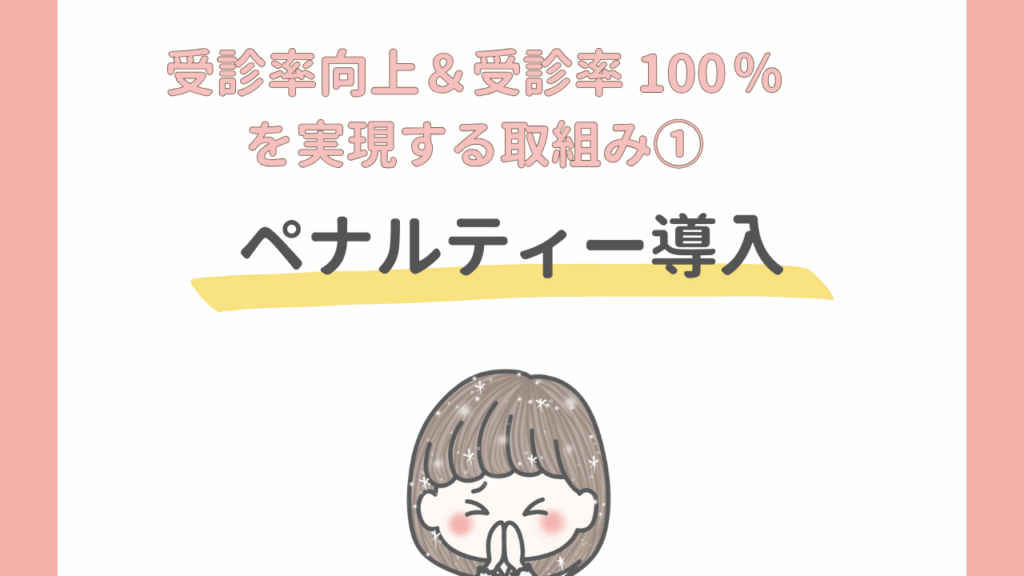
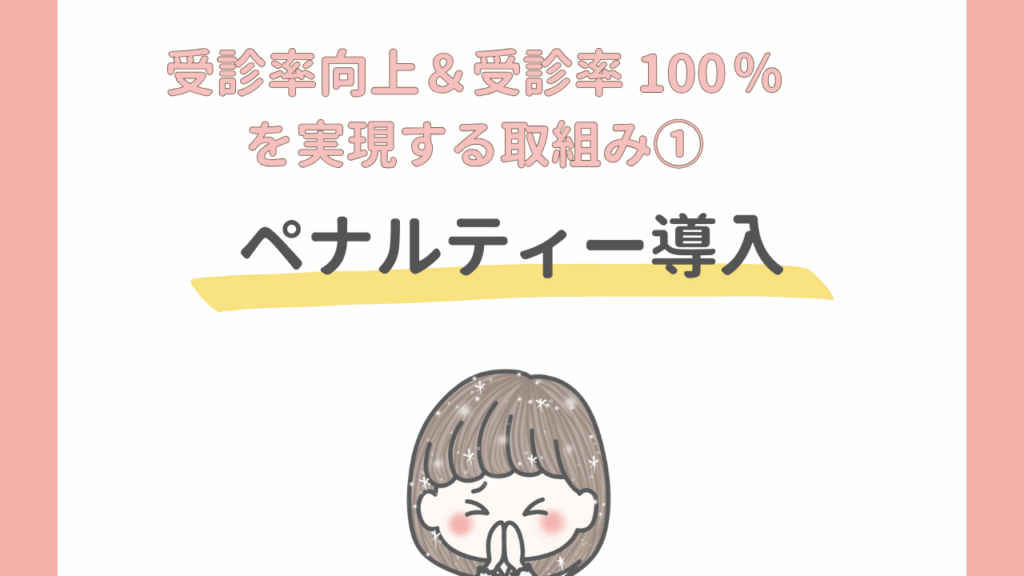
- 受診が確認できるまで会社の判断で就業措置(就業禁止、就業制限)を行う。
- 未受診者への就業上の措置(運転業務&車通勤禁止・出張禁止・1人作業禁止等)の導入。
- 健康管理規程を作成し、未受診者への対応を明記。
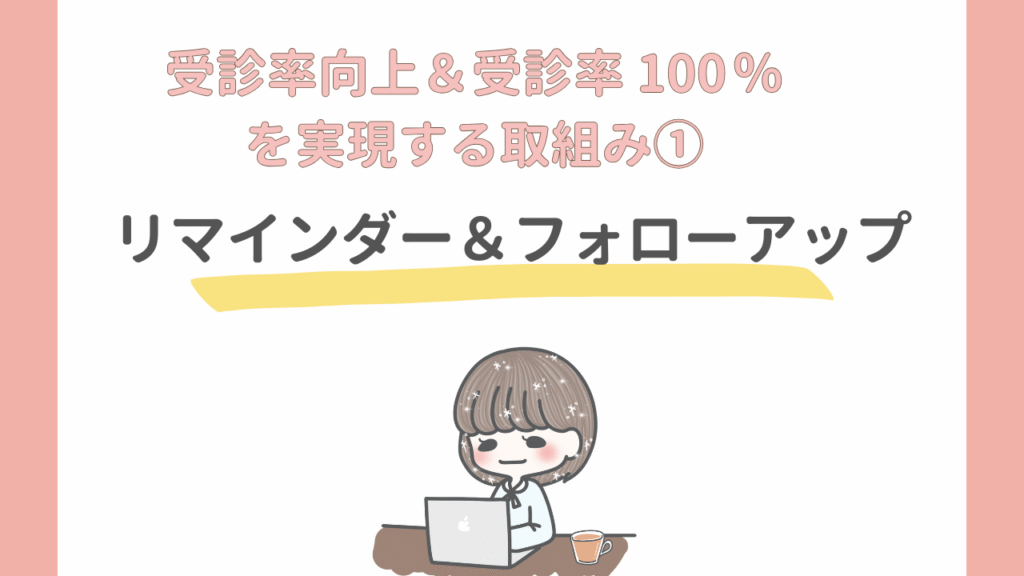
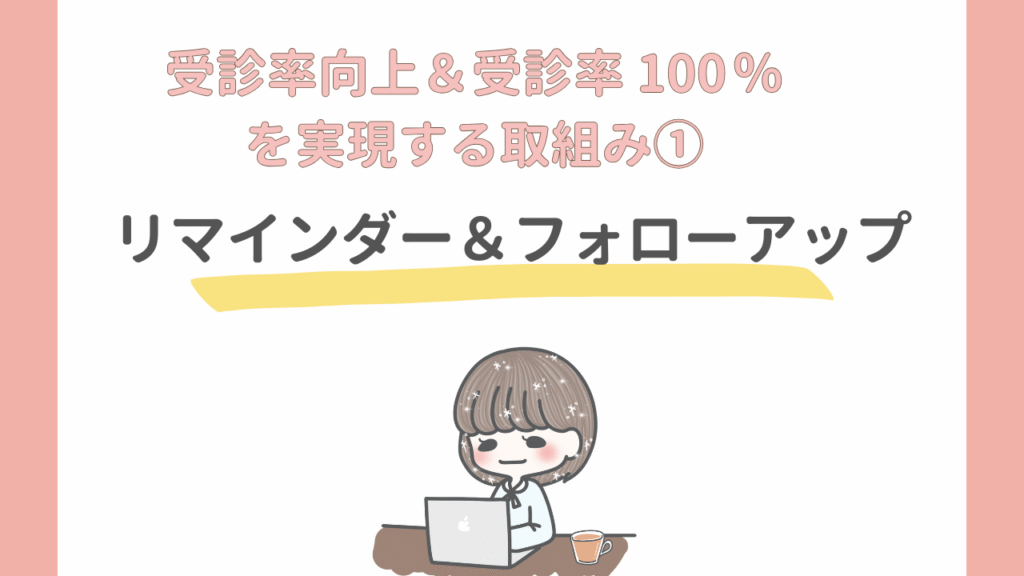
- 2~3週に1回、未受診者の上司(or個別)へ連絡+受診方法を提示
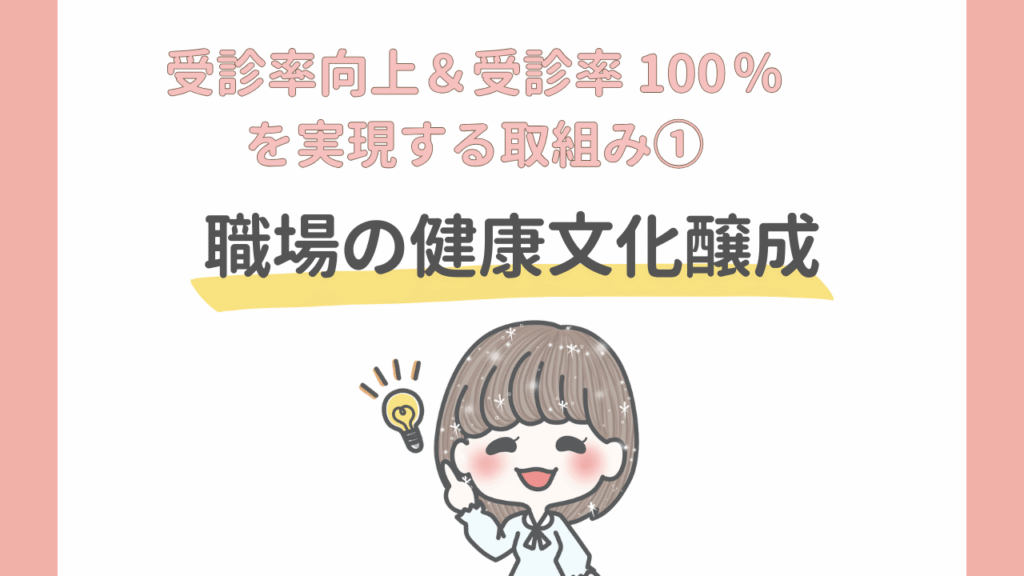
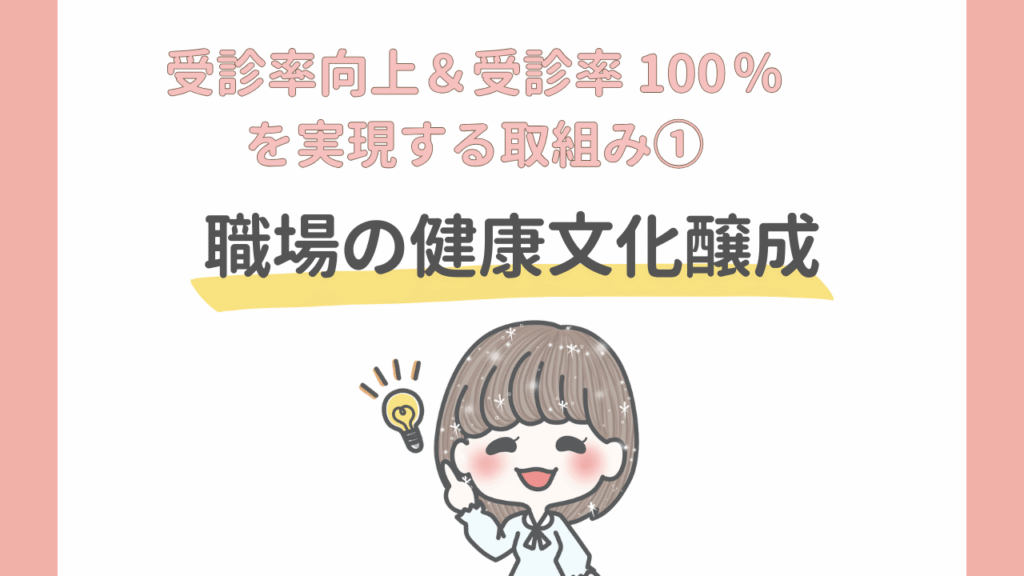
- 健診受診を当たり前とする長期的ヘルスプロモーション



私が元職場で行なった受診勧奨の仕組み化をご紹介いたします!ご参考までに!
私の元現場では、健康管理を健康管理部門で一元化し、専任の保健師1名(なのん)が全体を管理する体制にしました。隔週で未受診者リストを作成し、各部署の担当保健師へ共有 → 担当保健師から所属長へ再共有 → 所属長(上司)からご本人へ受診勧奨、という流れを標準化したところ、現場の声かけがスムーズになり、受診率の底上げになり、2年後に受診率100%の達成につながりました。
よくある質問 Q&A
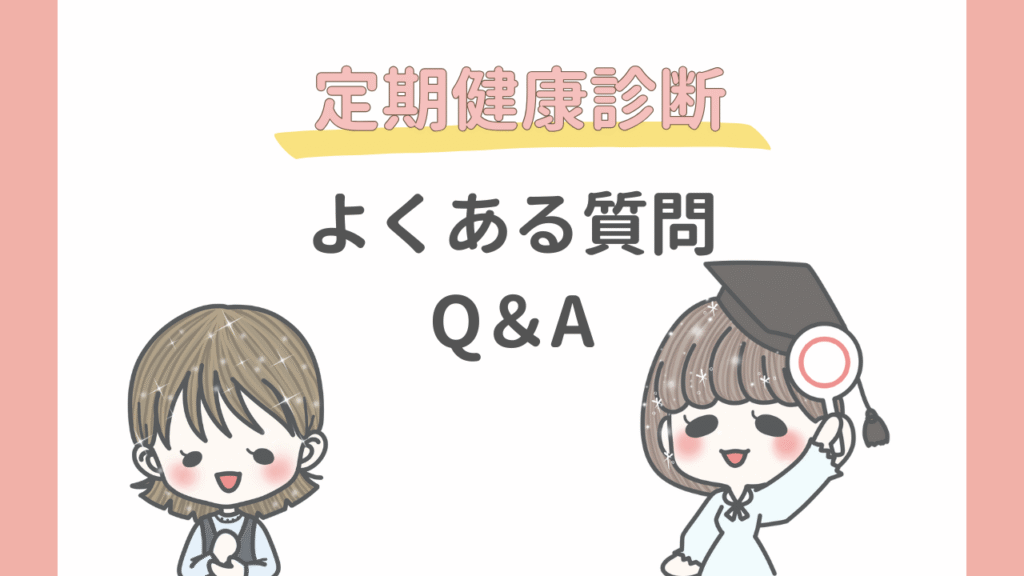
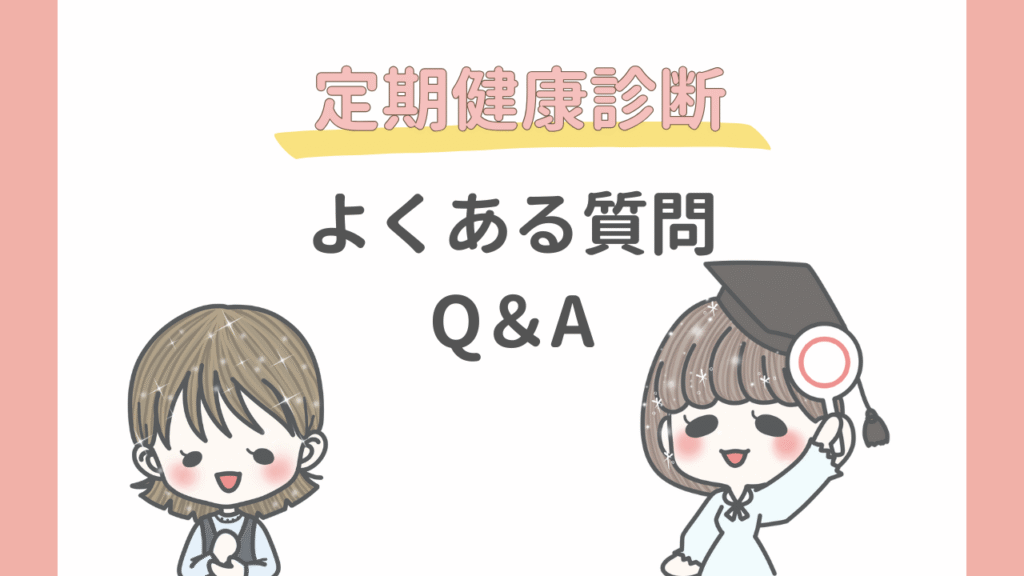
産業保健師がよく悩みがちな定期健康診断の疑問や悩みについて、なのんだったらどう考えるのかを回答いたします。
- 腹囲測定の抜け漏れがあります。どう対応するのがベター?
-
省略可能な条件に当てはまれば、省略可能ではあるが、確認作業が増えるため、原則全員実施とすることがベター。予算を確認の上、検討していくことが望ましいです。
- 7〜9月が会社の健診期間です。9〜10月入社の中途入社者は定期健診が必要?
-
雇入時健診が要件を満たしていれば、その年に“もう一度”定期健診は必須ではありません。 ただし、コンプライアンス遵守に厳しい企業では、次回は雇入時健診日から1年以内に受けさせることが望ましいです。
- 40歳以上で市役所の特定健診(特定健康診査)の結果だけ提出し、法定項目が不足しがちです…
-
法定項目が欠ける結果は“そのまま受理しない”運用が原則。 不足分は追加受診で埋めるか、会社指定機関での受診を案内するのがおすすめ。
事前対策- 事前に会社指定健診機関以外で受診した結果を提出する方は事前に申し出るよう案内
- 会社の必須項目リストを案内に明記(特定健診のみでは胸部X線等が不足しやすい)
- 「受診したくない」未受診者への対応は?
-
定期健康診断には、会社の実施義務と労働者の受診義務があります。まずはその趣旨を丁寧に説明し、理解を得てみてください。未受診時の対応は、段階的にすすめていくことが大事です。未受診の場合、健康状態の確認ができるまで、健康管理規程に基づき一時的な就業上の措置(配置・深夜業や高負荷作業の制限 など)を行うよう会社としての対応を検討していきましょう。



前職や産業保健活動がしっかり行なっている企業では、未受診者がいた場合、就業制限を会社として行なっていますので、自社の産業医にも意見聴取しながら、未受診者の取扱を決めることをおすすめします。
- 年1回6月が会社の健診期間です。4月入社で雇入時健診済みの新入社員は、その年6月の受診は不要ですか?
-
法令の原則は「1年以内ごとに1回」。雇入時健診の受診日(3月or4月)から起算して12か月以内に次回を設定できるなら、同年6月は必須ではありませんが、6月が健診期間であることを考えると、受診していただくことをお勧めします。
まとめ:定期健康診断の目的を理解し、受診率を高める取り組みを!
受診率100%は一朝一夕では達成できません。私も最初は苦労しましたが、「個人の問題」から「組織の課題」へと捉え方を変えたことで突破口が開けました。粘り強く働きかけ、味方を増やしながら健康文化を育てていきましょう。
定期健診は企業の法令遵守を推進し、企業を守る重要な取り組みです。受診率100%の達成で、次のステップへと産業保健活動を発展させましょう!
最後に ― 一緒に学び、実践しよう!
ご覧いただきありがとうございました!
産業保健師の役割や業務に悩んでいる方は、私が主宰する産業保健師育成プログラムで気づきのヒントを得られるかもしれません。
- 受講中に現場で起こっているお悩みをケーススタディとして検討
- 先輩保健師とのグループディスカッションで視野を拡大
産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!
産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。
産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。
一緒に成長していきましょう!


\ 産業保健師の実践力を鍛える/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!


- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!
- 産業保健師の転職支援の実績
- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成
- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%
- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価
- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績
- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施
- 育成プログラムを約20名へ提供
- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

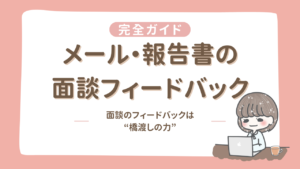
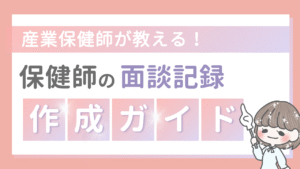
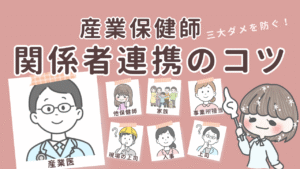
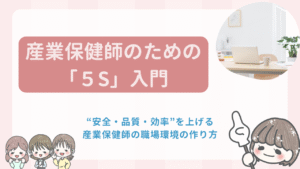
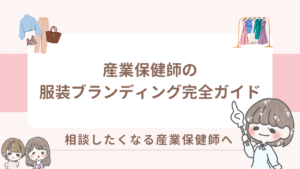

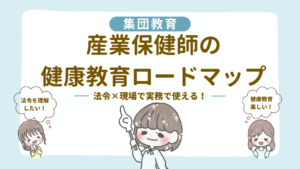
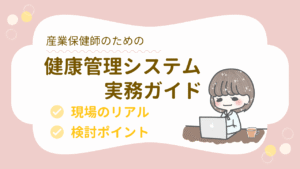
コメント