産業保健師の“三大ダメ”を防ぐ!関係者連携のコツ

こんにちは、産業保健師のなのんです!
みなさんは、産業保健活動に関わる関係者連携に対して、こんな疑問やお悩みはありませんか?
 産業保健師1年目
産業保健師1年目「困ったらとりあえず産業医面談…」どのケースを産業医に繋ぐべきか判断がつかないことがあります。



「私がなんとかしないと…」と抱え込んで疲弊してしまう。



報告・連絡・相談のタイミングがいまいちわからないです。



職場の上司からの“困りごと”に止まってしまい、打ち手が出ないことが悩みです。



どれも根っこは同じですね。産業保健師自身の中で、関係者の連携設計がない(弱い)のが原因です。
産業保健師の役割は大きく分けて「本人の自己管理支援」×「関係者支援」の掛け合わせです。
つまり、従業員本人だけでなく、上司・人事労務・産業医・社外資源といった関係者と一緒に進めて成果をつくる仕事。ここが腹落ちすると、対応の迷いがぐっと減ります。
\産業保健師の役割はこちら/


本記事では、現場で起こりがちな産業保健師の“三大ダメ”——産業医へ丸投げ/自分で丸抱え/職場の健康課題の放置(聞き流し)——を避けるための、具体的な連携の型(誰に・いつ・何を)をまとめました!産業保健活動に関わる関係者の連携設計を行なって、円滑な産業保健活動を行なっていきましょう!
- 各関係者ごとの関係者連携の基準とポイントが理解できる
- 各関係者との連携の可否を判断するためのポイントがわかる
- 「関係づくり」のコツを実践できるようになる


- 新卒から産業保健師歴約15年
- 産業保健師としての企業での活動実績
- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社
- オンライン健康セミナー 約10回/年
- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年
- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供
産業保健師の“三大ダメ”とは
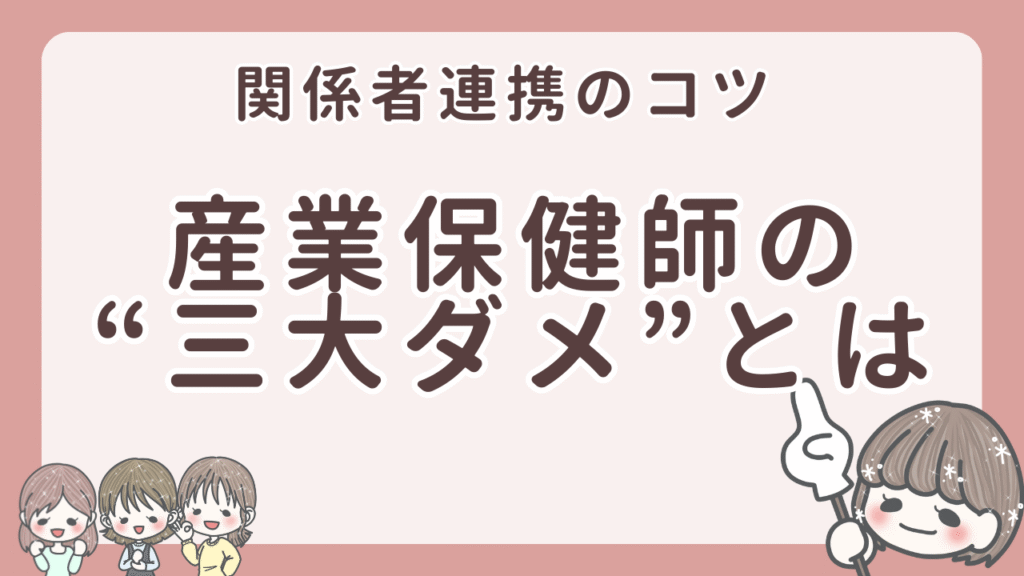
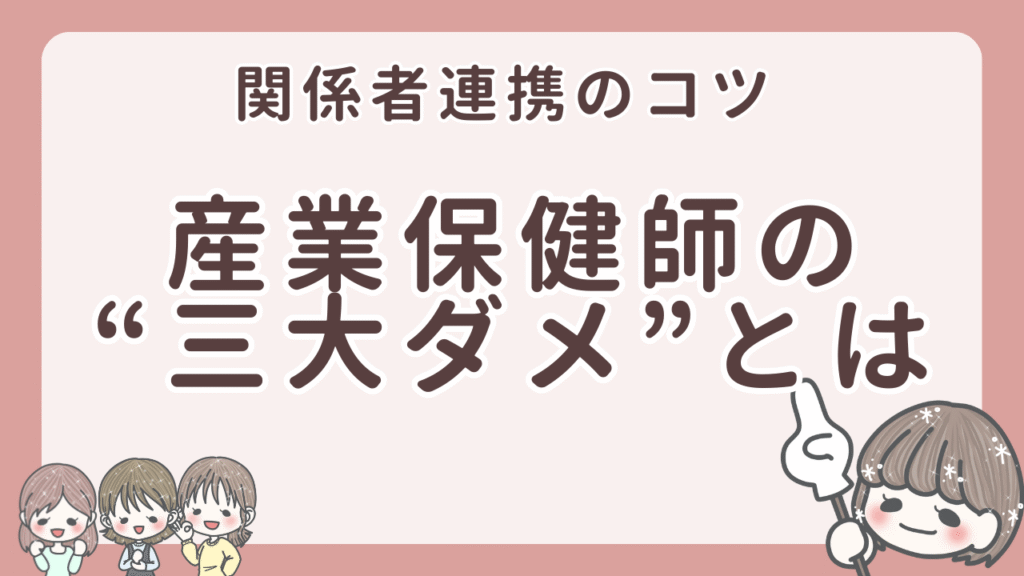
Xで「産業医の三大ダメ」という以下の投稿を見かけました。
「産業保健師版もある!」と感じ、私の現場経験をもとに“やりがちだけど成果が遠のくクセ”を整理しました。
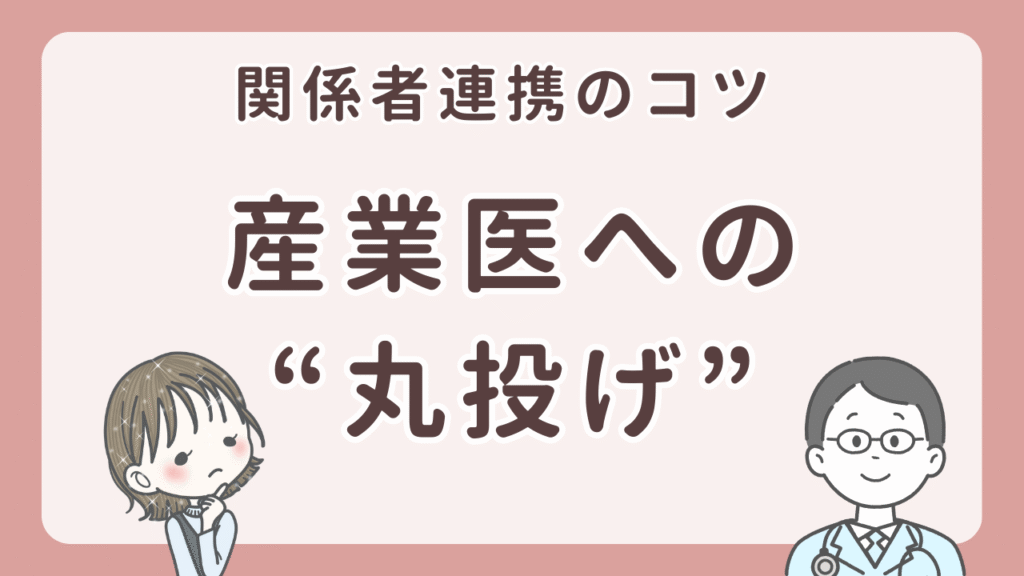
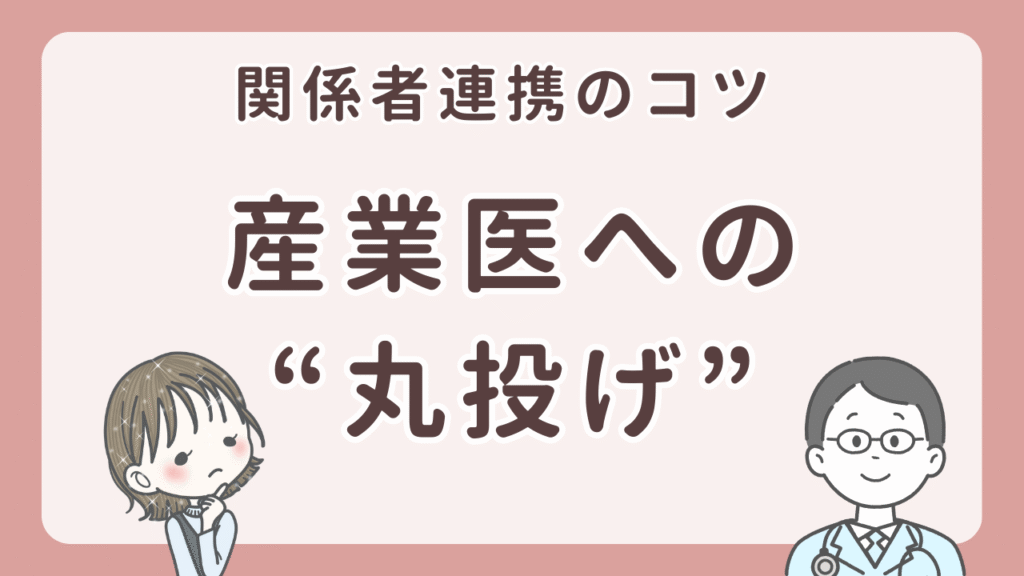
判断・調整・下準備がないまま産業医へ依頼や念の為産業医面談へつなげる。
- ありがち:判断も段取りも「とりあえず産業医に聞けばOK」「産業保健師が念の為・不安だから産業医面談へ繋げよう」で産業医業務の停滞
- リスク:産業医稼働の圧迫/現場が主体的に動かなくなる/産業医が困る
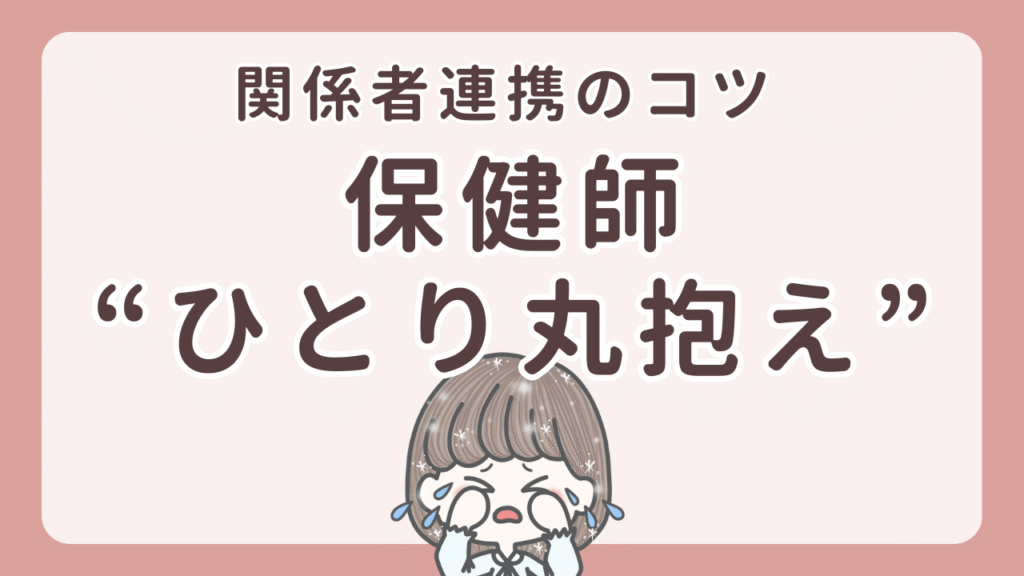
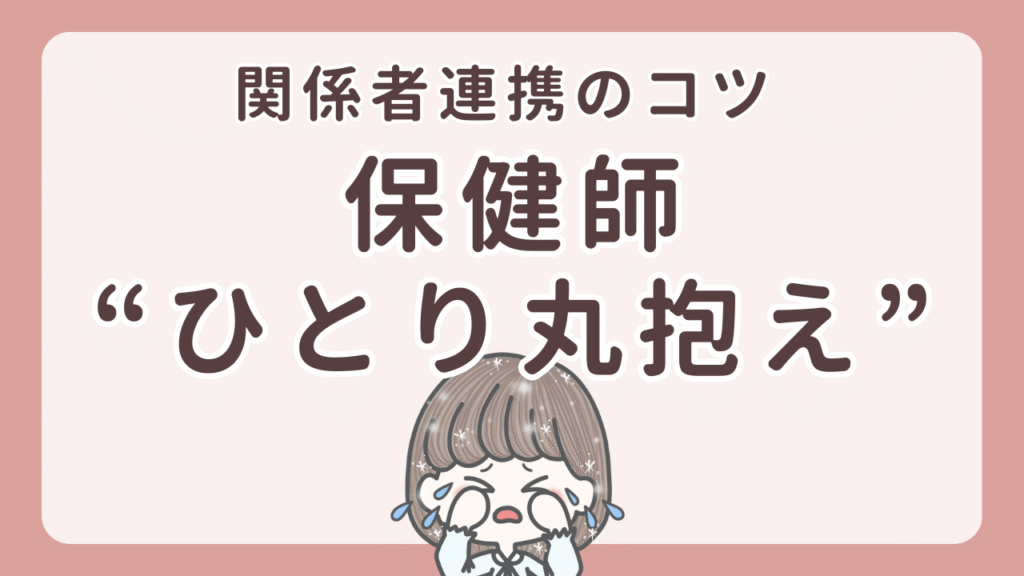
「自分がやった方が早い」「私が解決しなきゃ」という責任感から、関係者との連携が後回しになってしまう。結果として、会社・組織の視点が抜け、個別対応に偏る。
- ありがち:メンタル不調者などのケース対応、資料作成、体制構築、職場環境改善など…全部ひとりで背負う
- リスク:属人化・ミス・燃え尽き
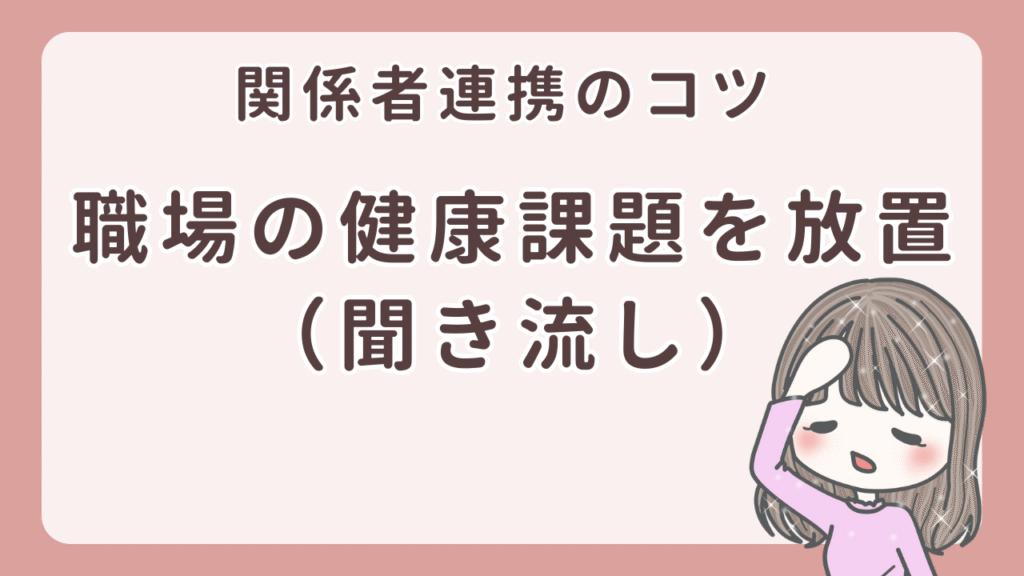
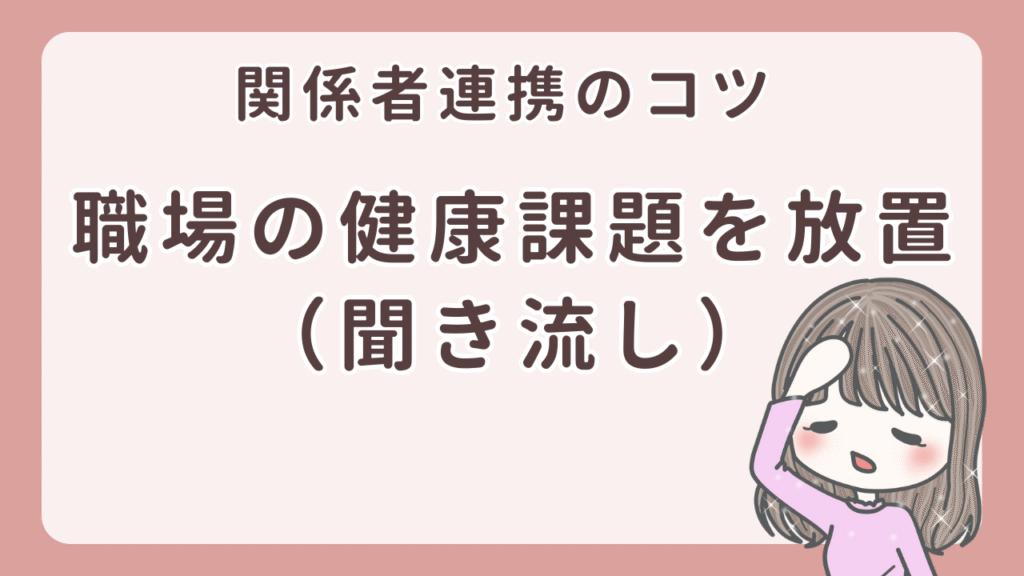
担当者や職場の上司から、本音サインや相談を受けても、事実整理・共有・対応計画・期限設定をせず、責任の所在も曖昧なまま“様子見”にする状態。
- ありがち:「受診したが良くならない」「面談も続けている」けど、改善行動が曖昧なまま“様子見”が長期化、休職の先送り、関係者への共有不足
- リスク:病状悪化・再休職・労災・チーム士気低下
インスタで関連投稿を載せています。あわせてご覧ください🌸
【産業保健師】「丸投げを防ぐ」ための関係者連携のコツ
次に各関係者別のつなぐ基準やポイントについてご紹介していきます。産業保健領域では、各社によって状況が異なるため、あくまで、参考までに、各社に応じて「つなぐ基準やポイント」を掴んでいきましょう!
関係者別の“つなぎポイント”
産業医と連携するときは、就業可否や配慮要否の判断・変更が必要な場合、人事労務より健康状態の医学的評価が求められているような場合は必要な時は、産業医意見の聴取を行うために、産業医と連携するのが原則。
すぐに産業医面談へつなげるのではなく、産業医意見を聴取した上で、必要に応じて産業医面談の設定を行うのがベター。
- 就業可否の判定:働くことができるか?を判断する
- 就業制限の可否:就業が健康状態を悪化させるリスクがあり、就業上の措置の必要性とその内容・範囲を判断する
- 就業措置の変更:就業上の措置の内容や範囲・制限の可否の変更が就業に耐えうる健康状態か判断する
- 復職面談の前に、産業医へ休職者の情報を伝え、産業医の復職面談を行う
- 事後措置で就業制限(時間外労働の制限)に該当した深夜業務従事者が、治療状況の悪化し、深夜業務を行うことで健康状態が悪化する可能性がある
- 業務上の支障が出ているが、主治医より療養が必要という診断書が出ない場合など、産業医面談を行い、要休業の可否を判断する
- 復職2ヶ月目の復帰者が、体調悪化・業務上の支障が出ており、本人が休みたくないため、関係者で話し合いが必要なケース
- 業医面談へつなげる。(→基準に沿って産業医は対応しているため、心配なら産業保健師が自己管理支援や受診勧奨すること)
- 療養が必要という診断書が出ているにも関わらず、念の為産業医面談を設定し、療養開始が遅れる(※会社の規程で、休職前に産業医面談の実施がルールとしてある場合は別です。)
- 復職2ヶ月目の復帰者が、体調悪化・業務上の支障が出ており、休ませた方が良いからと言って産業医面談へつなぐ。(→休ませるための説得を産業医へ丸投げしないこと)
人事・労務と連携するときは、基本的に人事・労務の仕事に関わる事象が起こった場合になります。
人事・労務と連携する基準は、以下になります。
- 就業措置・休復職・配置転換・勤怠など労務管理が必要
- 就業規則/規程運用に関与(短時間勤務・残業制限・深夜業制限 など)
- 安全配慮義務の観点で会社としての判断が要る
- 就業措置(配慮要否・内容・期間など就業上の措置が必要な場合)
- 勤怠/契約(工数・残業・シフト・配置など労働契約が守られていないor変更が必要な場合)
- 規程運用(手続・書式・スケジュールなど会社の規程を新規・追加修正が必要な場合)
産業保健師の上司は、人事労務の職位者(部長やグループリーダー、課長など)や産業医である場合が多いため、連携する際は、何に対しての相談なのかを必ず明確にして連携すること。
産業保健師の上司と連携する基準は、以下になります。
- 各業務の優先順位/リソース配分の判断が必要な場合(例、個別対応の案件の山積み、締切が間に合わない、業務の偏りなど)
- 品質・倫理・コンプラ判断が絡む(迷いがある/社内基準に照らした確認など)
- 対外折衝・組織決定が必要(他部署からの研修依頼、部署横断の施策や経営合意が必要な提案の場合など)
- リスク顕在化(産業保健スタッフ内でのヒヤリハット、労災時の救急対応・再休職・ハラスメント疑い等)
- 優先度(今、何を先にやるか)
- リスクと責任(どこがボトルネックか/責任の所在はどこか)
- 意思決定(承認・エスカレーション・期限)
職場の上司(管理監督者)と連携が必要な場合は、業務管理や仕事に関する相談が必要な場合が基本。
職場の上司(管理監督者)と連携する基準は、以下になります。
- 業務品質・安全リスクの兆候:ミス増、ヒヤリハット、事故リスクの高まり
- 勤怠や働き方の変化:遅刻・欠勤・早退の増加、残業/深夜業が続く
- 就業配慮の“実装”が必要:シフト調整、タスク再配置、出張/夜勤回避など上司決定が要る
- 人間関係/ハラスメントのシグナル:チーム内トラブルで業務影響が出ている
- 配慮実施後の再評価:1ヶ月・3ヶ月のフォローで“効果/継続/切替”を判断したい時
- 事実と影響の把握:本人が面談で話している内容や職場で起こっている問題の客観的なすり合わせ
- 当面ゴール:当面の職場の配慮内容や期限など現場と本人のゴールをすり合わせ
- 役割分担:本人・上司・人事・産業保健スタッフのやること/期限を明確化
主治医と連携する際は、診断・治療における主治医意見を得たい場合が基本となります。
主治医と連携する基準は、以下になります。
- 治療と就業の両立に向けて、業務適応性や配慮の妥当性を確認したい
- 就業可否や就業制限の医学的見解が必要(産業医が主治医所見を参照)
- 治療計画の見込み(通院頻度・副作用期間など)を把握したい“効果/継続/切替”を判断したい時
- 業務適応性(どの業務が適/不適)
- 両立配慮(勤務時間・夜勤・出張・負荷)
- 見通し(目安期間・再評価タイミング)
生活支援・見守りなど家族のサポートが必要な際に連携するのが基本となります。
主治医と連携する基準は、以下になります。
- 就業において家族サポートが必要な場合(服薬・通院・生活リズム支援)
- 危機介入が必要(自傷他害リスク、急性増悪の兆候、救急対応)
- 療養環境の整備(家事サポート・通院補助・生活リズムの調整など)
- 生活支援(睡眠・服薬・通院同行・家事サポート)
- 危機対応(連絡先・早期受診・救急対応)
- 職場との距離感(業務情報は共有しない)
産業保健活動の各業務管理や引継ぎ・代行対応が必要な際に連携するのが多い傾向があります。ケースの事例検討会やスキルアップの勉強会などを開き、判断難易度の高いケースの助言が必要な際も有効です。
他産業保健師と連携する基準は、以下になります。
- 拠点/案件が複数で、代行・引継ぎが発生する
- 他産業保健師(先輩や同僚など)の助言が欲しい
- 品質担保/標準化(テンプレ整備、二重チェック)が必要
- 休復職・高リスクなど判断難易度が高いケースの勉強会や事例検討会
- 不在時の即応体制(当番/オンコール)を回す時
- 標準化:共通テンプレ/命名規則/保管場所(版管理)など業務遂行に必要な確認
- 分担:一次対応(R)/最終責任(A)/助言(C)/共有(I)などの把握
- 代行・引継ぎ・助言:産業保健活動を円滑化
事業所訪問の目的が達成できるように連携するのが基本となります。(事業所訪問時の担当者とは、他事業所へ保健師面談や健康セミナーの実施の際に連携する現場の窓口担当者や現場の衛生管理者・安全担当者・現地の人事総務担当者などを指します)
事業所訪問時の担当者と連携する基準は、以下になります。
- 職場巡視・現地面談者や面談場所調整・安全衛生委員会の実施時
- 設備/工程変更・災害/ヒヤリハット発生後の確認時
- 現地教育・健康イベントの開催時
- 立入/撮影/持込に許可が必要な時
【産業保健師】「抱え込まない」ための3視点で状況を切り、連携可否の判断
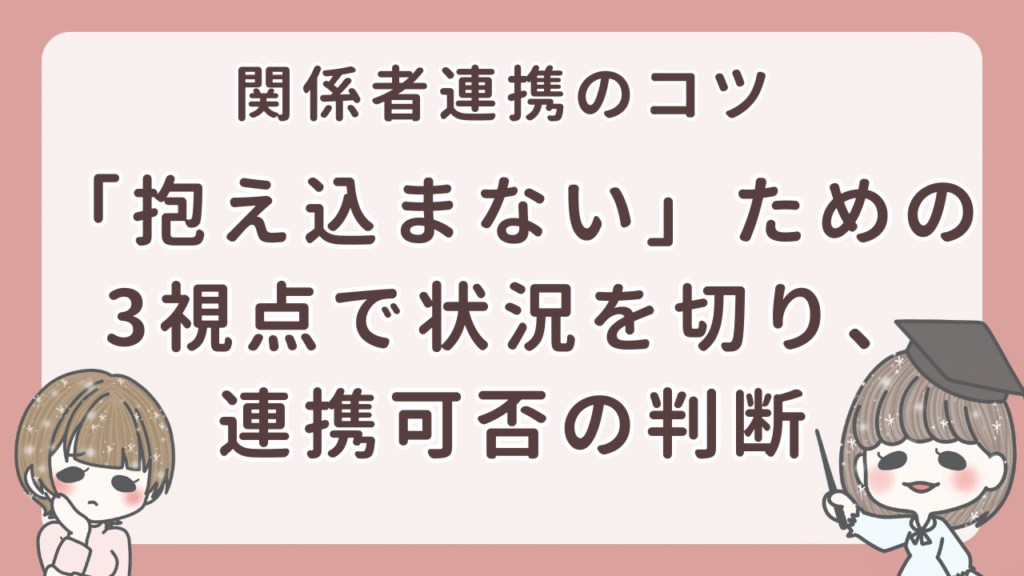
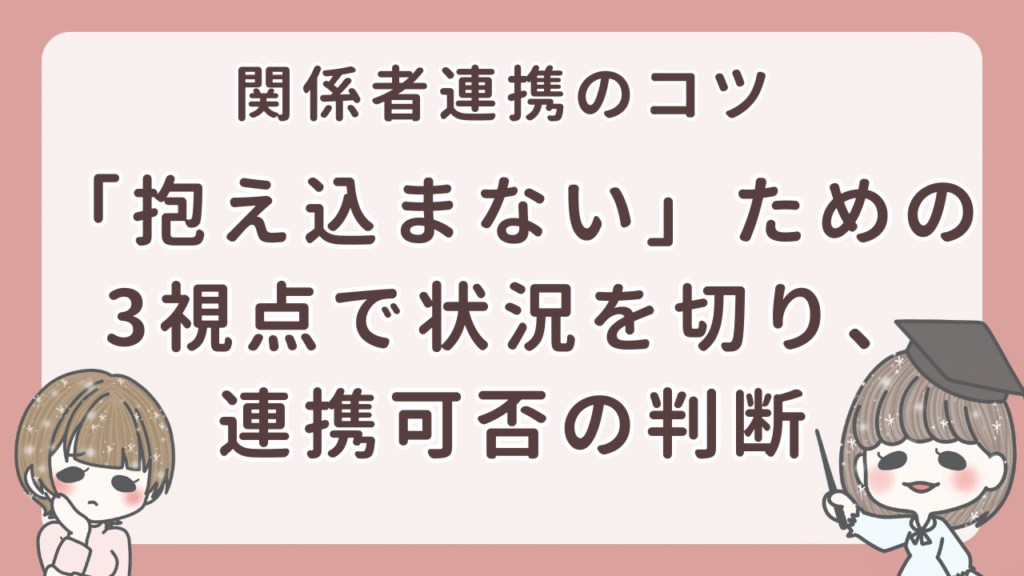
“私が何とかしなきゃ”で抱え込むと、属人化・遅延・燃え尽きが起こりがち。ここでは3視点フレームワークと同意→共有→役割分担の基本フローを、現場で回せる形に落とし込むポイントを解説していきます!
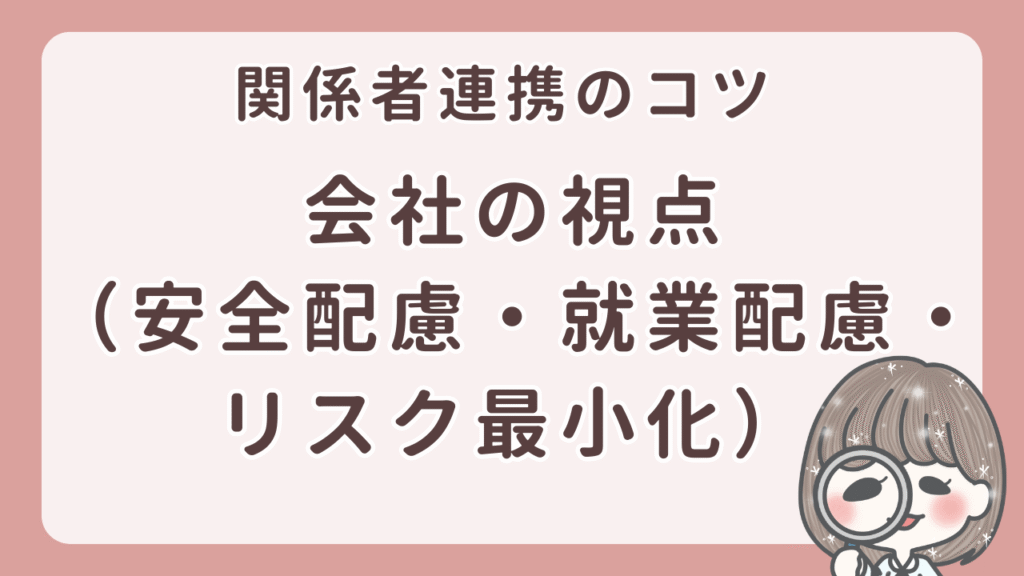
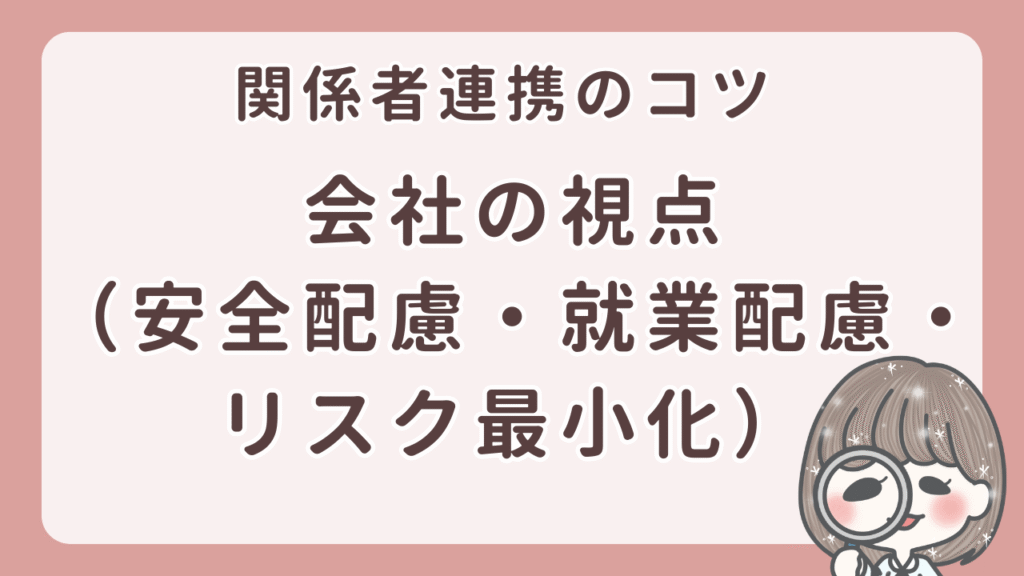
- 目的:会社としての義務とリスクを最小化し、働ける環境を整える
- 観点:就業可否・就業配慮の要否/労災・情報漏えい・職場安全
- 連携の例
- 健診未受診者への対応を人事労務・産業保健師の上司と連携し、未受診者対応の体制を構築した。
- 工場内の労災防止のために、安全体力機能テストのイベントを企画し、運動機能低下による労災予防をするため、産業保健師の上司と職場の上司(管理監督者)と連携した
- 職場で労災が起こったため、救急対応を行った。救急対応の内容を産業保健師の上司、産業医、工場長、職場の上司(管理監督者)と連携した
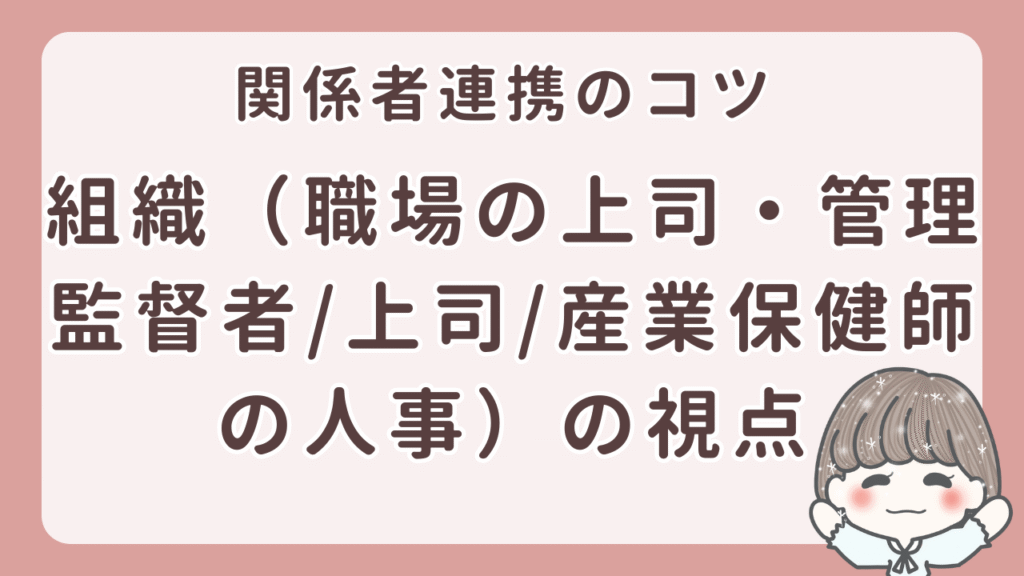
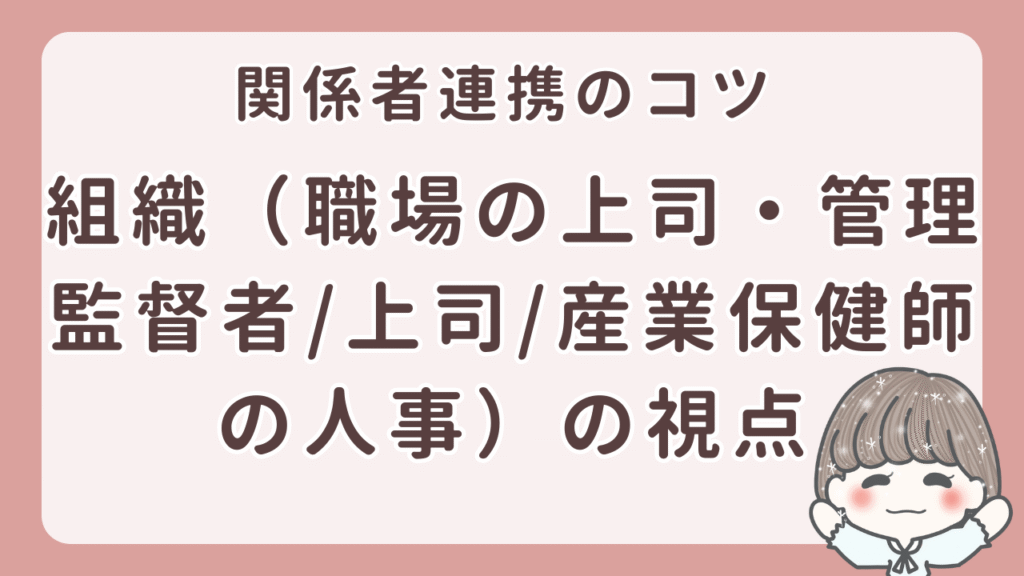
- 目的:配慮を“実装”できる段取りを組む
- 観点:職場での業務調整/勤怠・シフト管理/報連相ラインと頻度/産業保健スタッフ間のタスク調整
- 連携の例
- メンタル不調者で就業配慮が必要な場合に、人事労務と職場の上司(管理監督者)と連携した
- 職場の上司(管理監督者)が、業務上の支障のある従業員に対して、面談を行い、健康面の理由と聴取できたため、産業保健師及び人事労務へ共有した
- 産業保健スタッフ内の繁忙期に偏りがあったため、上司へ相談した
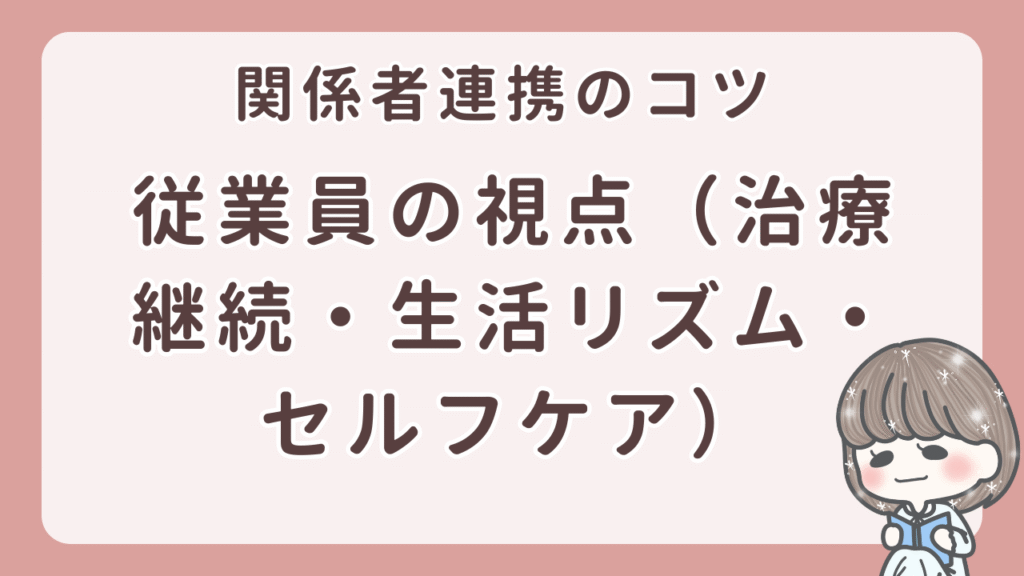
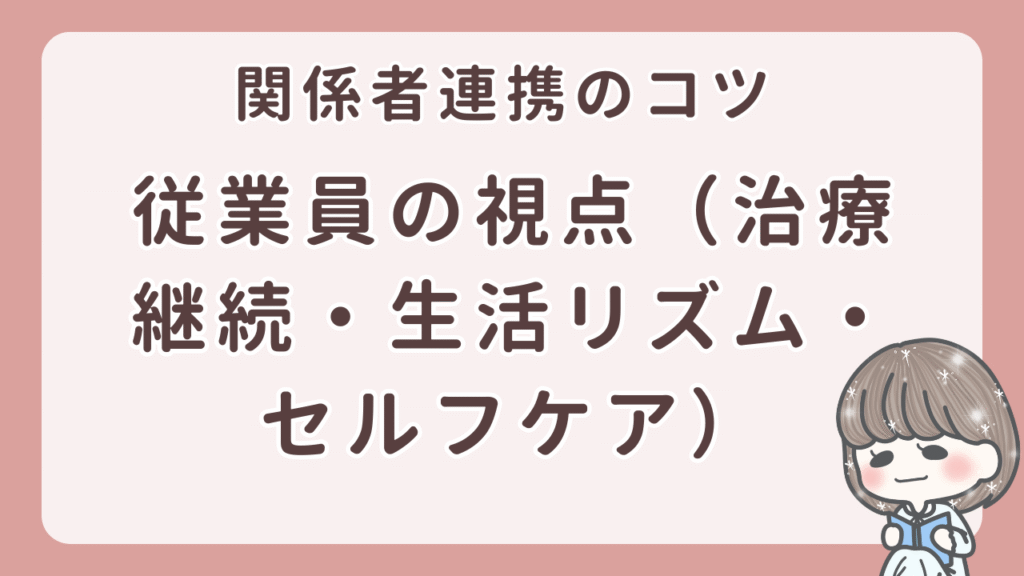
- 目的:本人の行動変容を支援して改善の土台をつくる
- 観点:通院・服薬遵守/睡眠・運動・飲酒/SOSの早期申告
- 連携の例
- めまい・ふらつきがあり、健康管理室へ来室した高血圧治療中の従業員。血圧測定したところ、血圧が190/120であったため、ご本人へ「職場の上司(管理監督者)へ伝え、帰宅する」ように助言
- アルコール依存症の従業員に、出勤時にお酒臭い場合は、帰宅してもらうことを約束し、職場の上司(管理監督者)へも連携後、お酒の臭いがした場合は、上司から帰宅するように伝えてもらうよう連携した
【産業保健師】「放置を防ぐ」ための報連相の型と連携設計
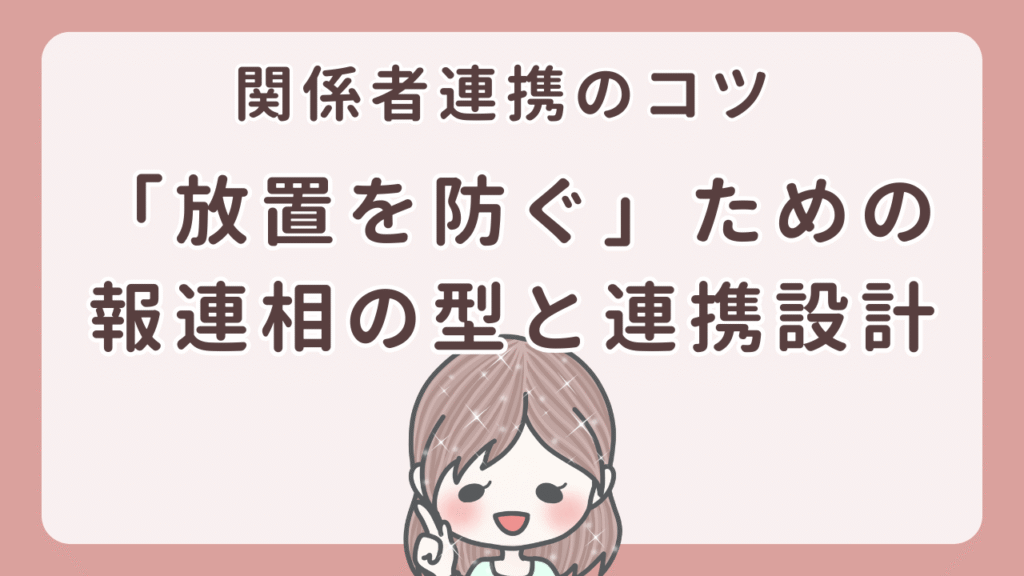
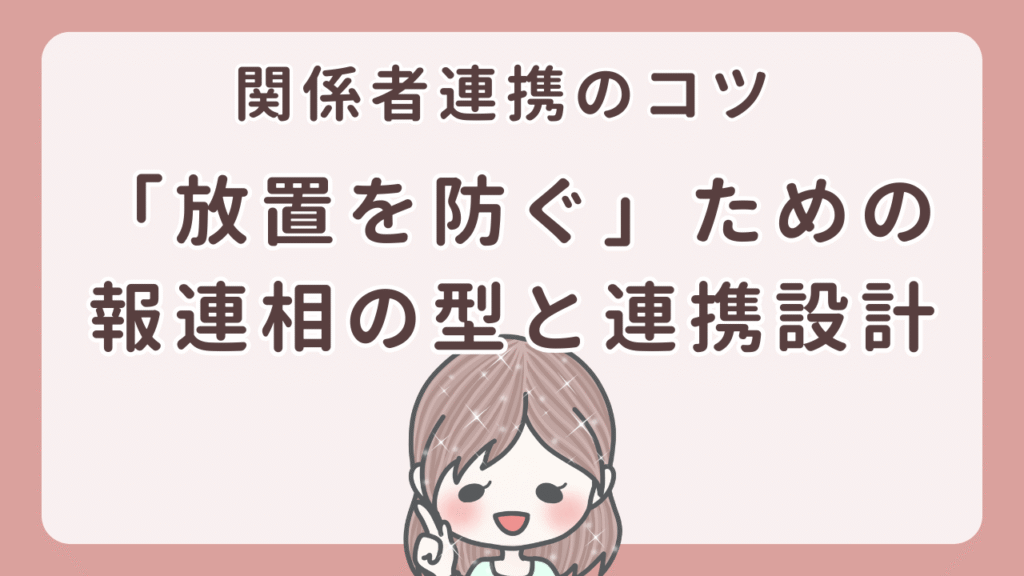
“様子見で…”、“ぽろっとでた職場の本音の困りごとを聞き流す…”が長引くと、悪化・再休職・信頼損失へ一直線。ここでは放置や聞き流しを起こさないためのトリガー運用/共有ルール(SLA)/役割分担の明文化などの報連相の型と連携設計のコツをご紹介します。
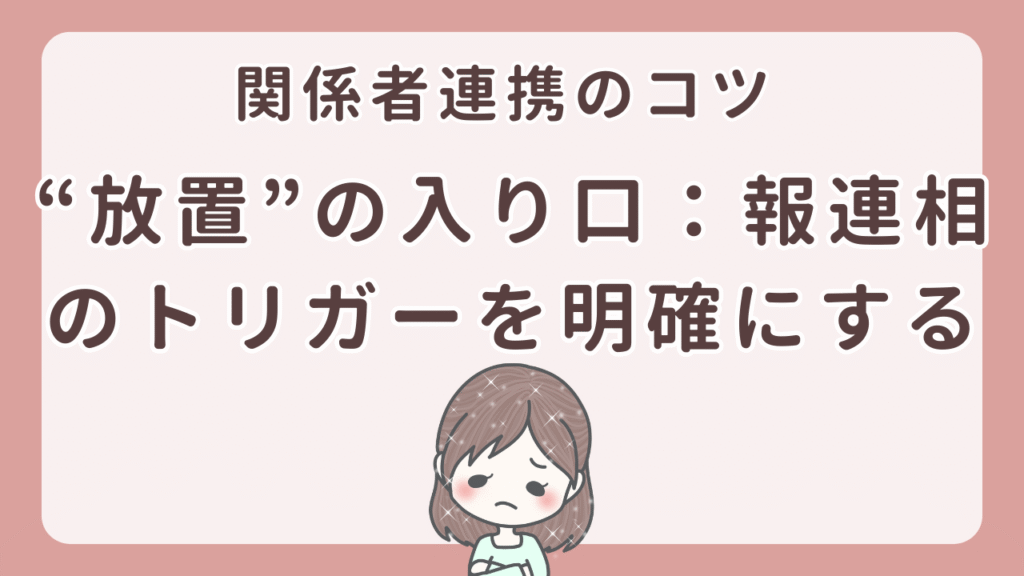
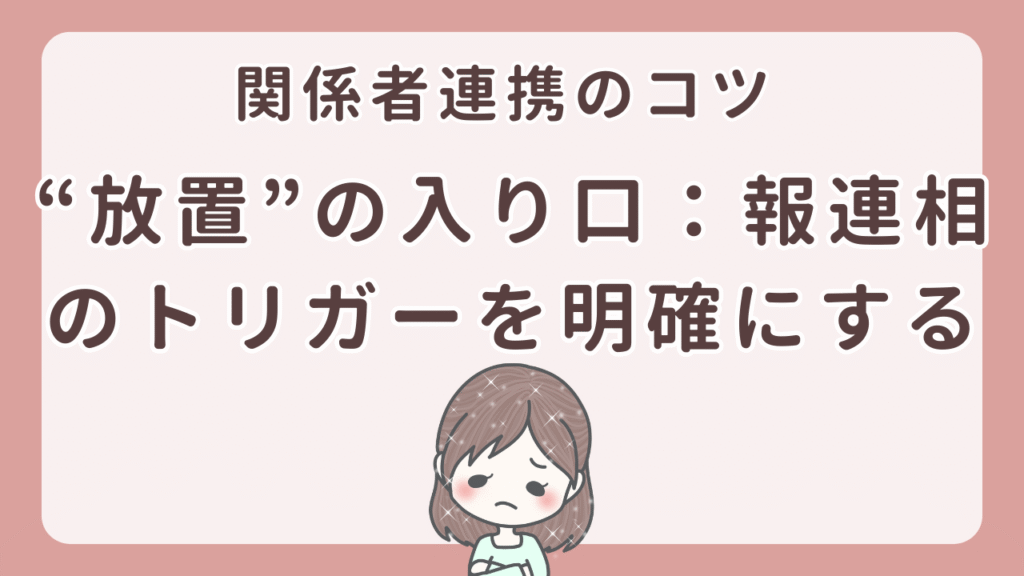
先ほど紹介した「3視点で状況を切り、連携の可否を判断(会社/組織/従業員)」で連携の可否を判断するが、迷う場合は、以下のトリガーが発生した場合は、48時間以内に要点共有を行うこと。
- 通常勤務に支障がある場合
- 通常勤務に支障がある場合とは、安全の低下、勤怠の乱れ、パフォーマンスの低下、他者からの指摘や人間関係のトラブル、言動様子がいつもとおかしいなどがある場合を言います。
- 産業保健活動の遂行が危うい場合
- 会社の安全配慮義務違反や損害賠償責任につながる可能性が高い場合
通常勤務に支障がある場合の考え方はこちら👇を参考にされてください。
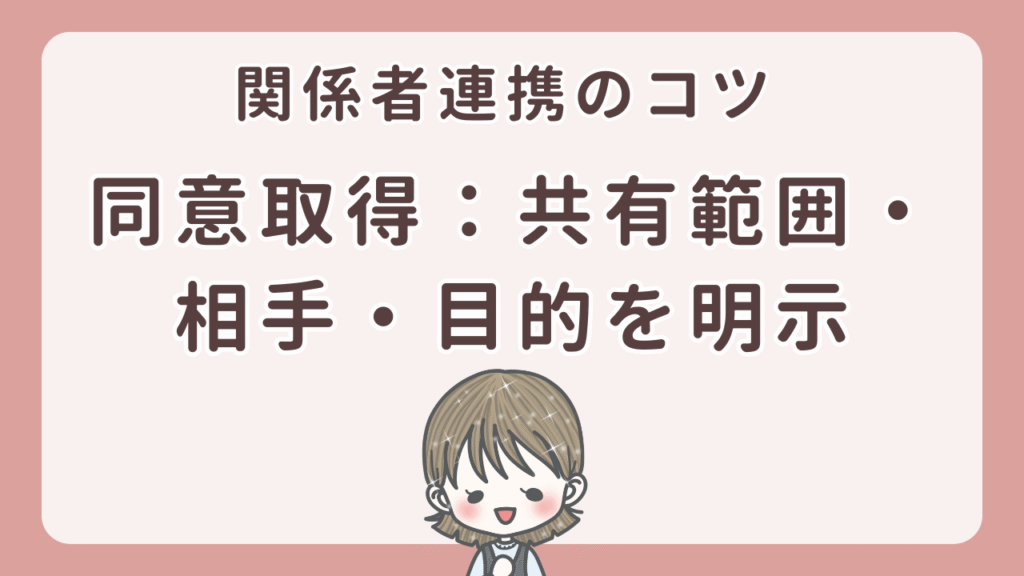
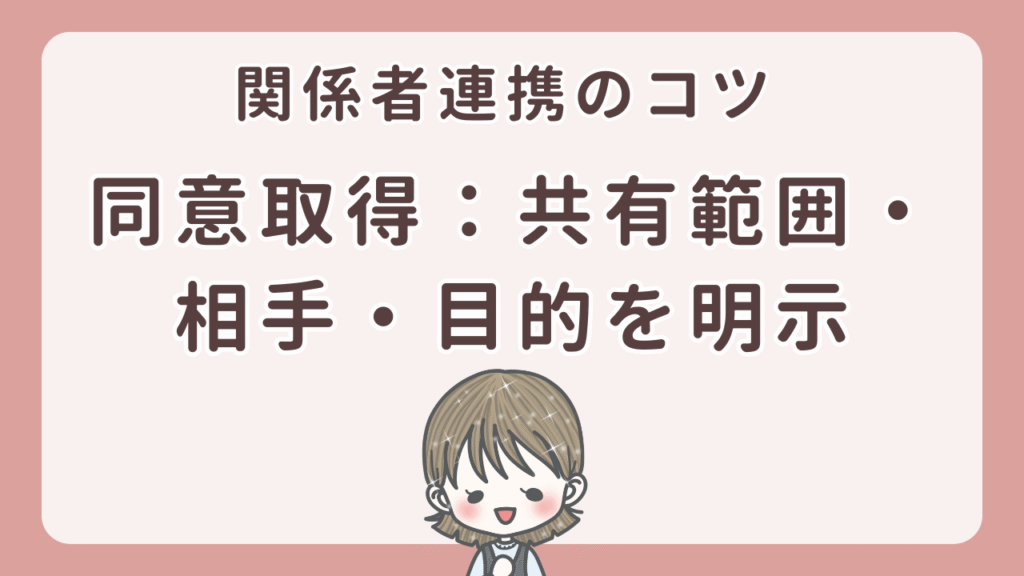
目的:連携・調整や就業上の配慮のための基本的に最小限共有に限定
- 目的限定:連携・調整や就業上/安全配慮の検討のために必要な最小限に限定
- 範囲明示:何を(共有項目)/誰に(相手)/どこまでを事前に説明
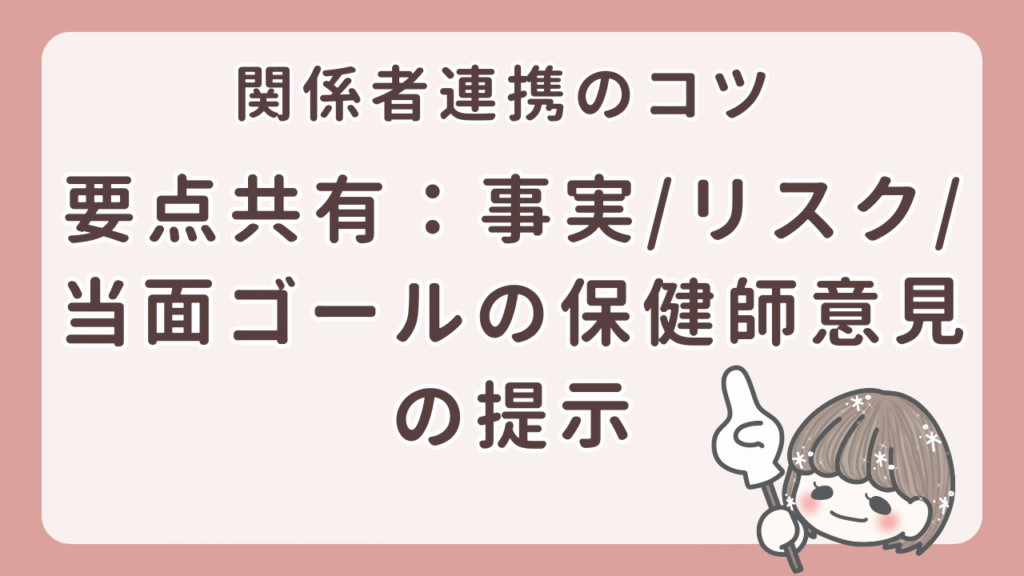
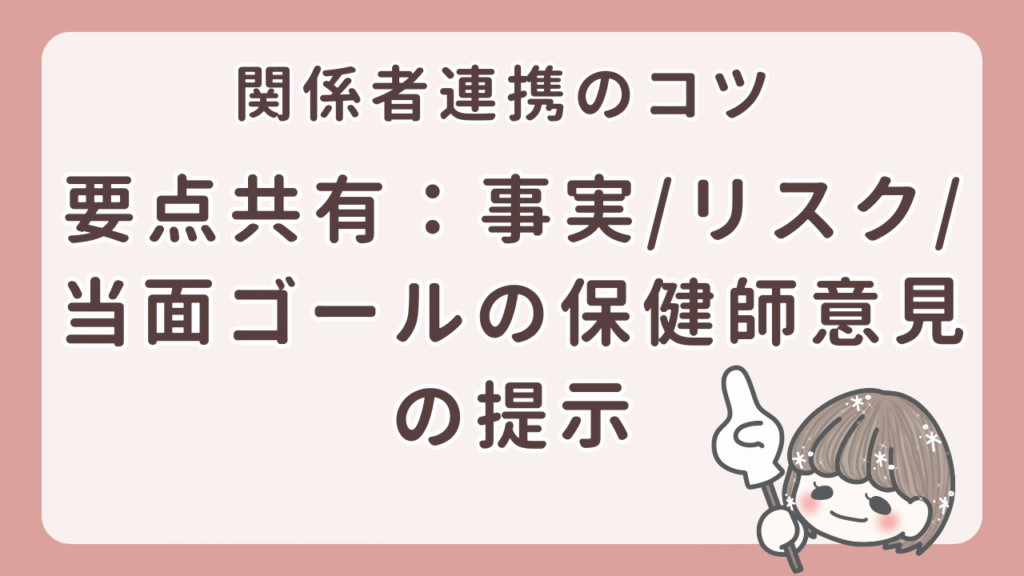
- 基本的には、48時間以内に共有
- 面談で取得した事実やそれに基づくリスク(会社/組織/本人におけるリスク)、産業保健師の意見を添えた上で、共有し、関係者でゴールを決定


- R(実施)/A(最終責任・決定)/C(相談・連携)/I(情報共有)
- RACIの雛形例は以下になります。
| タスク | 従業員 | 管理監督者 | 人事 | 保健師 | 産業医 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事後措置(就業制限対象者) | C(該当者通知) | A(就業制限決定通知) | R(面談) | C/I(意見聴取) | |
| 健康相談 | R(セルフケア) | R(面談) |
関係者連携の最重要ポイントは「関係づくり」
産業保健領域は短期で成果が出るものではなく、5〜10年で土台を育てる仕事。短距離走ではなく駅伝です。そのため、長期目線での、関係者と“本音で話せる”関係を育てることが、結局いちばん効きます。その具体的な作り方を、すぐに現場で使える形でまとめました。
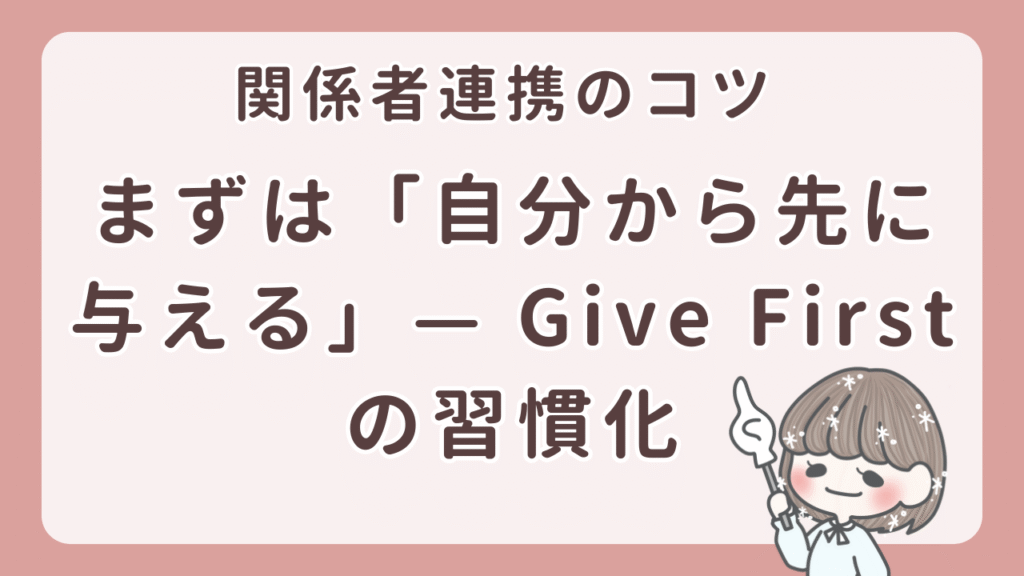
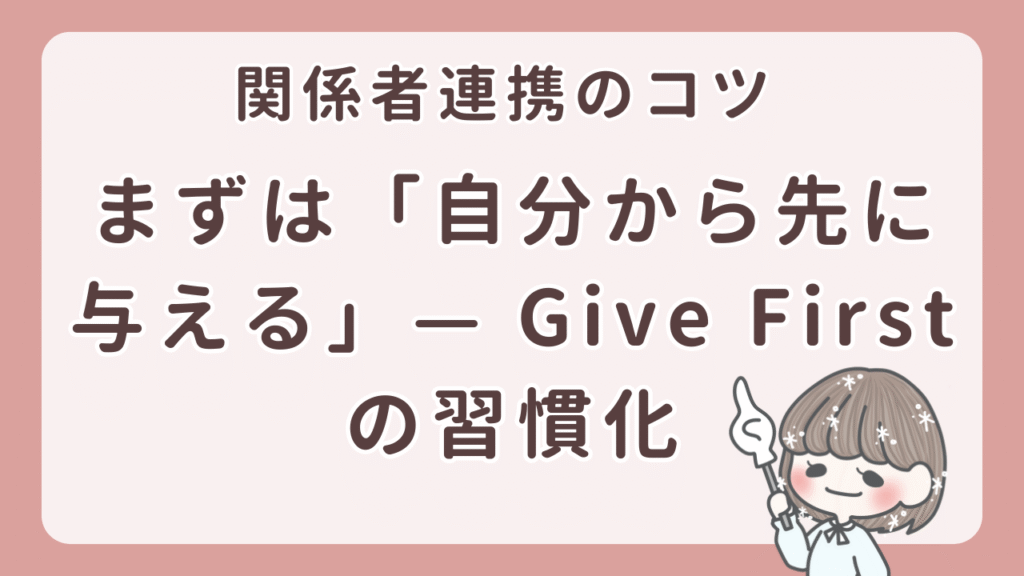
まずは、自分ができる範囲で先出し、相手から好感を得ることが大事です。小さく・素早く・一貫して先出しすると、信頼の初速がつきます。
- 笑顔+名前で挨拶(相手の名前→自分の名前→一言ねぎらい)
- その場で答えられない質問は“48h以内に回答”を約束→実行
- 上司の“事務負荷”を1つ軽くする(議事メモの雛形、チェックリスト化)
- メールの結びに短い労い:「お忙しいなかご確認ありがとうございます。助かります。」
- 即時の“ありがとう”(チャットで15秒以内のリアクションでも可)
\各関係者から「協力を引き出す」コツをチェック/




各関係者に応じて、定例MTGや臨時MTGを行い、各関係者に必要な情報を共有&提供する。月次、週次、四半期など開催リズムを事前に決めておくのがベスト。
- プロジェクトMTG:各プロジェクトの担当保健師や関係者の打ち合わせ
- 保健師MTG:保健師間の打ち合わせや共有
- 医療職MTG:産業医・産業保健師での会議
- 健康支援部門MTG :産業保健師の上司、産業保健師(必要に応じて産業医や健康経営推進担当者など)が集まり、全体の進捗管理や企画提案などをする会議
- 関係者会議や復職判定会議:メンタル不調者などの体調不良者に対して、人事・職場の上司(管理監督者)・産業医・保健師・本人などで集まり、対応の方向性を検討する会議
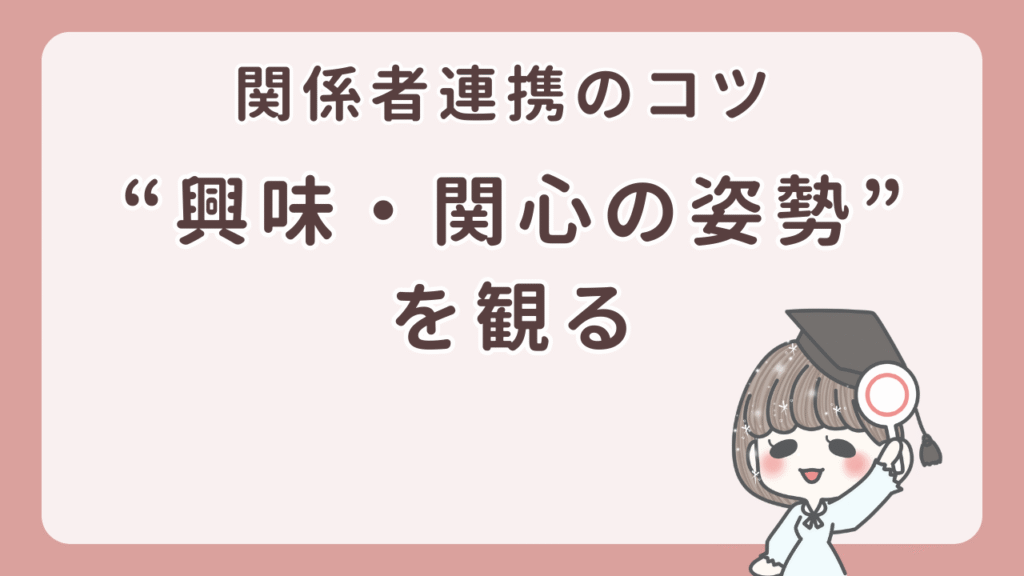
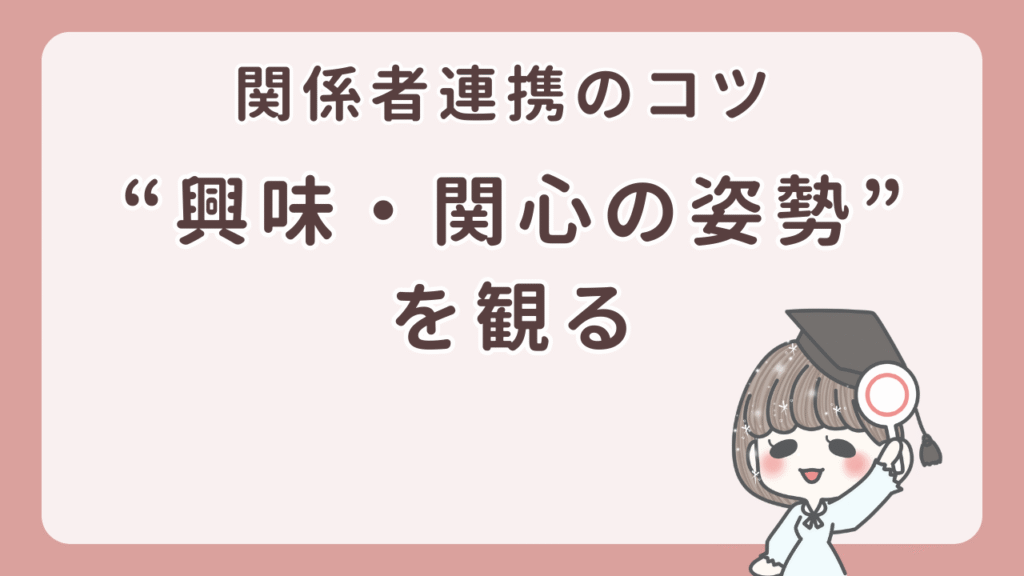
関係者の“興味・関心の姿勢”を正しく読み、合う伝え方で関与を引き上げていることで関係者連携がうまく回ります。産業保健へ力の入れ具合や健康支援に関する考えなどを把握していきましょう。
- 意思決定の速度と質が変わる(ゴール・期限・担当が早く決まる)
- 刺さる提案ができる(相手の価値基準に合わせられる)
- 長期の協力関係を育てやすい(5〜10年の“駅伝”に効く)
興味関心の姿勢3タイプ
| タイプ | 行動シグナル | 刺さる価値 | 合う伝え方(例) | 次の一手 |
|---|---|---|---|---|
| 推進型(高関与) | 即レス・結論重視・期限を切る | 速さ・結果・再現性 | 「結論→期限→役割の3行」 | 2週間で結果KPIを提示 |
| 様子見型(中関与) | 様子見・前例確認・慎重 | リスク低減・根拠・手順 | 「事実→リスク→対案→影響の1枚」 | 小さく試す“検証2週間” |
| 受け身型(低関与) | 反応薄・議題逸脱・先送り | 負担最小・現場実装の容易さ | 「今日からできる1つ+所要10分」 | 成功スナップを共有し関与を上げる |
Q&A よくある質問
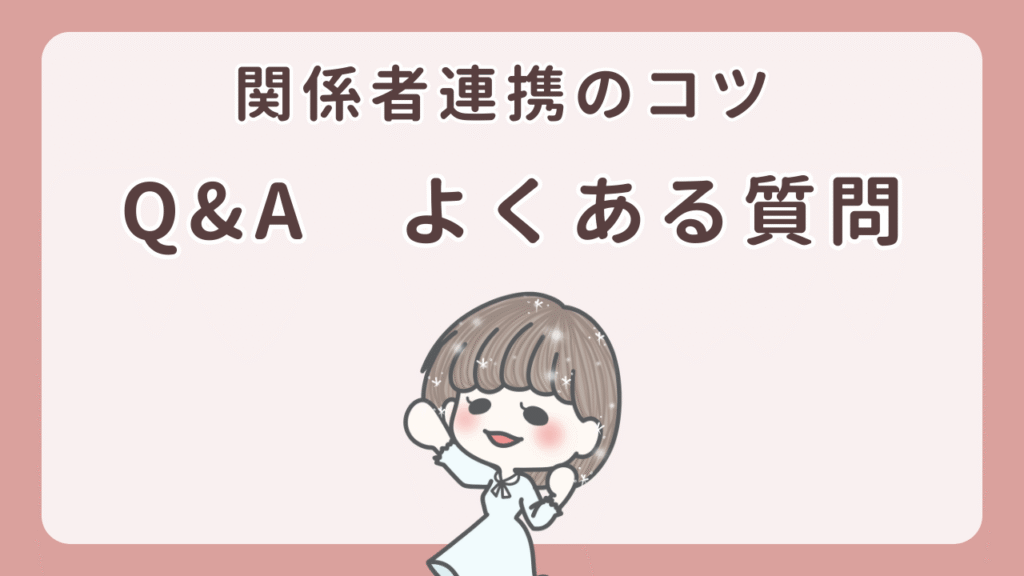
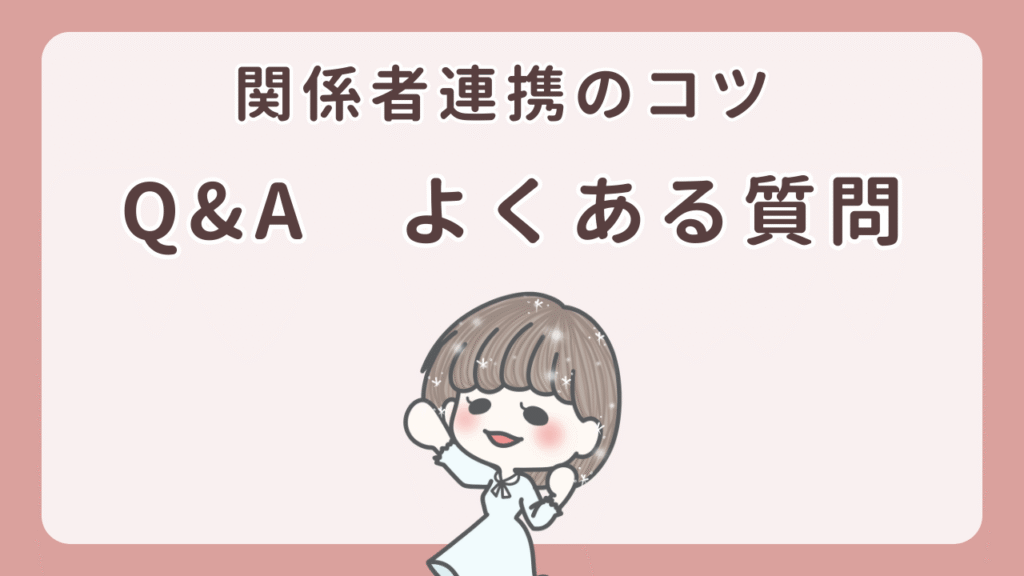
次に、関係者連携に対するよくある質問に対して、なのんだったらどう回答するのかをご紹介いたします。
- 産業医につなぐ=丸投げになりませんか?
-
丸投げは“判断と段取りを放棄”すること。結論先出しで論点を整理し、産業医判断が必要な点を明確に依頼できていれば“連携”です。健康状態への医学的評価、就業可否判断が必要な場合は、必ず産業医意見を伺うこと。
- 本人の同意が取れないときは?
-
原則は同意を得る。ただし緊急性・安全配慮の観点が強い場合は、必要最小限の情報で上長/人事に共有を検討。
- 受診も面談も続けたが改善が乏しい…
-
“様子見る”の再定義を。関係者でアウト要件を設定し、休職や就業制限の検討を。
- クライアント企業から訪問時間が決められています。そのため、人事担当者と話す時間がありません。雑談することで関係構築ができると思っているのですが、本音を聞き出すということが難しいと感じています。
-
関係構築は“会話量”より“印象の質”で決まります。相手の状況に気づいて声をかけたり、メールで一言労いを添えるだけでも関係性が深まります。また、担当者を観察し、担当者が行なっている産業保健業務が少し楽になる小さな支援を提供することで、信頼に変わります。
まとめ
放置しない・抱え込まない・丸投げしない——鍵は設計された関係者連携です。
迷ったら、三者視点(従業員・組織・会社)に戻りましょう。あなたの一歩が、職場の安全と健康を前に進めます。
最後に ― 一緒に学び、実践しよう!
ご覧いただきありがとうございました!
産業保健師の役割や業務に悩んでいる方は、私が主宰する産業保健師育成プログラムで気づきのヒントを得られるかもしれません。
- 受講中に現場で起こっているお悩みをケーススタディとして検討
- 先輩保健師とのグループディスカッションで視野を拡大
産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!
産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。
産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。
一緒に成長していきましょう!


\ 産業保健師の実践力を鍛える/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!


- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!
- 産業保健師の転職支援の実績
- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成
- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%
- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価
- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績
- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施
- 育成プログラムを約20名へ提供
- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価



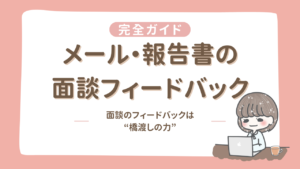
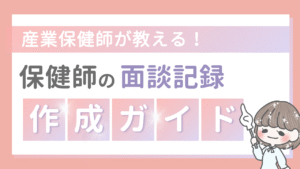
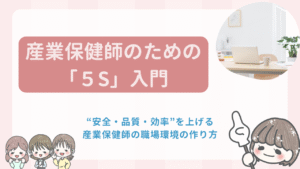
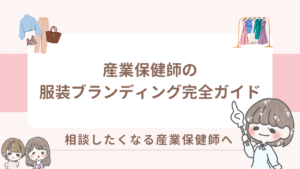

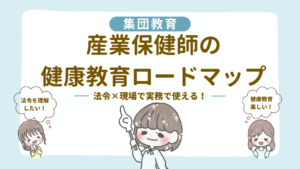
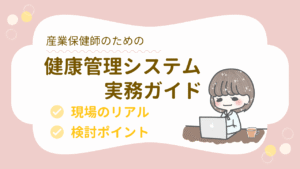
コメント