質問力=産業保健師の戦闘力!上司や産業医相談もスムーズに!“できる産業保健師”の質問ルール
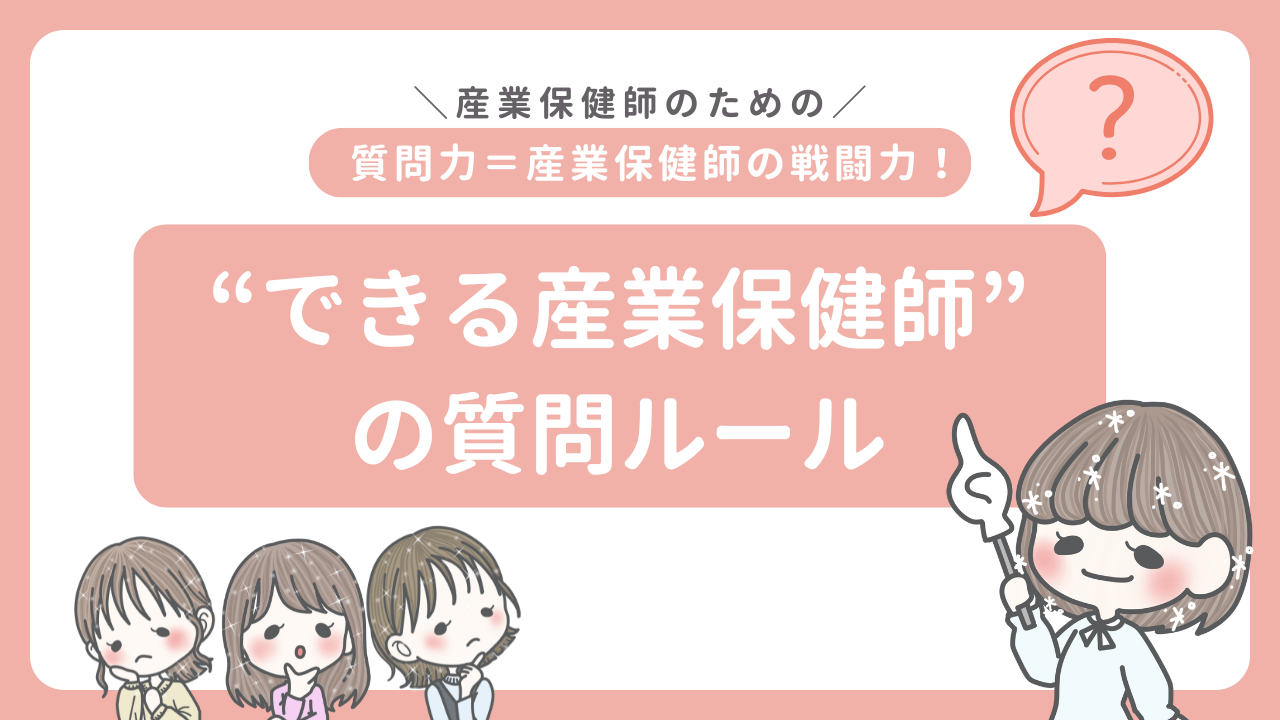
こんにちは!産業保健師のなのんです!
みなさんは、良い質問を意識していますか?
質問の仕方ひとつで、相手との関係や得られる回答の質が大きく変わるため、産業保健師とっては、非常に重要なスキルが質問力です!
産業保健師1年目の方からこんなご相談をいただきました。
 産業保健師1年目
産業保健師1年目メンタル不調のAさん対応を産業医に相談したら明確な答えが得られず「結局、どうしたいの?」と返され、どうしたらいいかわからないから聞いてるのに、聞き方がわからず困っています。



上司や現場との質問の往復が多く時間ばかり過ぎ、タスクが前に進まないんです。



とりあえず全部背景を送って“読んでください”になってしまって、相手の時間をとっている気がしています。



産業医から指摘されて、産業医面談要否を判断する材料の“抜け”に後から気づくことがあります。



なるほど!みなさまは、これから質問力を鍛えるチャンスですね!質問の質を高めることは、信頼関係構築や業務の効率化につながります。
質問が変わると、集まる情報も、信頼も、提案の通り方も、一気に変わります。あなたの“丸投げ”になりがちな相談を、“相手が動きたくなる質問”へ書き換えていきましょう。
- 産業保健師が「質問力」を鍛える重要性を知る。
- “損をする質問”5パターンと、その改善ポイント(NG → OKの具体例で即改善できる)。
- 現場で使える“良い質問”5つの原則を知り、現場で実践できるイメージがつく。
“答えを持っていないから質問する” だけでは、相手の頭と時間は動かない。動かすのは “設計された質問” です。
本記事では 「損をする質問」5パターン と 「良い質問」5原則 を具体例つきで分解し、今日から質問力をレベルアップする実践法をお届けします。


- 新卒から産業保健師歴約15年
- 産業保健師としての企業での活動実績
- 産業保健体制の立ち上げ支援 4社
- オンライン健康セミナー 約10回/年
- メンタル&フィジカルの保健師面談 約30件以上/年
- 営業職・研究職・臨床検査職・事務職・配達業務職・小売業・物流センター・製造業・金融業・IT企業など様々な職種の従業員に対して産業保健サービスを提供
基礎から実践まで、“できる産業保健師”を育成!
産業保健師において質問力が重要スキルな理由
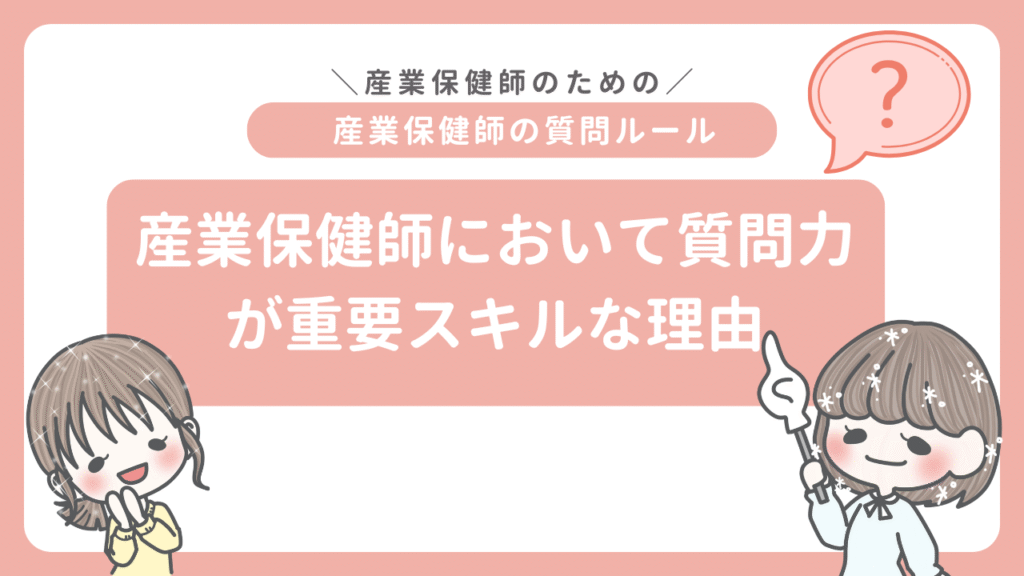
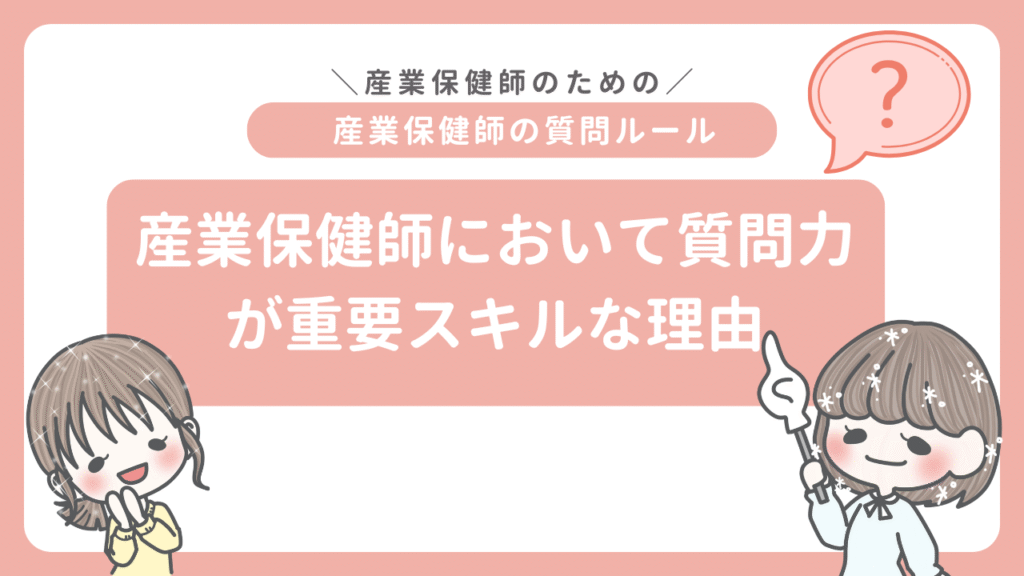
産業保健師のアウトプット(情報精度・提案スピード・信頼・学習・キャリア価値)は、一見バラバラに見えて “質問の質” という一本のテコで同時に押し上げられます。
質問力は単なる会話スキルではなく、限られた時間資源を最大化し、成果を複利化する“レバレッジ”。この章では、質問力がもたらす 5 つの波及効果を分解し、「なぜ最優先で鍛えるべき基盤スキルなのか」をご説明いたします。
適切な質問を行うことで、従業員や上司、人事、先輩産業保健師、産業医など関係者から必要な情報を正確かつ効率的に収集できます。これにより、より具体的な対応策を検討することが可能です。



適切な質問を行わないと、回答者は何を答えていいのかわからず、
正確な回答が得られないんですよね。
効果的な質問により、従業員や職場の課題の背景や詳細を把握することで、暫定的に実行可能な解決策を提案できるようになります。



現場の声を効果的な質問によって収集するからこそ、その解決策を保健師目線で提案することが可能になります!
効率的な質問は無駄を省き、短時間で必要な情報が得られるため、業務全体の効率が上がります。



多くの産業保健師さんたちを見てきましたが、質問力がある方は、産業医や人事への質問から得られた回答が量的にも質的にも高く、産業保健活動が円滑に進んでいく傾向があります!
良い質問は、相手に「自分の話を真剣に聞いてくれている」という印象を与え、信頼関係を築くお手伝いをします。



対従業員への信頼アップだけでなく、上司や人事からも
一目置かれ、相談されやすくなります!
良い質問を行うことで、産業保健スタッフ(産業医や産業保健師など)のコミュニケーションが活性化し、チームの方向性を見極め、意見の意見を引き出すことで、産業保健師としてリーダーシップを発揮できます。



統括保健師時代には、後輩ちゃんたちへ、いろんな角度からの質問をして産業保健の理解度や一人ひとりの考え方を把握し、同じ方向を向いて産業保健活動ができるようにしていました!
産業保健師が『損をする質問』5パターン
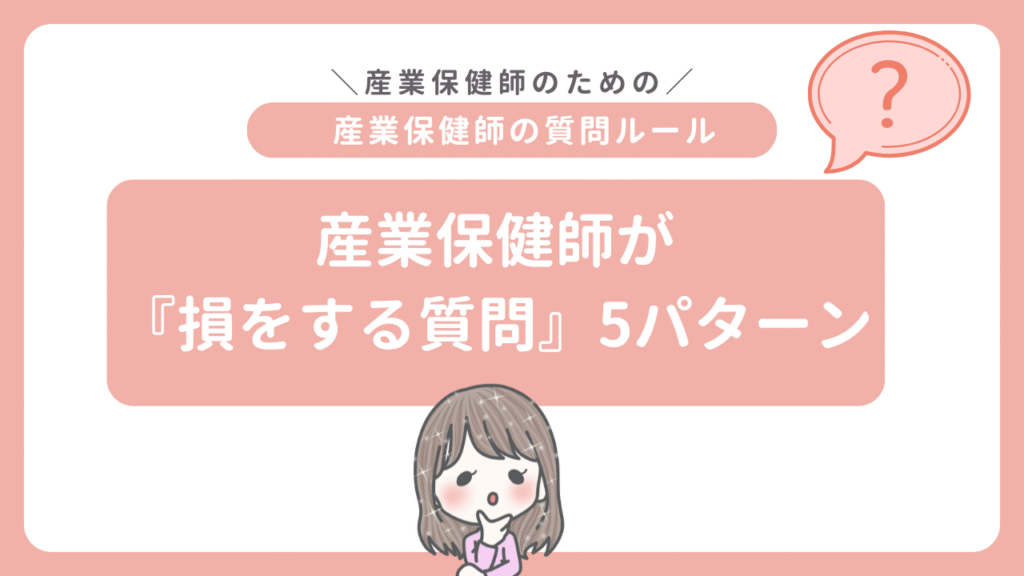
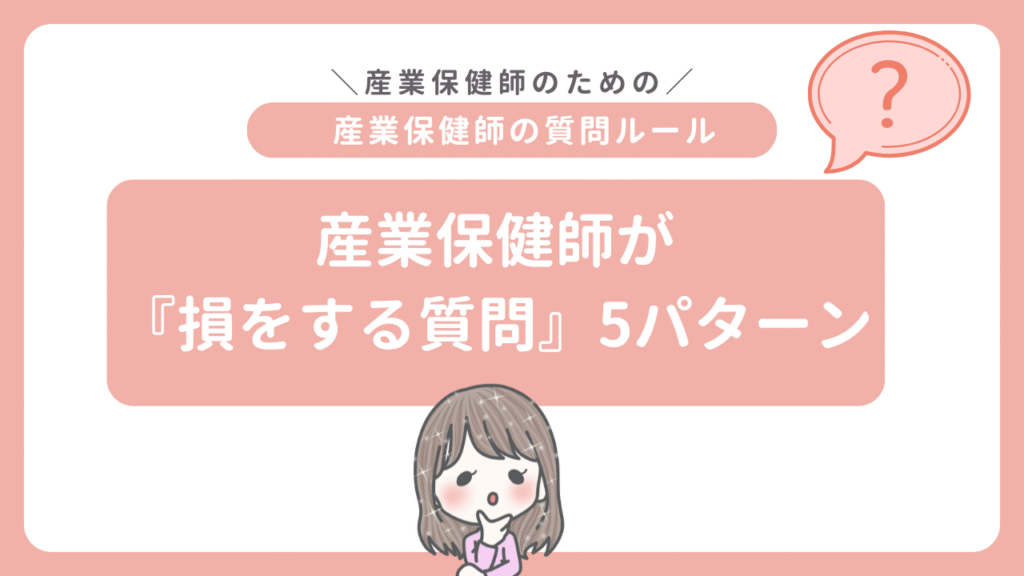
質問力を高めたいと思っても、まず“何をやめるか”が明確でないと改善は進みません。
ここでは、産業保健師の現場で信頼と時間を削る 「損をする質問」5パターン を具体例でご紹介します。以下の5つのパターンは、質問する側が損をしますので、NGパターンを行っていないかチェックしてみましょう!
特に長文の質問です。長々と背景や無駄な説明をしたり、回答に時間がかかる質問は、相手に負担をかけます。また、メールなどのテキストベースでの質問の場合、改行や句読点が全くない質問は読みづらく、自分のことだけ伝えているだけの日記のような質問も同様に、回答者が質問を解読するのに時間がかかり、回答者はストレスに感じます。
具体例:産業医への質問
「上司から体調が悪そうだと言われて、保健師面談を実施したんです。Aさんという方がいて、営業職の方なんですがよく寝付けずたまに突発なお休みをすることがあると言っていました。産業医面談した方がいいと思ったので、Aさんに提案したのですがいいですと言われてしまって、、、、、Aさんの体調について、心配なのですが、産業医面談を行う必要はありますか?」
時間は命そのもの。質問をするときは、相手の貴重な時間を奪っているという認識を持つのが大事。



特に、産業医は保健師よりも時間単価(1時間あたりの時給)が高いです。産業医の時間を奪うということは、産業医が企業へ提供する価値が減るor産業医コストが高くなるということになります。貴重な時間を奪わないという意識が大事ですね!
自分では全く考えない丸投げの質問です。質問が抽象的で、具体性がないため、相手が何を答えればいいのか分からなくなる。とても困る質問です!回答者の気分を害することもあるので要注意です!
具体例:産業医への質問
「保健師面談をしたAさんの体調について、心配なんですが、産業医面談が必要ですか?」



デッドボール級の質問ですね。。。逆に私だったら「必要だと思いますか?必要ないと思いますか?」と聞いてしまう質問の仕方ですね。
簡単にGoogleなどで調べられる内容をそのまま聞いてしまう。
具体例:先輩産業保健師への質問
「一般健康診断と定期健康診断って何が違うんでしょうか?目的ってなんなんでしょうか?」



「私はGoogleじゃない!調べた上で、わからないところを質問して」っと、先輩が忙しい時は先輩にそう感じさせてしまうので、要注意!
相手に責任を押し付けるような質問は避けましょう。
具体例:産業医or先輩産業保健師への質問
「ラインケア研修は、どんなことしたらいいですか?」
具体例:上司への質問
「これをする意味あるんでしょうか?」「これをしたら評価してくれますか?」



こうしたらどう?っと回答した内容をそのまま質問者が提案した時に、
提案がうまくいかなかったら、回答者へ責任転嫁してきそうだなあと感じてしまいますね。上司への質問も威圧感を感じてしまうのでNG。
なぜその質問をするのかが相手に伝わらないと、誤解や不信感を生みます。
具体例:産業医or先輩保健師への質問
「休職率が高いと思うのですが、どう思いますか?」
「職場環境改善のために保健師にできることって何がありますか?」



どう思いますか、っと言われても「高いと思います。」
としか回答できないですよね、、
質問の目的がわからないとどう回答していいかわからず、
質問された側がとてもストレスになるのです。
産業保健師の質問力を伸ばす『得する質問』5原則
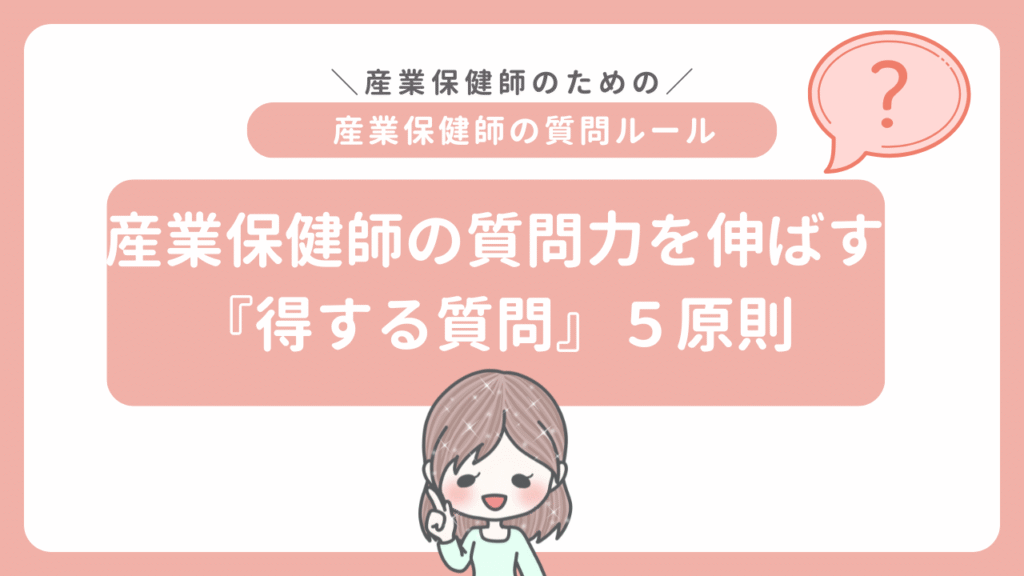
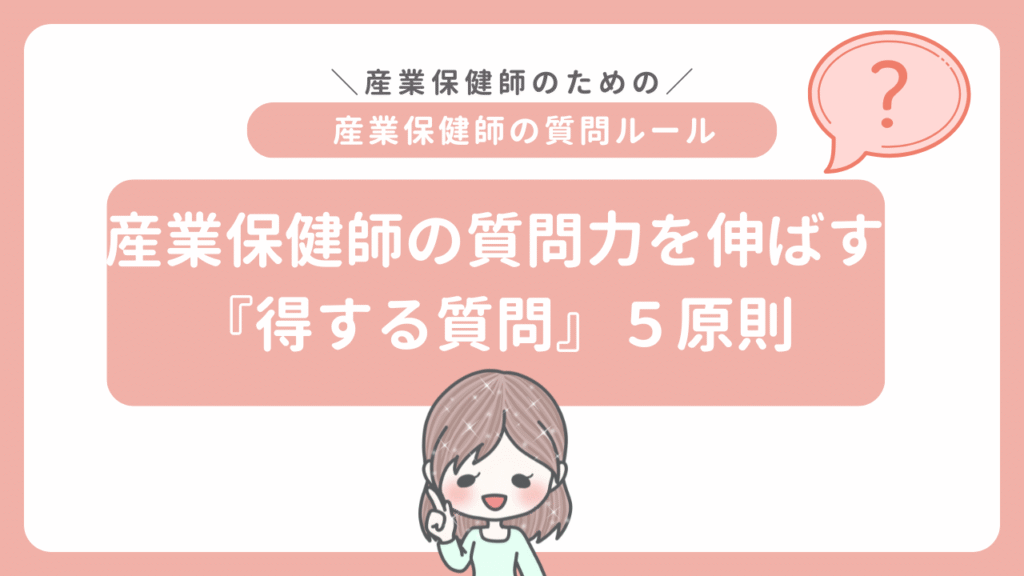
“損をする質問”を手放した次のステップは、成果・信頼・効率を同時に底上げする “得する質問” の型を身体に入れること。
ここでは、産業保健師の現場で汎用性が高く、メール/面談/産業医相談のいずれにも転用できる 5つの原則(簡潔・時間配慮・事前調査共有・好意的回答・ゴール明示) を、実際の良い質問例とともに解説します。
相手が一読して内容を理解できる質問を心がけます。
具体例:上司への質問
「今月の会議では、
①定期健康診断受診状況の報告
②ストレスチェックの結果報告
③現在の産業保健体制の課題の洗い出しを行った結果
の3点を報告しようと思っています。それ以外に◯◯さんが把握しておきたい議題はございますでしょうか?」



上司は忙しいです。忙しい中質問を読んでいるという状況を理解し、一読すれば、全体感を理解できる内容にすることは相手への敬意にもつながります。
相手への感謝を伝え、必要最低限の情報を求める工夫をします。
具体例:産業医への質問
「いつも産業医の視点からアドバイスいただきありがとうございます!お手すきの際で構いませんので、メンタル不調者のAさんについて、産業医面談の必要性についてアドバイスをいただきたいと思っています。
保健師としては、受診勧奨や保健指導を行い改善を試みましたが、勤怠不良や体調の回復が見られず、産業医面談で就業可否の意見をいただきたいと思っています。
Aさんの経過は、面談記録(リンクを貼る)を参照いただき、お手すきの際にご意見頂けますと幸いです。」



感謝の言葉があると誰しも嬉しいですよね。また、あれこれ一気に聞こうとせず、重要度の高いものから質問していくと、相手も回答しやすいですね。
事前に調べたり試みた内容を共有することで、相手が1から全て説明しなければならない負担を軽減します。
具体例:先輩産業保健師への質問
「定期健康診断の受診は、労働安全衛生規則44条に1年ごとに1回、定期にと書かれていることを確認したのですが、定期とはいつのことを指すのでしょうか?もしご存知でしたら、教えていただけると嬉しいです。」



ここまで調べたのね〜っと調べた努力が伝わり+αをたくさん教えたくなりますね!
質問が前向きで建設的であると、相手も積極的に回答しやすくなります。
また、その人だからこそ答えてほしい質問をすることを意識すると気持ちよく回答してくれます。
具体例:先輩産業保健師への質問
「保健師面談を行っていて、肩こり腰痛に悩んでいる方が多いと感じています。
健診分析はこれからなのですが、健診分析を行った結果や保健師面談の声を数値化して、もし肩こり腰痛の健康課題があれば、何かしら取り組みたいと思っています。
肩こり腰痛を予防するために◯◯先輩は、これまでどんな取り組みをされてきたか、もしそのような知見がありましたら、アドバイスいただけると大変嬉しいです。」



保健師面談で聴取した声だけでなく健診分析を行い現状把握を行うという前向きに活動していくことを伝えつつ、先輩の知見も知りたいという言葉は、教えたくなりますよね。
何を得たいのか、具体的に示します。
具体例:上司への質問
「◯◯さん(不調者の上司)からご依頼いただきました保健師面談ですが、保健師による体調確認の面談を行う前に、以下の3つ
①勤怠:突発的なお休みや早退、遅刻があるか?
②パフォーマンス:以前と比べてパフォーマンスや業務遂行能力は落ちているか?
③安全:安全に作業が行えているか?
について現在抱えている課題や問題点をご共有いただきたいのですが、可能でしょうか?」



どんな情報を得たいのかを具体的に書くことで必要な情報を得やすくなりますね!
おすすめ書籍
私が産業保健師5年目くらいの頃に産業医よりおすすめされ熟読していた書籍をご紹介します。
この書籍を読むと、考えないで質問をすることの恐ろしさを痛感します。
現場で効く!産業保健師の質問力強化4ポイント
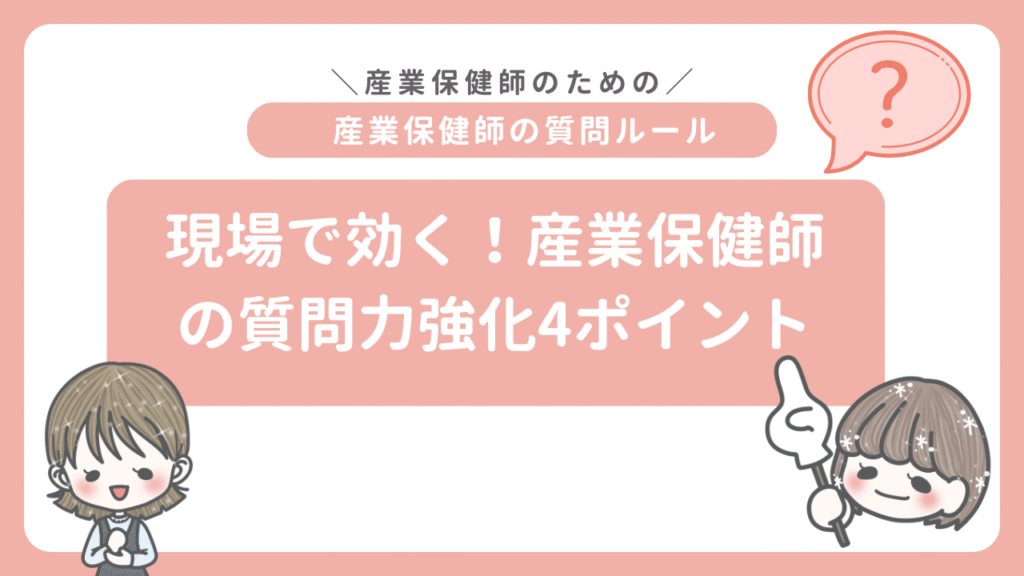
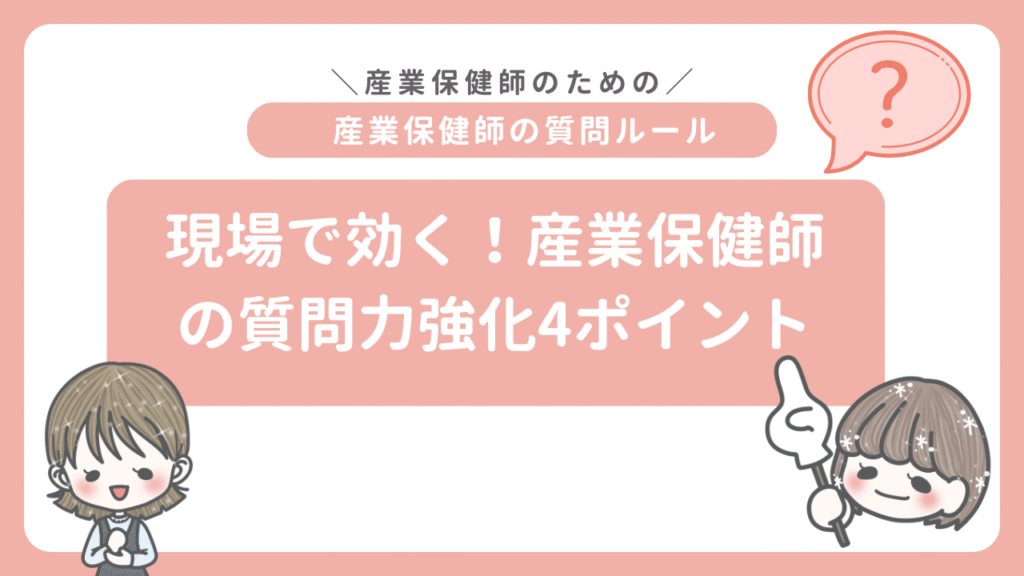
“NG質問→良い質問”の構造がわかったら、次は日常で再現するための行動ポイントを押さえる段階です。
ここでは、質問を「思いつき」ではなく「設計されたレバレッジ」に変える4つの基本動作 ― 準備 / 良問活用 / 目的設定 / 実行とフィードバック ― をご紹介します。
相手やテーマについて事前に情報を集め、何を聞きたいのか明確にしておく。
相手が答えやすく、回答したくなる「良い質問」を行う。
質問をする目的を明確にし、会話の方向性を見失わないようにする。
自分の時間を割いて回答したのにも関わらず、何も実行されていなければ、相手はあなたの質問に答えても意味がないと考えます。必ず、何かしらのアクションを起こし、アドバイスを受けて、行動した結果を報告する。
まとめ:質問力は産業保健師が鍛えるべき基盤スキル
質問力は、産業保健師として産業保健活動を効果的に円滑に行う上で欠かせない重要なスキルです。日々の業務で意識的に質問力を鍛えることで、より良い職場環境づくりと従業員支援に貢献できます。



質問力は意識して行っていけば誰しも身につけられますし、他社でも通用するスキルです!必ず磨いていきましょう!
最後に ― 一緒に学び、実践しよう!
ご覧いただきありがとうございました!
産業保健師の役割や業務に悩んでいる方は、私が主宰する産業保健師育成プログラムで気づきのヒントを得られるかもしれません。
- 受講中に現場で起こっているお悩みをケーススタディとして検討
- 先輩保健師とのグループディスカッションで視野を拡大
産業保健の実務に関するお悩みがある方は、育成プログラムに参加することで新たな気づきや解決のヒントが得られます。みんなと一緒に成長していきましょう!
産保ゆめUPスクールでは、産業保健師の基礎的な実践力を鍛える産業保健師育成プログラムサービスをご提供しています。
産業保健師に必要なスキルや基礎知識、企業で働く上での考え方を網羅し、実践力を鍛え、産業保健師としての成長と自己実現につながる講座となっています。
一緒に成長していきましょう!


\ 産業保健師の実践力を鍛える/
最後までお読みいただき、ありがとうございました!これからも産業保健師としての成長を応援しています!


- 産業保健師の転職から成長までトータルサポート!
- 産業保健師の転職支援の実績
- 延べ約50名の転職相談を担当し、内定率90%を達成
- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ支援により、書類通過率90%
- 模擬面接+フィードバックにより、「自信を持って面接に臨めた」と高評価
- 産業保健師の実務相談および育成プログラムの実績
- 個別実務相談(事後措置・休復職支援など)を約10名分実施
- 育成プログラムを約20名へ提供
- 産業保健師向け勉強会(つながる産保カフェ)を毎月開催し、延べ参加者数30名以上、「勉強になった」「新しい視点を得られた」と高評価

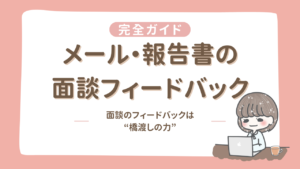
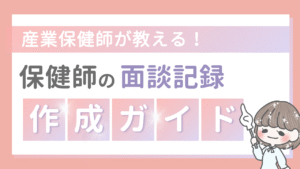
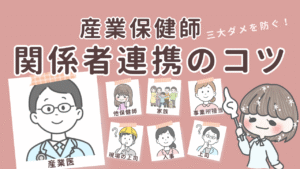
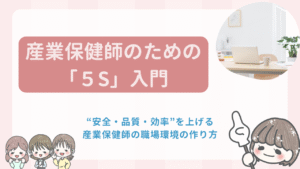
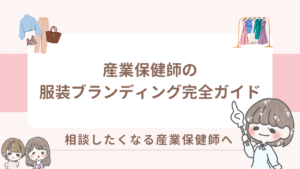

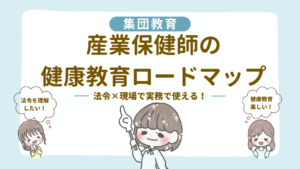
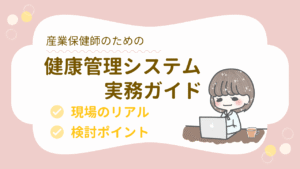
コメント